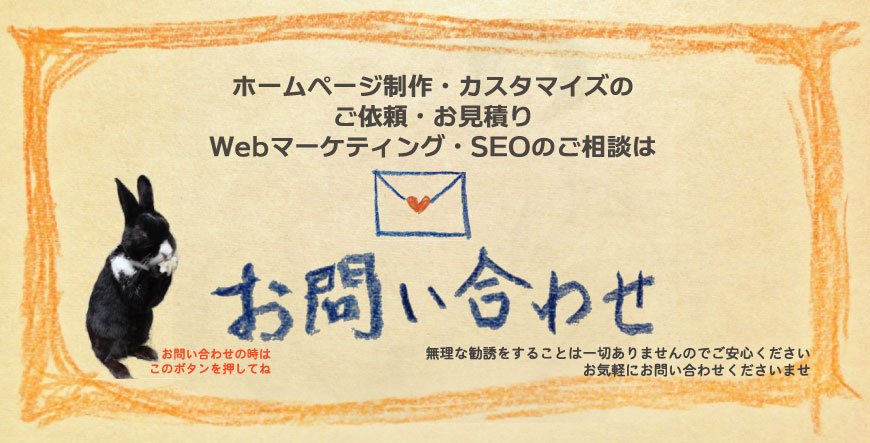夜のとばりが降りた町を、俺は一人、重い足取りで歩いていた。
今日一日の仕事を終え、事務所のシャッターを下ろしたばかりだ。
コンクリートのひび割れや、古びた木材の匂いが、まだ鼻腔に残っている。
父が残したこの工務店を継いで、二年。しかし、現実は容赦なかった。業績は上がるどころか、ジリ貧の一途を辿っている。
このままでは、どうなる? 娘のひまりは、もうすぐ小学校に上がる。妻の顔にも、最近は笑顔が少ない。この小さな工務店が潰れるということは、俺の人生が、家族の未来が、文字通り立ち行かなくなることを意味していた。
まるで、底なし沼に足を取られ、ゆっくりと、だが確実に沈んでいくような感覚だ。呼吸が苦しい。この重圧が、いつか俺を押しつぶしてしまうのではないかと、夜な夜な悪夢にうなされる。
ふと、顔を上げると、鉛色の空の切れ間から、わずかながら繊月が顔を覗かせていた。
細く、か細い光は、まるで今の俺の心境を表しているかのようだ。
この工務店が、俺自身が、まるでこの月のように、闇の中に飲み込まれて消えてしまうのではないか。
冷たい夜風が頬を撫でる。その風の中に、確かに父の面影を感じた。
父は、この町で、この小さな工務店を、たった一人で守り抜いてきた。どんな苦境も、その大きな背中で乗り越えてきたはずだ。
だが、俺には、父のようにはできない。
父が築き上げてきたものを、俺の代で、この手で終わらせてしまうのか。その想像が、俺の胸を締め付ける。
繊月は、見る間に厚い霧の中に溶け込んでいく。
明日、この霧が晴れる日が来るのだろうか。
それとも、このまま深い闇に閉ざされて、俺たち家族の光も、永遠に失われてしまうのか。
俺には、まだ、何も見えない。ただ、この胸の奥底で、わずかながらの希望の光を探し続けることしかできなかった。
沈みゆく船の上で、必死にオールを漕ぐように、ただ藻掻き続ける日々だった。