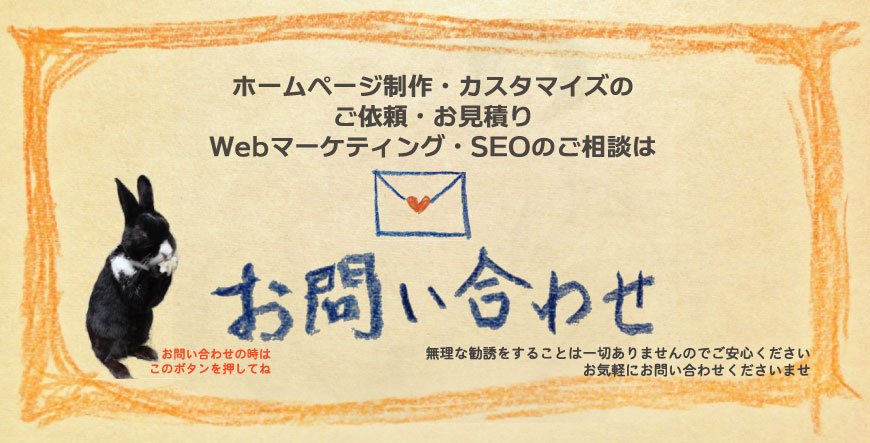俺の名前は健太。この町で小さな工務店を営む、しがない中年だ。30代後半、とっくに若手とは言えない歳になったが、相変わらず現場で汗を流す毎日だ。昔は下請けの仕事でどうにか食いつないでいた。
だが、それも長くは続かない。長年つきあいがあった常連のじいさん、ばあさんたちが店を畳み始め、仕事はめっきり減った。新規の客なんて、ここ何年もご無沙汰だ。
藁にもすがる思いでチラシを撒いたこともあった。だが、ポストに投函されたそれは、ゴミと一緒に捨てられるだけだった。
1年前、たまたま電話営業がかかってきた業者に、サブスクのホームページ制作を頼んだ。月々1万円。これでも俺には清水の舞台から飛び降りるような金額だったが、ホームページがあれば客が来る、と甘い言葉に誘われたんだ。
だが、結果は変わらなかった。サイトはある。だが、そこから仕事が舞い込むことはなかった。
そんなある日、Instagram集客の噂を耳にした。
顔出しなんて柄じゃない。だが、他に手立てもない。妻に頼んで、店のインスタグラムアカウントを作ってもらった。
妻は店の事務も見てくれている。ホームページの更新も、SNSの管理も、すべて妻に任せっきりだった。
だが、それも一年が過ぎた。インスタグラムからの問い合わせはゼロ。投稿するたびに虚しい気持ちになるだけだった。
途方に暮れていたある夜、ふと、高校の同級生だったアイツの顔が浮かんだ。
一平。高校を卒業して以来、年に一度会うか会わないかの仲だが、困った時に頼れる友人は、アイツしかいなかった。一平は、今じゃWeb制作会社の社長だ。
金融系のデカい会社で営業をやって、その後20代で独立したと聞いていた。人前に出るのが苦手な奴だったが、腕は確かだと評判だった。
一平の会社のホームページを覗いた。洗練されたデザイン。プロの仕事だと一目でわかる。だが、俺が求めるのはそんな立派なサイトじゃない。客を呼べるサイトだ。
俺は震える指で、久しぶりに一平に電話をかけた。呼び出し音が何度か鳴り、一平の声が聞こえた。
「おう、健太か。どうした、珍しいな、お前から電話なんて」
俺は単刀直入に用件を切り出した。
「実はな、一平。ちょっと相談したいことがあってよ。今、時間あるか?」
一平は少し考えたようだったが、すぐに承諾した。
「いいぜ。明日、そっちの店に行くよ」
一平は、俺がインスタグラムを始めたことで俺の存在に気づいていたらしい。
だが、何も言わずに、ただ俺の様子を見守っていたという。まったく、食えない奴だ。
だが、今の俺には、アイツの助けが必要だった。一平がどんな顔をして俺の店に現れるのか、俺は不安と期待がないまぜになった気持ちで、夜空を見上げた。明日から、何かが変わるかもしれない。そう信じるしかなかった。