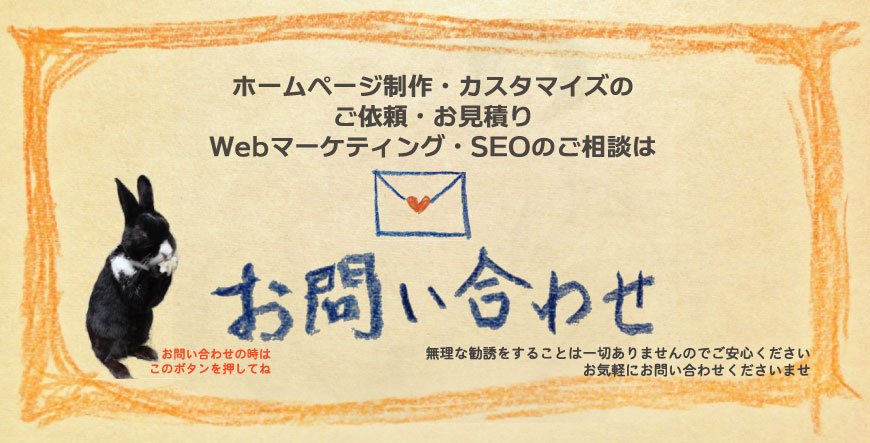薄暗い事務所で、俺は腕を組み、重い溜息をついた。壁に貼られた昔ながらのカレンダーは、日付だけが無情に進んでいく。30代後半の男が、こんなにも手詰まりになるとは思わなかった。
娘は幼稚園の年長で、そろそろ小学校に上がる。あの子のためにも、この工務店を潰すわけにはいかない。
俺がこの工務店を継いで、もう2年以上になる。親父が築き上げてきたものを、俺がダメにするわけにはいかない。
だが、現実は甘くない。昔は親父の代からの常連客がいて、下請けの仕事も細々と入っていた。だが、高齢化の波には逆らえない。
馴染みの客はじいさんばあさんになり、次々と店を畳んでいった。そうなると、俺の工務店に直接仕事が舞い込むことも減る。新しい客は来ない。チラシを撒いても、まるで効果がないのは分かりきっていたことだ。
1年前、たまたま電話がかかってきた業者の口車に乗せられ、月1万円でホームページを作った。サブスクタイプのやつだ。ホームページがあれば、きっと客が来る。そう信じていた。
「1ページだけで十分ですよ」
担当はそう言っていた。確かにそれでいいと思ったし、必要最低限の情報は載せた。
だが、結果は惨敗だ。誰も俺のホームページなんて見ちゃいない。飾りだけの存在だ。
そして、妻の美咲に任せきりにしていたInstagramも、まるっきり音沙汰なし。投稿するたびに、この虚しさは何なんだ、と自分に問いかける日々だった。
そんな俺の苦境を知ってか知らずか、この町の別の工務店が、最近目覚ましい勢いで客を増やしているという噂を耳にした。聞けば、そこの社長は元ホストで、Web集客に力を入れているらしい。公式サイトのコンテンツマーケティング、SEO、そしてSNS集客で、地域のシェアをどんどん奪っているという。同じ高校の同級生らしいが、俺とは接点がなかった。
「ピンポーン」
事務所のチャイムが鳴り、俺はハッと顔を上げた。玄関のドアを開けると、そこに立っていたのは、高校時代と変わらない少し体格の良い男。一平だった。
「よう、健太。久しぶりだな」
一平は軽く手を挙げ、俺の顔を見てにやりと笑った。人前に出ないことを信条としているような奴だが、俺の前に現れた彼は、いつもの飄々とした態度だ。
「おう、一平。悪ぃな、急に呼び出して」
俺は一平を事務所の中に招き入れた。簡素なパイプ椅子に腰掛ける一平と、その向かいに座る俺。昔話に花を咲かせる間もなく、俺は本題に入った。
「見ての通りだよ。このざまだ。仕事が減って、どうにもならん。それで、お前に相談したいことがあるんだ」
一平は黙って俺の話を聞いていた。俺は現状を包み隠さず話した。チラシの効果のなさ、ホームページの失敗、そして一年続けたInstagramの不発。話しているうちに、情けない気持ちが込み上げてくる。
一平は腕を組み、天井を見上げた。そして、静かに口を開いた。
「健太。お前がWeb集客を甘く見ていたのは、薄々感づいていたぜ。言い方は悪いけどな」
その言葉に、俺は思わず息を呑んだ。