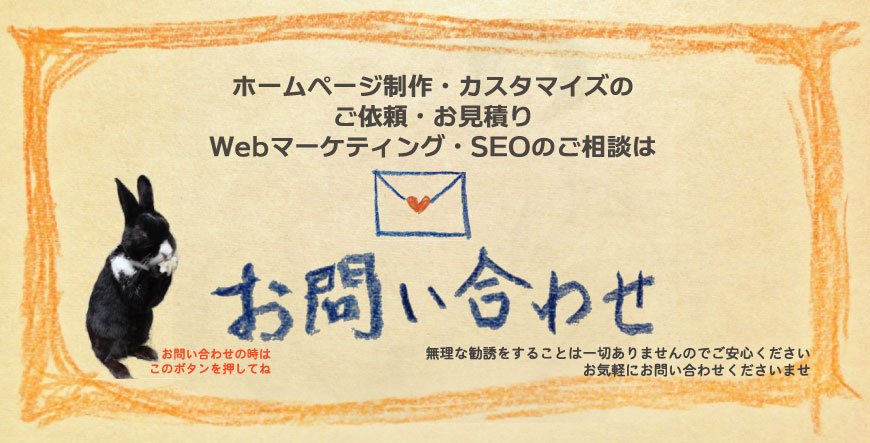「なるほどな……。健太、お前んとこの顧客は、どんなことで困って、お前に何を期待して依頼してくるんだ? そして、お前は、その期待にどう応えてきたんだ?」
一平の問いは、俺の頭の中を整理していくようだった。俺は、これまで漠然とやってきた仕事のやり方や、顧客との関係性を、初めて客観的に見つめ直すことになった。
「そうだな……。例えば、急な水漏れとか、ドアの建て付けが悪くなったとか、そういう緊急性の高い依頼が多いな。あとは、高齢の客だと、ちょっとした段差をなくしたいとか、手すりをつけたいとか、バリアフリーに関する相談も増えてる。俺は、そういう時、すぐに駆けつけて、できる限り早く解決するようにしてるつもりだ。あと、小さな仕事でも嫌がらずに引き受けてきた。親父の代からだから、この地域のことは隅々まで分かってるし、顔馴染みも多いから、安心して任せてもらえるってのはあるかもしれねえな」
俺が訥々と語るのを、一平は黙って聞いていた。時折、頷きながら、俺の言葉の端々に隠された意味を探っているようだった。
「なるほど。迅速な対応、地域密着、そして小さな仕事も厭わない姿勢。それがお前んとこの強みになりうるな。だが、健太。お前、新規集客ばかりに気を取られてないか?」
一平の言葉に、俺はギクリとした。まさにその通りだった。新規の客を獲得することばかり考えて、目の前の大切なものを見失っていたのかもしれない。
「…そう、かもしれないな。仕事が減ってくると、どうしても新しい客を探すことばかり考えてしまう」
「それが悪いわけじゃない。だが、既存の顧客をないがしろにするのはもっと悪い。考えてみろ、健太。今までお前んとこに仕事を依頼してくれた客は、お前に何を求めてきたんだ? そして、お前は、その期待にどれだけ応えられてきたんだ?」
一平の問いに、俺は改めて考えさせられた。俺の工務店は、ただ単に家を修理するだけの場所ではない。地域の人々の生活に寄り添い、困り事を解決する、いわば「町の便利屋」のような存在だったのかもしれない。
「…そうか。確かに、俺のところに依頼してくれる客は、単に工事をしてほしいだけじゃなくて、困った時に頼れる相手を求めてるのかもしれないな。だから、ちょっとしたことでも相談してきてくれてたんだ」
俺が納得すると、一平はさらに問いかけてきた。
「じゃあ、健太。お前、営業の経験は?今まで、今の会社以外で営業をした経験はあるのか?」
突然の質問に、俺は少し戸惑った。首を横に振った。
「いや、ないな。高校を卒業してしばらくフリーターをやって、その後、同業種の別の工務店で十年以上、ひたすら職人として修行してきたんだ。2年前に親父が他界して、それで跡を継いだもんだから、営業や経営の経験は全くないんだ」
俺の言葉に、一平は呆れたような、それでいてどこか納得したような顔をした。
「なるほどな。じゃあ、まずはそこからだ。工務店っていうのはな、ただ良い仕事をするだけじゃ客は来ない。自分たちの強みを、ちゃんと客に伝えなきゃ意味がないんだ。だが、お前は無意識のうちに営業をしてきたんだぜ。日々の仕事の中で、顧客との信頼関係を築き、次の仕事につなげてきた。それがお前の営業だ。その経験は、今の状況を打破するためにも必ず役に立つ。お前は、この工務店の『顔』なんだ。その自覚を持って、もう一度、自分の強みを絞り出してみろ。お前が提供できる、他のどこにもない価値は何だ?」
「強み…他のどこにもない価値、か……」
俺は呟いた。自分の工務店の強みなんて、考えたこともなかった。ただ、親父の背中を見て、真面目に仕事をしてきただけだ。
「そうだ。それをマーケティング用語では『USP(Unique Selling Proposition)』って言うんだ。他社にはない、お前たちの工務店だけの魅力。お客さんが『ここにお願いしたい!』って思う、決定的な理由だ」
一平はそう言って、パソコンの画面に何かの資料を表示させた。
「例えば、お前んとこは何ができるんだ? リフォームもするのか? 新築も?」
「ああ、リフォームも新築も、小さな修繕からバリアフリーまで、何でもやってる。俺自身は、大工仕事から設備工事まで、一通りこなせる」
俺が答えると、一平は考え込むように顎に手をやった。
「なるほどな。何でもできるってのは強みだけど、それが却って客には伝わりにくいこともある。まずは、お前たちが特に得意なこと、お客さんに喜んでもらってることを洗い出すところから始めよう。そして、それをどうやって客に伝えるか、だ」
一平の言葉に、俺は頭の中が整理されていくような感覚を覚えた。
今まで漠然と抱えていた課題が、少しずつ明確な形になっていく。これが、Web集客というやつなのか。俺は、食い入るように一平の言葉に耳を傾けた。
俺はただの職人ではなかった。この工務店を背負う、経営者なのだ。
そして、俺の強みは、この地域で培ってきた信頼と、一つ一つの仕事に真摯に向き合う姿勢にある。それこそが、俺の工務店が生き残るための道標なのかもしれない。
俺は、一平の言葉を胸に、改めて自分の工務店の「価値」とは何かを深く考え始めた。