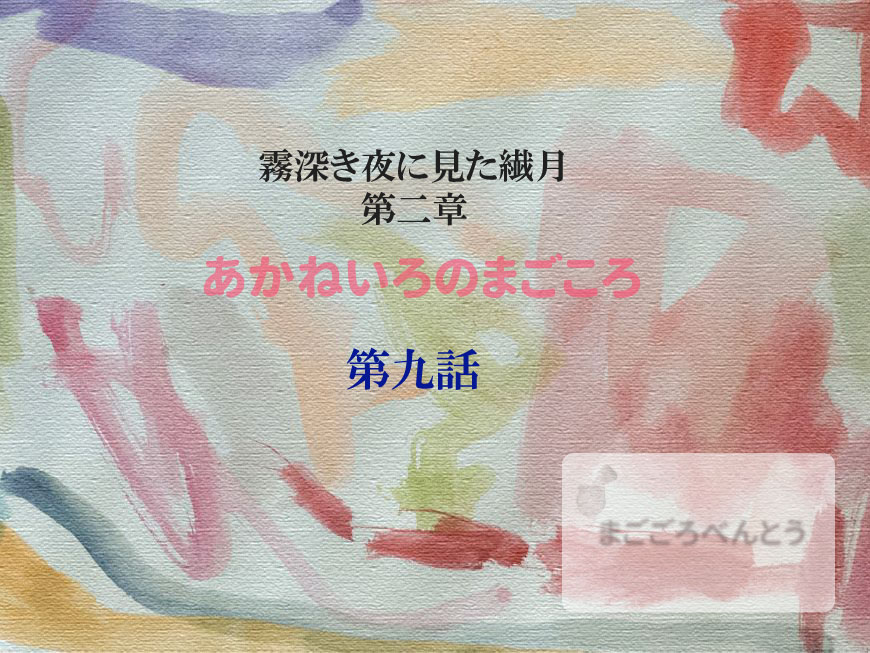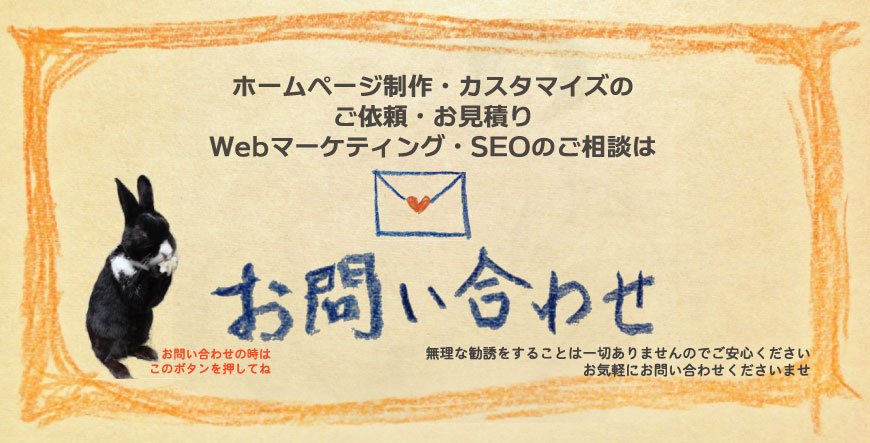健太の事務所を後にした真紀は、足早に「まごころ弁当」に戻った。浩二に、今日健太から聞いた話を早く伝えたい。
特に、浩二のフレンチの腕を活かした「ちょっと良いフレンチ弁当」のアイデアは、希望の光に見えた。
その日の営業が終わり、片付けも一段落した頃、真紀は恐る恐る浩二に切り出した。
「ねぇ、浩二さん。健太さんがね、浩二さんのフレンチの腕を活かしたお弁当を期間限定で出してみたらどうかって……」
浩二は、顔についた小麦粉を拭いながら、怪訝そうな顔で真紀を見た。
「フレンチの弁当? うーん、どうだろうな。仕込み時間もかかるし、原価も高くなる。今出してる弁当の業務に支障が出るかもしれないし、それに、一時的にやったところで意味があるのか?」
浩二の反応は、真紀の期待とは裏腹に、消極的だった。彼は、厨房での効率とコストを何よりも重視する。
「せめて、予約をもらえたら、考えられないこともないが……。今の状態で、そんな特殊な弁当が売れるかな?」
浩二の現実的な言葉に、真紀の心は少ししぼんでいく。新しいことに挑戦することへのためらいが、浩二にはあった。
真紀は、浩二の言葉を聞きながら、ある日のことを思い出していた。それは、健太宅に子どもたちを迎えに行った帰り際、美咲が何気なく語っていたことだ。
「真紀さん、今の時代って、本当に情報が多すぎて、人間ってすぐに忘れちゃうらしいのよ。昔、すごくお気に入りだったお店のこととか、美味しかった商品のこととか、お気に入りだったことすら忘れちゃうって」
「そうなの? なんか、寂しいわね」
「そうなのよ。でもね、健太が言ってたんだけど、そういう時にSNSってすごく有効なんだって。新しくお客さんを呼ぶだけじゃなくて、『ああ、そういえばあのお店あったな』とか、『あの商品、美味しかったな』って思い出してもらう、一つのきっかけとしても使えるって。忘れてた記憶を呼び覚ます、っていうのかな」
真紀の頭の中で、美咲の言葉が鮮明に蘇る。
そうだ、フレンチ弁当は新規のお客さん獲得のためだけじゃない。
以前の飲食店時代に「まごころ弁当」の味を知っていたお客さん、浩二の腕を知るお客さんに、「そういえば、あのお店にあったちょっと贅沢な洋食メニューの味、なんとなく好きだったな」と思い出してもらうきっかけになるかもしれない。そして、それが「もう一度食べてみたい」という感情に繋がるかもしれない。
真紀は、もう一度浩二に向き直った。彼の才能を眠らせておくのはもったいない。そして、この苦境を打開するためには、ただ現状維持をするだけではダメだ。思い出してもらうための戦略。それが、今、必要なのかもしれない。