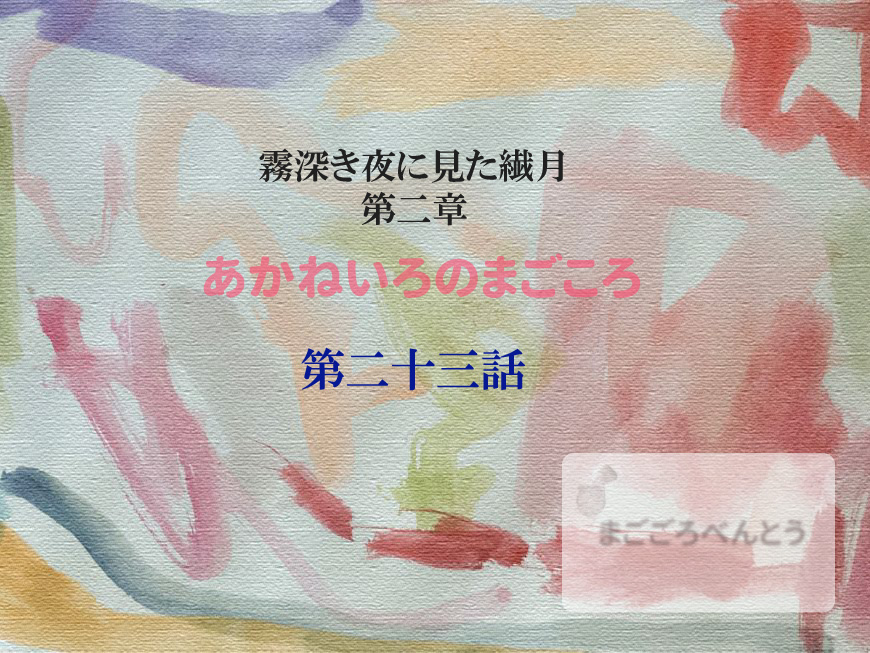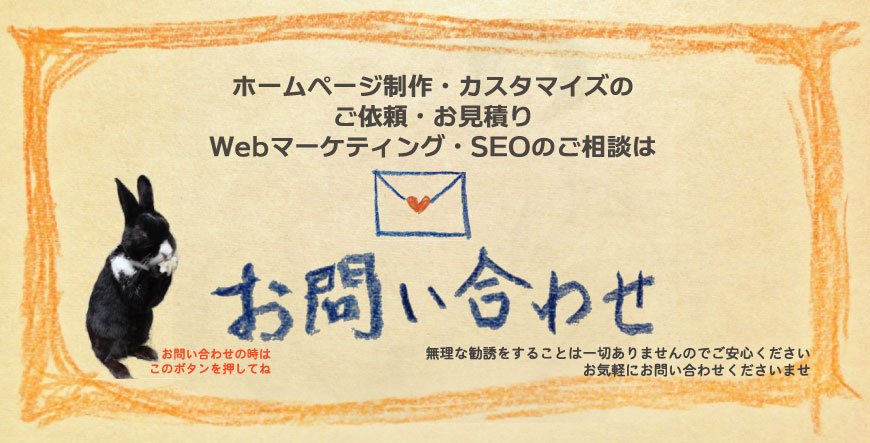祭りの翌日、「まごころ弁当」の朝は、心地よい疲労感とともに始まった。
普段通りの仕込みの時間だが、厨房の空気は少し違っていた。
「昨日は……凄かったな」
浩二が鍋を火にかけながら、独り言のように呟いた。
「ええ。お断りしてしまったお客様には申し訳なかったけど……でも、あんなに並んでくれるなんて」
真紀は、昨日の喧騒を思い出しながら、エプロンの紐を締めた。だが、感傷に浸っている暇はない。一平の言葉が、耳に残っている。
『今日のこの熱を、どうやって冷めない資産として残すかだ』
真紀は作業の合間を見て、スマートフォンを手に取った。Instagramのアイコンを開く指が少し震える。昨日の祭りの最中、大輝の協力でインフルエンサー騒ぎがあった後、必死に配ったチラシ。その効果がどう出ているか。
画面を開いた瞬間、真紀は息を呑んだ。
フォロワー数が、一晩で数百人増えている。だが、驚くべきは数字だけではなかった。DM(ダイレクトメッセージ)の通知バッジが、見たことのない数になっているのだ。
『昨日は完売残念でした! 次はいつ販売しますか?』
『チラシもらいました。フレンチ弁当、絶対食べたいです!』
『並んでたけど買えなかった〜。予約はできますか?』
『運良く買えました! テリーヌ最高でした!』
そこにあるのは、無機質な数字ではなく、一人一人の「温度」を持った言葉だった。
「浩二さん、ちょっとこれ見て」
真紀はスマホの画面を浩二に見せた。
「こんなに……メッセージが来てるの。みんな、次を待ってくれてる」
浩二は手を拭き、画面を覗き込んだ。老眼を気にして少し顔をしかめながらも、一つ一つのメッセージを目で追う。
「……『テリーヌ最高でした』か。……そうか」
浩二の口元が、わずかに緩んだ。厨房の中で完結していた彼の仕事が、スマホという小さな窓を通じて、確かに誰かに届き、反響として返ってきている。その実感は、職人としての矜持を静かに、しかし強く揺さぶった。
「真紀、返事はどうするんだ? これ全部に返すのか?」
「うん、やるわ。だって、『またお知らせします』って約束したんだもの」
真紀はその日の休憩時間、そして帰宅後の時間をすべて使い、一件一件丁寧に返信を書き始めた。AIによる自動返信でも、コピペの定型文でもない。相手の言葉に合わせた、生身の人間としての返信だ。
『並んでいただいたのに申し訳ありませんでした。次回は必ず!』
『感想ありがとうございます! シェフの浩二も喜んでいます』
それは気の遠くなるような作業だったが、不思議と苦ではなかった。画面の向こうに、あの行列の人々の顔が見える気がしたからだ。
そして、その夜。真紀はInstagramに一枚の写真を投稿した。
それは、祭りで完売した直後の、空っぽになったショーケースと、疲れながらも充実した笑顔を見せる浩二と真紀のツーショット写真だった。一平のアドバイス通り、真紀が慌てて撮影したものだ。画質は決して良くないし、少し手ブレもしている。いわゆる「インスタ映え」する綺麗な写真ではない。
しかし、投稿文には嘘偽りのない感謝と、次回の店舗での「フレンチ弁当予約会」の告知を添えた。
反応は劇的だった。投稿から数分で「いいね!」がつき始め、コメント欄には「予約します!」「行きます!」という声が溢れた。
さらに、予想外の反応はGoogleマップでも起きていた。
「まごころ弁当」のビジネスプロフィールに、祭りの写真が「お客様」によって投稿され始めたのだ。
『お祭りで発見。すごい行列で買えなかったけど、店員さんの対応が素敵だった』
『次回リベンジします』
買えなかった客までもが、写真を投稿し、口コミを書いている。
一平が分析していた通り、GoogleのAIはこの動きを見逃さなかった。
短期間に集中した「実体のある写真(UGC)」、活発な「口コミ」、そしてそれに対する店主からの丁寧な「返信」。
これらの要素が、「この店は地域で活動している信頼できるビジネスである」という強力なシグナルとなり、Googleマップ上での「まごころ弁当」の表示順位を、じわりじわりと押し上げ始めていた。
ユウキの会社が失った「信頼」という資産が、ここでは泥臭い手作業によって、着実に積み上げられようとしていた。