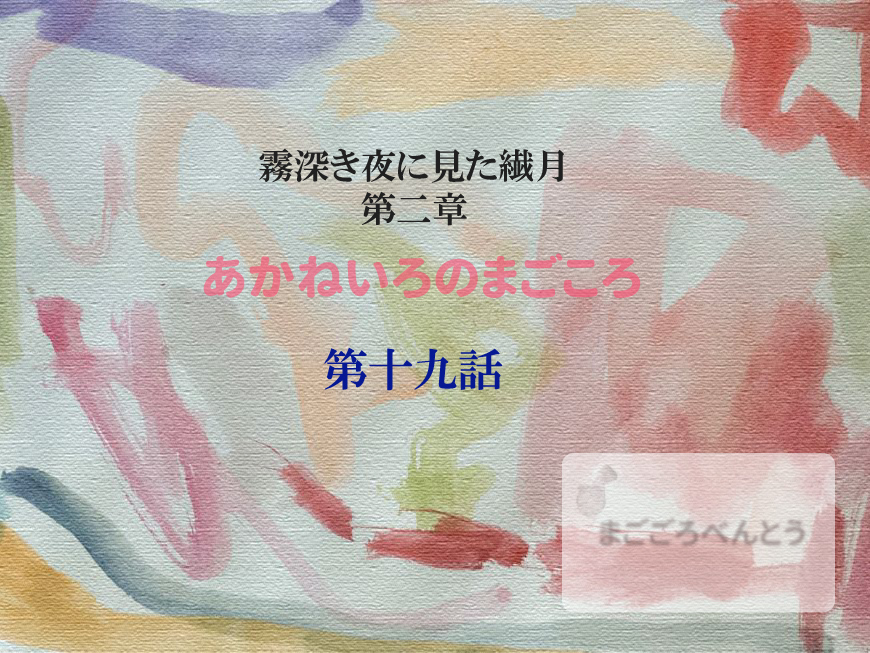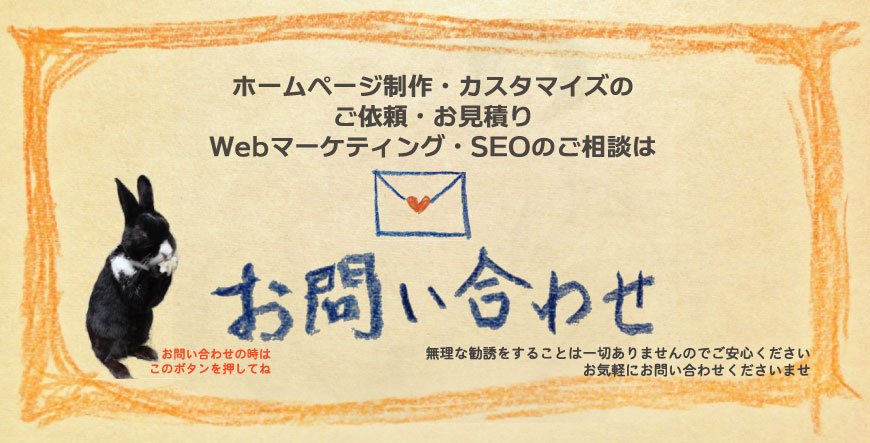地域の神社の境内は、湿気を帯びた熱気と、ソースが焦げる香ばしい匂いで満たされていた。祭りの喧騒は、人々の理性を少しだけ麻痺させる力を持っている。「まごころ弁当」が出店した仮設テントの前には、予想以上の行列ができていた。
「いらっしゃいませ。限定のフレンチ幕の内、残りわずかです」
真紀の声は、祭りのざわめきの中でもよく通った。その横で、浩二が鬼気迫る表情で盛り付けを行っている。額に汗を浮かべ、無駄のない動きでソースをかける姿は、屋台の親父というよりは、戦場に立つ料理人のそれだった。客たちは、プラスチック容器の中で輝く料理の彩りに目を奪われ、「これ、本当にお弁当?」と驚きの声を上げていく。
昼のピークが過ぎ、少しだけ客足が途切れた頃、一人の男がテントの前に現れた。洗いざらしのシャツに身を包んでいるが、その目は弁当の陳列だけでなく、人の流れ、真紀の所作、そして看板の配置を冷徹に観察していた。
「盛況だな。健太から聞いていた通りだ」
男は短くそう言うと、真紀に視線を合わせた。真紀は一瞬身構えたが、すぐに直感した。
「一平さん……ですか?」
「ああ。邪魔するつもりはない。ただ、約束通り様子を見に来ただけだ」
一平は、残っていたフレンチ弁当を一つ購入し、その場で蓋を開けた。一口、テリーヌを口に運ぶ。表情は崩さないが、その目がわずかに細められた。
「なるほど。屋台のレベルじゃない。浩二さんの腕は本物だ。だが、もったいないな」
一平は弁当の蓋を閉じると、鋭い視線を真紀に向けた。
「真紀さん。今日、この弁当を食べた人間は満足して帰るだろう。だが、それだけだ。彼らが家に帰り、明日になった時、この店のことを覚えている保証はどこにもない」
真紀は言葉に詰まった。美味しいものを提供すれば、客は戻ってくる。そう信じていた。
「祭りの熱狂は一過性のものだ。だが、事業は続く。ここで重要なのは、今日のこの『熱』を、どうやって冷めない『資産』として残すかだ」
一平は、テントの隅に貼られたInstagramのQRコードを指さした。
「あのQRコード。ただ貼ってあるだけでは誰も読み込まない。客は弁当を食うのに忙しいからな。もっと貪欲になる必要がある。例えば、『その場でフォロー画面を見せれば、冷たいお茶を一本サービス』。たったそれだけで、フォロワーというリストが手に入る」
一平の言葉は、淡々としていながらも重みがあった。
「Web集客というのは、パソコンの前だけで完結する遊びじゃない。今日のような泥臭い現場こそが、最強のコンテンツになる。Webの世界は虚構になりがちだが、ここにはリアルな汗と笑顔がある」
彼は、弁当を美味しそうに頬張る親子連れを顎でしゃくった。
「あの笑顔。浩二さんが真剣に鍋を振る背中。そして『完売』の札。それを写真や動画に撮っているか? それらは、あとでホームページやSNSに載せた時、まだ見ぬ客に『この店は信頼できる』と思わせるための、決定的な証拠になる」
真紀はハッとした。目の前の調理と販売に必死で、この光景を記録するという発想が欠落していたのだ。
「ホームページは、店の魅力を受け止める『受け皿』だ。だが、そこへ客を流し込む『入り口』は検索エンジンだけじゃない。この祭りも立派な入り口だ。ここで出会った人間を、どうやってWebという網の中に絡め取るか。その導線を太くすることが、より専門的にはマーケティングだ」
一平は、懐からスマートフォンを取り出し、並んでいる行列の写真を一枚撮った。
「まずは記録だ。そして、今夜の投稿でその熱量を伝える。浩二さんのフレンチの腕も、この祭りの熱気も、Web上で可視化されなければ、存在しないのと同じだ」
祭りの太鼓の音が響く中、真紀は急いでスマートフォンを手に取った。厨房で汗を拭う浩二の背中、そして容器を返しに来た客の満足げな表情。それらはすべて、まごころ弁当が生き残るための武器なのだと、真紀は強く認識した。
一平は、無言で頷くと、人混みの中へと消えていった。後に残されたのは、明確な課題と、それを乗り越えようとする真紀の強固な意志だけだった。