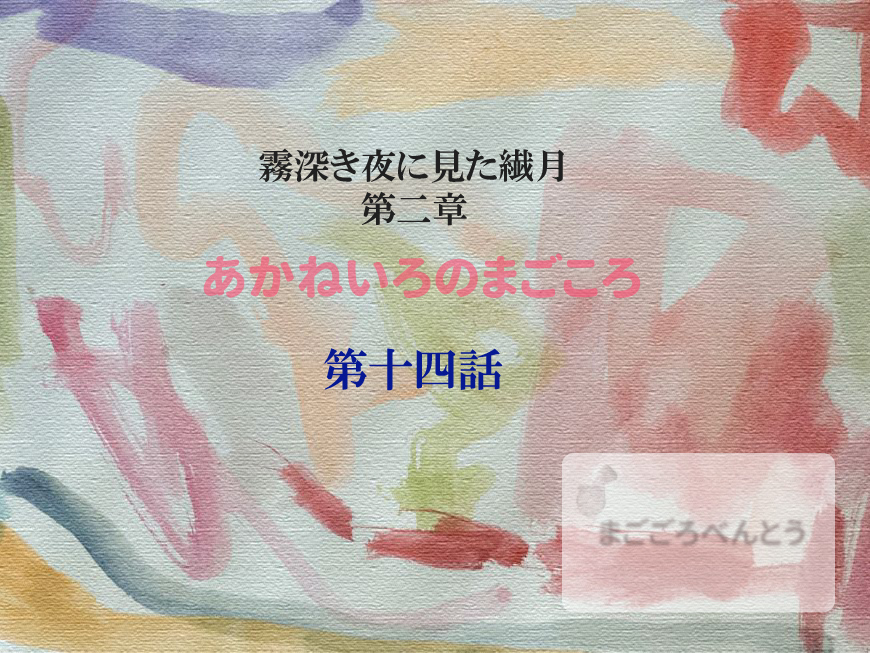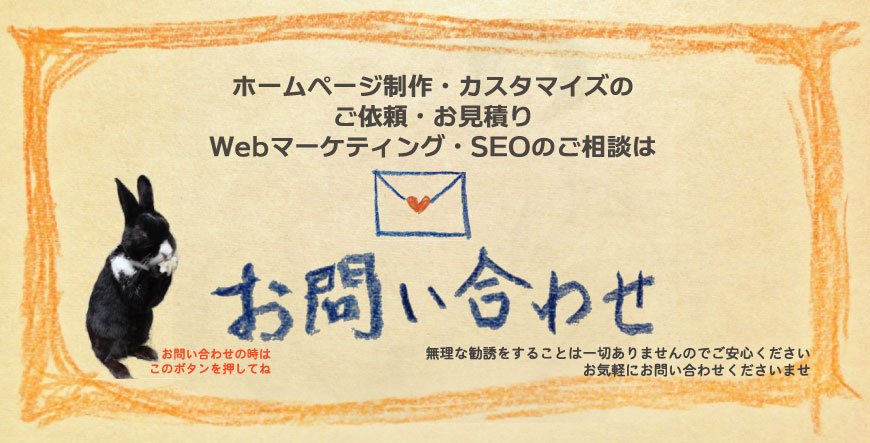真紀との話し合い、そしてあかねの涙を見た日から、浩二は変わった。これまでは厨房に引きこもり、調理以外の全てを真紀に任せきりだった自分を深く反省した。妻一人に重い荷物を背負わせている場合ではない。経営者としての自覚を持たなければ。
そんな折、顔見知りの酒屋の店主から、地元の経営者の会合に誘われた。「顔を広めるいい機会だぞ」という言葉に背中を押され、浩二は参加を決意した。
会合当日。浩二は、普段は作業着ばかりで着慣れないスーツに身を包み、ぎこちない手つきでネクタイを締めた。急ごしらえで作った名刺をポケットに忍ばせ、会場へと向かう。場には、いかにもやり手の経営者然とした人々がひしめき合い、慣れない立ち居振る舞いに浩二はひどく落ち着かなかった。
名刺交換の列に並び、おずおずと差し出した名刺を受け取ったある参加者が、浩二の顔をじっと見た。
「まごころ弁当さんですか。いつもお世話になってます。しかし、確か前は飲食店をされてましたよね?」
その問いに、浩二は少し緊張しながら答えた。
「はい。でも今はもう、お弁当がメインで」
しかし、相手の目は、その言葉の裏にある浩二の職人気質を見抜いたようだった。
「でも、ずっと料理の世界一本で?」
「ええ。昔はフレンチで十年以上修行したりもしていたんですが……」
浩二は、自身の経歴を語るにも、ひどく謙遜し、不器用な言葉を選んだ。それでも、相手の目は浩二の言葉の端々から真剣な思いを感じ取ったようだった。
「へぇ、フレンチですか! それはすごい。じゃあ、もうフレンチは作らないんですか? なんか、あなたの本気のフレンチ、一回食べてみたいなあ」
その言葉は、浩二の心に深く響いた。まさか、こんな場所で自分の料理を「本気で食べてみたい」と言われるとは。
会合は深夜まで続き、慣れない付き合い、慣れない酒に、浩二はすっかりフラフラになった。久しぶりのアルコールは、彼の体を芯から温め、心地よい疲労感を与えた。
しかし、心はどこか晴れやかだった。三流だ、素人だと自虐していた自分の中にも、まだ「本気」を求め、期待してくれる人がいる。そして、その「本気」を実現するための道筋が、かすかではあるが見えてきた。浩二の顔には、新しい挑戦への決意と、わずかながら自信の光が宿り始めていた。