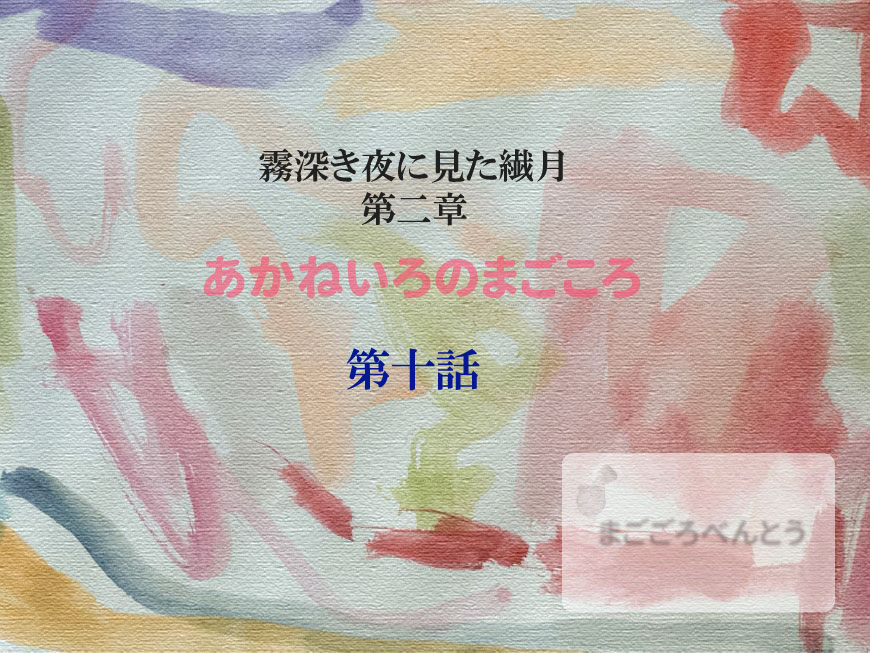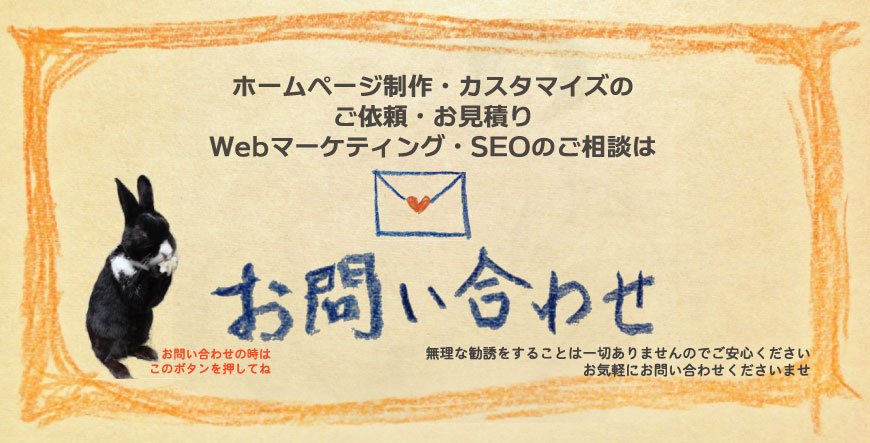真紀の提案に、浩二は俯いたまま、絞り出すように言った。
「俺の腕なんて、もう三流だよ。それに、商いのことなんて嫁さんに任せっきりの、五流にも満たない素人だ。そんなフレンチ弁当、誰も求めちゃいないさ。それが現実だよ、真紀」
その自虐的な言葉に、真紀の胸に熱いものがこみ上げてきた。
脳裏に、飲食店を営んでいた頃の光景が鮮明に蘇る。
あの頃は、毎日のように新しいメニューを考案し、お客さんの「美味しい!」の一言に心底喜んでいた浩二の姿があった。彼の作る料理は、いつも真紀の心を温かく満たしてくれた。
「なんで……なんでそんなこと言うのよ!」
真紀の目から、大粒の涙が溢れ落ちた。感情が抑えきれなくなり、声が震える。
「あの時、お客さんが『浩二さんの料理、最高だね!』って言ってくれた時、あなたはどんな気持ちで作ってたのよ! あなたの料理で、みんなが笑顔になってたじゃない!」
真紀の怒りに満ちた声が、店の奥まで響き渡る。その声に、隣の部屋で遊んでいた娘のあかねが、二人が喧嘩していると思ったのか、「ママ!パパ!」と泣きながら駆け寄ってきた。
あかねが真紀の足元にすがりつき、泣きじゃくる。真紀は、そんなあかねの小さな頭を撫でながら、震える声で言った。
「違うのよ、あかね。ママ、喧嘩してるんじゃないの。大丈夫だから……」
娘を抱きしめながらも、真紀の心は決して折れなかった。むしろ、浩二の諦めにも似た言葉と、過去の記憶が、彼女の中で確固たる決意へと変わっていく。
「私、絶対にこの店を再生させてみせるから。浩二さんの腕は、こんなところで終わらせない。もう一度、みんなを笑顔にする料理を、絶対に世の中に届けてみせる!」
真紀は、涙で滲む視界の先で、浩二の背中をまっすぐ見つめていた。その瞳には、どんな困難にも立ち向かう、強い光が宿っていた。