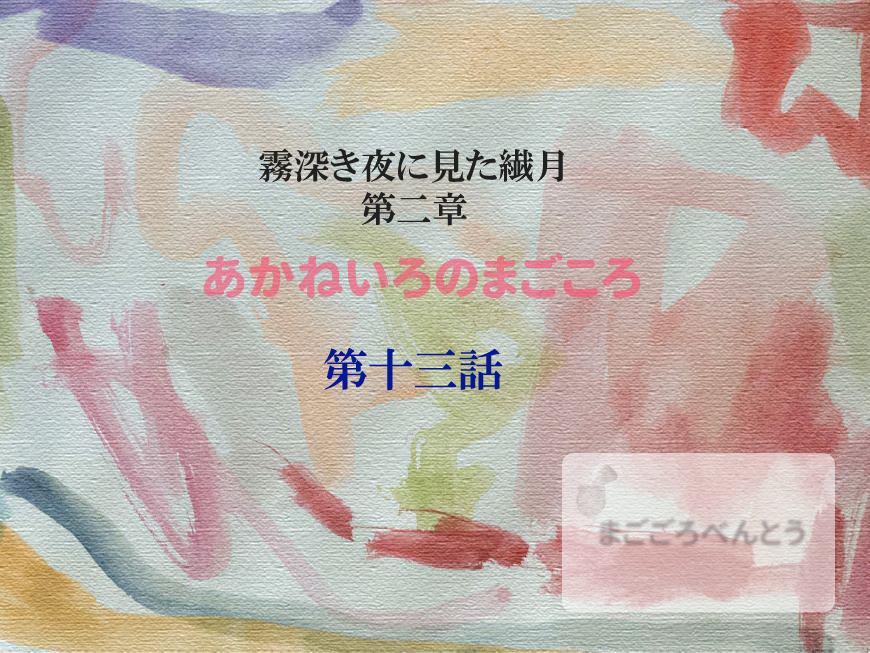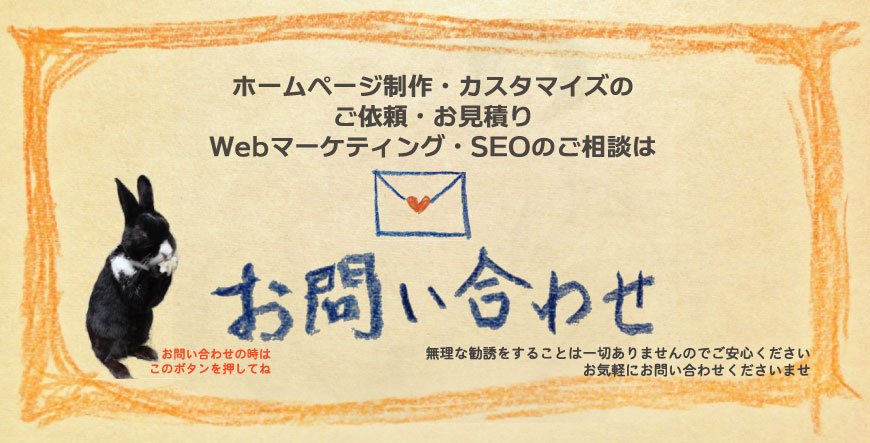大輝は一平との打ち合わせを終えると、スマートフォンの地図アプリで「まごころ弁当」の場所を確認した。
駅前の賑やかな通りから一本入った路地裏に、その小さな店はひっそりと佇んでいた。
年季の入った木の看板に「まごころ弁当」と手書きで書かれた文字が、どこか懐かしい雰囲気を醸し出している。
店に入ると、温かい出汁の香りがふわりと漂ってきた。ショーケースには彩り豊かな弁当が並び、奥の厨房からは小気味よい包丁の音が聞こえる。レジには、先ほどの真紀が立っていた。
「いらっしゃいませ!」
真紀の明るい声に、大輝はにこやかに応じた。
「店内でも食べられるんですね? じゃあ、この日替わり弁当、中でいただいてもいいですか?」
「はい、どうぞ! できたてですから」
大輝は日替わり弁当を受け取ると、店の奥にある小さなイートインスペースへと向かった。一口食べると、じんわりと出汁の旨みが広がり、おかず一つ一つが丁寧に作られているのがわかる。
「うん、これは美味い……」
大輝は思わず声に出した。手作りの温かさが、コンビニ弁当とは一線を画している。このクオリティなら、もっと知られてもいいはずだ。
彼は並んでいる弁当をゆっくりと眺めながら、頃合いを見計らって口を開いた。
「どれも美味しそうですね。いつもこの辺りで仕事してるんですけど、こんな素敵なお店があるなんて知りませんでした」
「ありがとうございます。うちは、この場所で細々とやってるもので」
真紀は少しはにかんだ。大輝は今日の目的を思い出し、自然な流れで尋ねた。
「あの、これだけ美味しいお弁当なら、イベントとかで特別なお弁当を出したり、『ポップアップストア』とかやったりはしないんですか? ほら、あの空きスペースとかを借りて期間限定でお店を出すようなやつです」
真紀は、大輝の言葉に目を見開いた。
「ポップアップストア、ですか? あのお祭りとか道の駅とか大型ショッピングモールとかでたまに見かけるような……?」
彼女は一瞬、戸惑いの表情を見せたが、すぐに笑顔で続けた。
「実は、そういうことも考えたりはするんですけど、なかなかそこまで手が回らなくて……。でも、そう言っていただけると嬉しいです。私たちも、何か新しいことに挑戦したいとは常々思っていて」
真紀の言葉に、大輝は内心でほくそ笑んだ。一平の読み通りだ。彼女は、新しい可能性を模索している。
「ですよね。やっぱり、特別なものって、お客さんも喜ぶと思いますよ。もしやるとしたら、SNSとかで告知すれば、きっと話題になりますよ」
イートインにあったInstagramのQRを一瞥して大輝は続けた。
「あ、インスタやられてるんですね。僕もSNSで動画作ったりしてるんですけど、最近はそういう期間限定のものって、すごく拡散されるんです」
大輝は、自分の専門分野に絡めて、さりげなく提案を重ねた。真紀の目が、期待に満ちた光を帯びていくのが分かった。
「そうなんですか! なるほど……。貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます!」
真紀は、感謝の言葉を述べながら、にこやかに他の作業に勤しんでいた。
大輝はにこやかに礼を言い、店を後にした。一平からの依頼は、完璧に果たせた。この種が、真紀の心の中でどう育っていくか、大輝は密かに期待を膨らませていた。