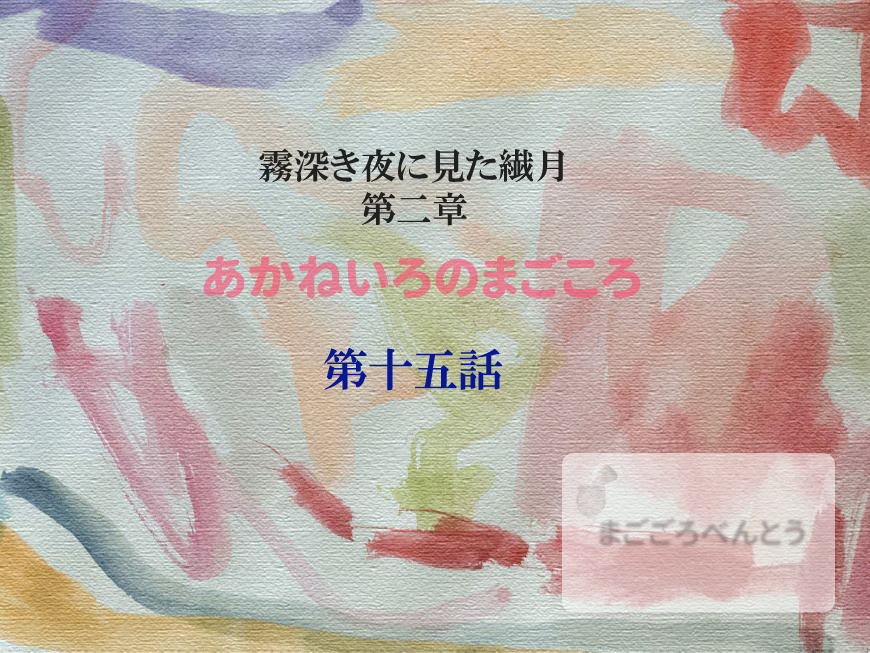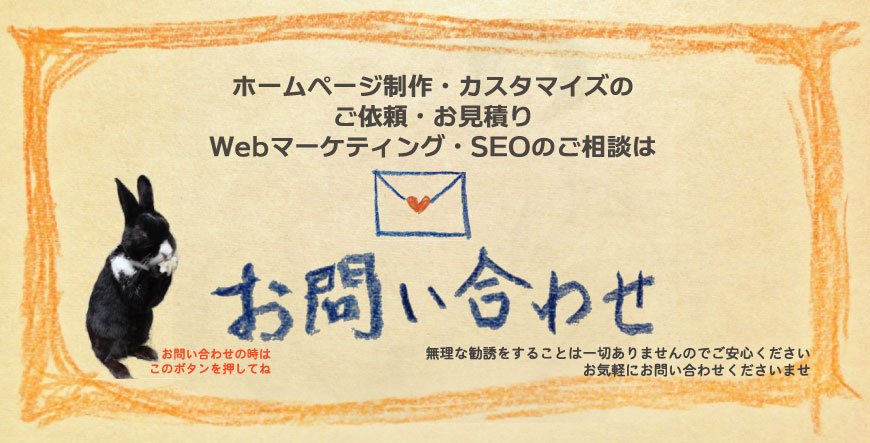浩二は、昨夜の会合から帰ってきて以来、どこか雰囲気が変わっていた。疲労の色は隠せないものの、その顔には諦めではなく、うっすらと希望の光が宿っている。真紀は、そんな浩二の変化に気づき、静かに見守っていた。
翌朝、真紀が仕込みの準備をしていると、浩二がいつになく口を開いた。
「おい、真紀。あのフレンチ弁当の話……」
真紀は、期待と不安の入り混じった目で浩二を見た。
「もし、お前が本気でやると言うなら、俺は作る。フレンチだけじゃなくて、お前が『これだ』と思うものがあるなら、とりあえずやってみようと思う」
具体的な計画を語るわけではない。相変わらず不器用な言葉だったが、その中に確かな前向きな姿勢が感じられた。浩二が自ら、厨房の外のことに言及するのは稀なことだ。
浩二の言葉に、真紀の胸に熱いものがこみ上げた。あの怒鳴り合いの夜から、浩二の中で何かが変わったのだ。彼が自分の仕事に、そして店の未来に、再び目を向け始めたことに、真紀は深く感動した。
「浩二さん……ありがとう!」
真紀は、感情を抑えきれずにそう言った。浩二の前向きな言葉は、真紀の心に大きな勇気を与えた。彼女自身も、健太や大輝からのヒントを受けて、頭の中に様々なアイデアが浮かんでいたのだ。
「私ね、健太さんと話して、色々考えてみたの。期間限定のメニューをどうするかとか、今のお弁当のラインナップを少し調整してみることもできるんじゃないかって。それに、どうやってお客さんに知ってもらうか、具体的な集客方法も、自分なりに考えてみたのよ」
真紀は、話しているうちに声に熱がこもった。
「友達にも、うちの店のことや今回の件を少し話して、何か良い意見がないか聞いてみたの。それで、もう少し自分の考えがまとまったら、もう一度健太さんに相談してみようと思う。今度は、もっと具体的な案を持って」
真紀の瞳は、未来への希望に輝いていた。浩二の技術と、真紀の行動力。二人の歯車が、ようやく噛み合い始めた瞬間だった。