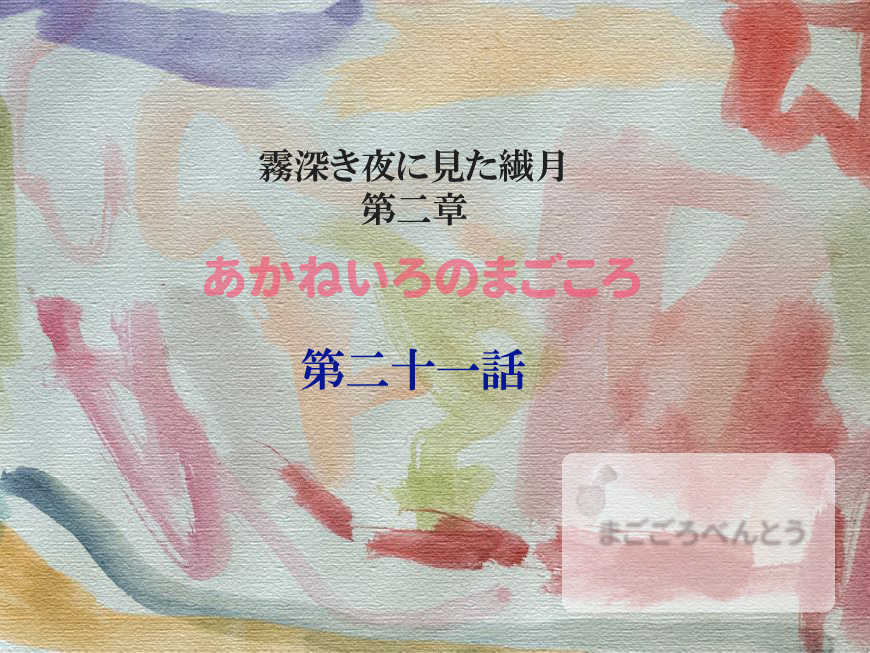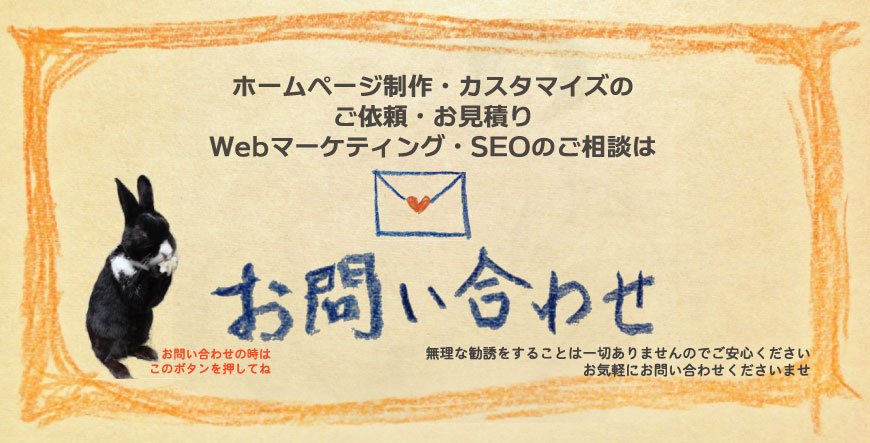真紀たちが祭りの熱狂を「資産」に変えようと地道な努力を始めた頃、都心のオフィスビルにあるユウキの会社では、張り詰めた空気が漂っていた。
「おい、どうなってるんだ! 先月と比べてリーチが激減してるじゃないか!」
ユウキの怒号が響く。
モニターに映し出されているのは、Instagramのインサイト画面だ。これまで順調だったはずの数字が、ある日を境に急降下していた。
担当の社員が青ざめた顔で報告する。
「社長、どうやらInstagramのアルゴリズムが大幅に変更されたようです。発見タブへの露出基準が厳しくなり、これまでのような『映え』だけの投稿や、ハッシュタグの乱用ではリーチが取れなくなっています」
ユウキは舌打ちをした。バズコンテンツ制作会社に高い金を払って依頼したにもかかわらず、プラットフォームのルール変更一つで、その努力が水泡に帰す。それがWeb集客の恐ろしさだ。
「で、どうするんだ。指をくわえて見ているつもりか?」
「いえ、業者から新しい提案が来ています。『Threads(スレッズ)』です」
社員はタブレットを操作し、新しいSNSの画面を見せた。
「今、Meta社はThreadsの普及に力を入れています。特に最近、アカウントの『トピック専門性』を評価するアルゴリズムが導入されました。専門的な情報を発信するアカウントが優遇される傾向にあります」
「専門性だと? うちは何でも屋じゃねえか」
「そこをAIでカバーします。ChatGPT等の生成AIを使って、業界のトレンドや豆知識を自動生成し、Threadsに流すんです。テキストベースなので画像生成ほどコストもかかりませんし、何より……」
社員は声を潜めた。
「AIツールを使えば、投稿作成にかかる作業時間は今の10分の1以下になります。それでいて、専門性を偽装……いえ、演出できるんです」
ユウキの目が怪しく光った。コスト削減とリーチ回復、一石二鳥の策に見えた。
「やれ。徹底的にだ。他社がもたついている間に、その『専門性』とやらでポジションを取れ」
指示を受けた業者の動きは早かった。翌日から、ユウキの会社のThreadsアカウントは変貌を遂げた。
『最新の住宅トレンド10選』
『知っておくべきリフォームの税制優遇』
『失敗しない業者選びのポイント』
AIが生成した、それらしく有益な情報が、1日に何十件も投稿され始めた。人間が書くには骨の折れる量だが、AIなら数秒だ。
効果はすぐに現れた。トピック専門性の評価が高まったのか、Threads経由でのインプレッションが急増し、それに引っ張られるようにInstagramの数字も持ち直し始めたのだ。
「ははっ、ちょろいもんだな。結局は数だよ、数」
ユウキは満足げに笑った。作業時間は激減し、数字は回復。まさに「効率化」の極みだと思っていた。ユウキはさらにアクセルを踏んだ。「投稿数を倍にしろ。AIをフル稼働させて、あらゆるキーワードを網羅するんだ」
しかし、その「効率化」は、プラットフォーム側から見れば「ノイズ」でしかなかった。
異変が起きたのは、それからわずか数日後のことだった。
「しゃ、社長!! 大変です!!」
血相を変えた社員が、ユウキの執務室に飛び込んできた。
「なんだ騒々しい。今度はなんだ」
「アカウントが……Threadsのアカウントが、停止されました!」
「は?」
ユウキは慌てて自分のスマホを取り出し、自社のアカウントを確認しようとした。しかし、画面に表示されたのは無機質なメッセージだけだった。
『このアカウントは、コミュニティ規定に違反したため停止されました』
「な、なんだこれは!? 何かの間違いだろう!?」
「いえ、業者に確認しましたが、同様の手法で運用していたアカウントが、軒並み一斉にBANされています。どうやらMeta社が、AIによる過剰な自動投稿や、エンゲージメントの低い連投を行う『スパム的企業アカウント』の大規模な締め出しを始めたようで……」
「締め出し……だと……?」
ユウキは言葉を失った。作業時間を1/10にし、効率だけを追い求めた結果、積み上げてきたフォロワーも、過去の投稿も、すべてが一瞬にして消え去ったのだ。
画面には「異議申し立て」のボタンがあるが、復旧の望みが薄いことは、社員の絶望的な表情を見れば明らかだった。
「Instagramの方は……?」
「今のところは無事ですが、Threadsと連携しているため、いつ影響が出るか……それに、今回の件でメタ社のブラックリストに入った可能性が高く、今後Instagramでも『シャドウバン』のような状態になり、露出が極端に減らされる恐れがあります」
ユウキは力なく椅子に沈み込んだ。効率化の名の元に、中身のない情報を垂れ流し続けた代償。それは、これまで積み上げてきたWeb上の信用という地盤そのものが、足元から崩れ落ちる音だった。
AIという魔法の杖で築き上げた城は、プラットフォームの「クリーン化」という波にあっけなく飲み込まれてしまったのだ。