久しぶりにペルソナとWebマーケティングの関係について触れようと思います。前回の「Webマーケティングにおけるペルソナとモデル」では、Webマーケティングの分野での「ペルソナ」という言葉はもう使わないと宣言しました(今回も、本質的なペルソナの意味を変えるような表現はしませんが…)。
しかしながら、先日、スマートフォン世代とされる若い世代の方々とお話する機会があったので、気持ちが再燃し、改めてユング博士への敬意として第二弾を書くことにしました。ペルソナとWebマーケティングの関係について、改めて書いていこうと思います。
今回も、Web雑談として、一平タイムズに記載します。ペルソナマーケティングというコトバや、ペルソナの分析と設定についてお伝えしていきましょう。
ペルソナマーケティング

大前提として、ペルソナマーケティングと「ペルソナ」の意味を考えてみたいと思います。
Webマーケティングの分野では、「モデルユーザー」と言えばいいのに、何故か「ペルソナ」という言葉を用いるようです。
ペルソナの意味については前回の「Webマーケティングにおけるペルソナ」でお伝えしましたが、カール・グスタフ・ユング博士が、分析心理学などの用語として提唱した「外面的人格」のことを指します。マーケティング分野では、仮定の顧客層をペルソナと呼ぶようですが、元々ペルソナとは、本人が持っている本来の人格とは別に、社会の中でどう振る舞うかという外面的な人格を意味します。
Webマーケティングにおいては「ペルソナを分析して設定して、マーケティングに活かす」、とりわけ、「ペルソナを分析して設定して、Webマーケティング活動に活かす」ということを指すようですが、一般的解説は、ペルソナではなくモデルユーザーのことを指していると考えることができます。
ペルソナの分析と設定
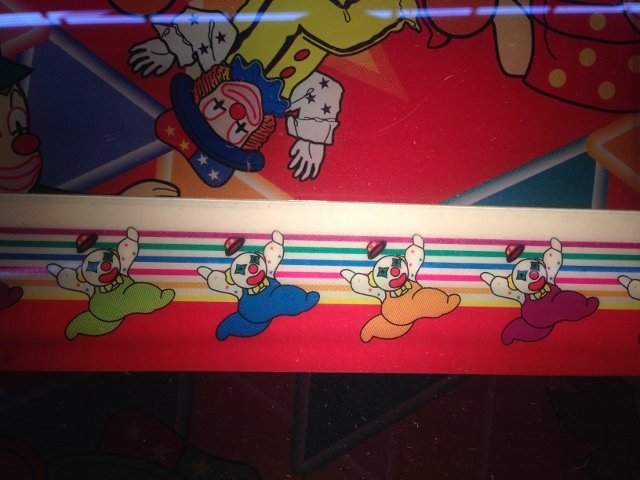
ここで考えてみると、マーケティングに関わる「ペルソナの分析と設定」ということが議題に上がった場合、「外面的人格の分析と設定」という意味で考えなければなりません。
本人の本質的な人格、趣味・嗜好、年齢、性別などは、「外面的人格」ではありません。そうした性格や趣味、ライフスタイルは本人の本来の人格であり、年齢や性別は客観的事実です。
「外面的人格」としてのペルソナ分析
そう考えると、ペルソナの本来の意味である、「外面的人格」を分析して設定する場合は、職業や立場に応じた、本質的な人格としてではなく、社会での役割としての人格を考える必要があります(そこまで考えているのかはわかりませんが)。
そういう意味では、企業でWeb担当者になった方が、上司の命令を受けて、Webマーケティング会社などをリストアップして、依頼先を探す場合を想定することは、「ペルソナマーケティング」として正しいかもしれません。
ただ、一般的なWebマーケティングにおける「ペルソナ」とは性格や趣味など、仮定のモデルの設定のことを指しているようです。それ自体はWebマーケティングの戦略設計には有効です。ただ、それはペルソナではありません。
性格・趣味

そこでペルソナマーケティングにおいて、性格や趣味を想定することは、本当に「ペルソナ」に関連しているのでしょうか?
性格や趣味は、本人の本質的な人格であり、仮面として、つまりペルソナとしての側面ではありません。
Webマーケティングにおいて、仮定の顧客層を設定し、その人物の性格や趣味に合わせて、反響がありそうなコンテンツを用意していくという事自体は良いのですが、任意に設定した架空の人物の正確や趣味、ライフスタイル、ある場面での行動のあり方などの想定は、ペルソナの設定ではなく、単なるモデルの設定です。
外面的人格としての性格、すなわち本人の普段の本質的な性格ではなく「ある会社の従業員である」という社会的な役割の中での立ち振舞い、選択、行動のあり方を想定するのであれば、ペルソナの設定になります。
年齢・性別

では、年齢や性別は、ペルソナに該当するのでしょうか?
年齢や性別は、本人の事実的な属性であり、外面的な人格ではありません。通常の考え方では、これらの属性は「ペルソナ」とされていますが、他人との関係の中で作り上げた「外面的人格」ではないため、ペルソナとは言えません。
年齢や性別といったカテゴライズは、架空の人物の設定としては良いですが、外面的人格という定義からは逸れたものになるため、ペルソナの設定と呼ぶには定義上論理がズレているとしか考えられません。
役職・立場
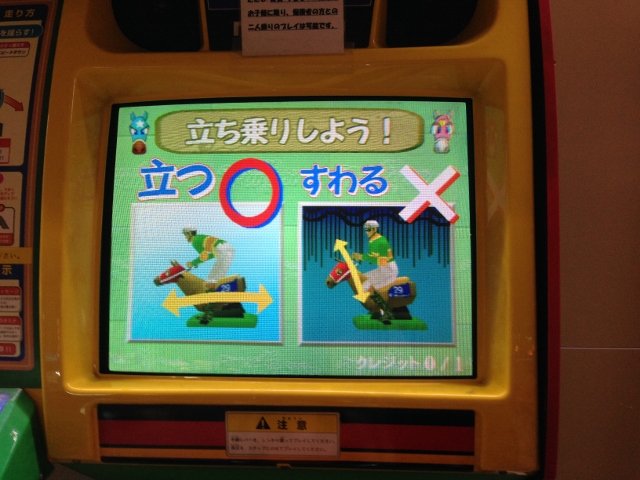
では、その人の役職や立場はペルソナと関連しているのでしょうか?
先の例で言うWeb担当者の方は、本人の性格や趣味を全面に押し出して考えることができるでしょうか?
内発的動機によって、自ら業者探しを行った場合は、取扱が異なりますが、上司の命令を受けて、一人の従業員として自らが属する企業や部署、上司の意向などを配慮して、業者探しをするはずです。
この場合は、意志決定において、本人の性格や趣味、年齢や性別よりも、従業員としての立場が優先されると考えることができます。
本人の好きな音楽や本・映画、世代として好きなテレビ番組や芸能人などを想定しても、役職としての立場が最優先されるため、一般的な「ペルソナの設定」とされているものは有効的ではありません。
こうしたところに配慮する、つまり、ユーザーの本人の趣味ではなく、外面的人格を形成している役職や立場を想定して、コンテンツを作ったり、マーケティングに活かすことが「ペルソナマーケティング」というならば、それほど間違いでもありません。
モデルユーザーとの混同を避けよう

ペルソナという言葉はなんとなくかっこいい言葉です。
だからといって、本質的な意味である「外面的人格」という意味を通り越して、モデルユーザーのことをペルソナと表現することは間違っています。
ユング博士の代わりに主張しますが、マーケティング分野における「ペルソナ」の用法はおかしいと思います。
性格や趣味、年齢、性別、その他ライフスタイルの想定は、「モデルユーザー」ではないでしょうか?
あくまで外面的な振る舞いによる影響、つまり、本人の自由意志が完全に発揮されず、社会的な立場や役割に応じて、意志決定に影響が出ることを想定することであれば、「ペルソナ」という言葉を用いてみてはいかがでしょうか?
「ペルソナとWebマーケティング」第二弾執筆の理由
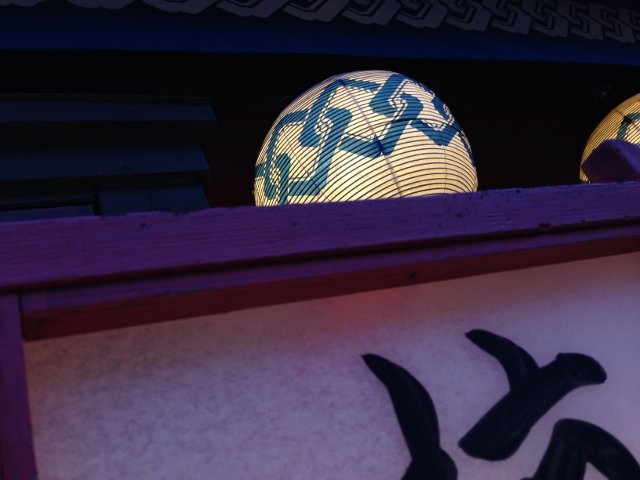
前回の一回きりで終わるつもりだったのですが、最近若い方とお話をしていて、分からない用語があるとスマートフォンですぐに検索するという流れを思い出しました。
そうして、仮に「Webマーケティング ペルソナ」とか「ペルソナマーケティング」と検索した場合に、ペルソナの意味をわからずに他のサイトのコンテンツページを転載しただけで「Webマーケティング ペルソナ」としてのコンテンツでアクセスを稼ごうとするようなページに検索結果が汚染されていた場合、ユング博士の功績が埋もれてしまうことに危惧を感じました。
また、それらのクエリの組み合わせを知らなくても、サジェストで自然に出てしまいます。
あくまで、それらの記事に対する警鈴として、検索順位のある程度のところに、こんな記事を忍ばせておきたいと考えました。もしかしたら第三弾もあるかもしれません。
第一弾 「Webマーケティングにおけるペルソナとモデル」
心理学とマーケティングにおける「ペルソナ」の意味の乖離
心理学者のカール・グスタフ・ユングが提唱した「ペルソナ(Persona)」と、マーケティングで使われる「ペルソナ」は、意味合いが大きく乖離しています。
1. ユング心理学における「ペルソナ」:外的人格
ユングの分析心理学において「ペルソナ」は、「外的世界(社会)に適応するために個人が作り上げる、仮面のような外的人格」を意味します。
語源: ラテン語で「仮面」や「劇の登場人物」を意味する言葉に由来します。
本質: 個人の「自我(Ego)」が、社会の期待に応えるために身につける役割、外面です。これは、その人の真の自己(影や内面)とは異なります。
問題点: ユング心理学では、ペルソナと真の自己が過度に同一化すると、アイデンティティの危機を招くとして、バランスが重要とされます。
2. マーケティングにおける「ペルソナ」:理想的な顧客像
マーケティングにおける「ペルソナ」は、製品やサービスを開発・販売する上で、架空の理想的なターゲット顧客を詳細に定義したモデルを指します。
本質: 年齢、職業、収入、趣味、家族構成、購買動機や行動パターンなど、その人の属性や特性を総合的にまとめたものです。
目的: チーム全体で顧客像を共有し、顧客のニーズや思考に深く共感することで、より効果的な戦略(誰に、何を、どう伝えるか)を立てるためのツールです。
乖離が発生した二つの主な理由
ユングの「仮面」という深層心理学的な概念が、マーケティングで「顧客の特性」という実務的な概念に変容したのは、主に以下の二つの理由によります。
理由 A: 概念の「実用化」と「単純化」
マーケティングの世界は、学問的な厳密性よりも実務での効果と共有の容易さを重視します。
「仮面」の概念は非実用的: ユングの定義する「真の自己と外面の乖離」といった複雑な深層心理学の概念は、製品開発や広告文作成という実務には難解すぎます。
実用的な部分のみを抽出: マーケティングが本当に必要としたのは、「顧客の頭の中で何が起こっているか」を推測し、「役割」として定義する部分でした。ユングのペルソナが社会的な役割や外面を指すことから、「理想的な顧客という役割」を定義するツールとして、その名称だけが借用され、最も実用的な意味に単純化されました。
理由 B: 「ユーザー中心設計」の思想への適合
マーケティングペルソナは、1999年にアラン・クーパー(Alan Cooper)がソフトウェア開発(UX/ユーザーエクスペリエンス)の分野で提唱したことで広く定着しました。
原点の意図: クーパーがペルソナを提唱したのは、開発者が「自分が欲しいもの」を作るのではなく、「ユーザーが本当に必要としているもの」を作るため、ユーザーをあたかも実在の人物のように感じて共感するためです。
この文脈では、ユング的な「仮面と自己の乖離」よりも、「この人はどんな特性と動機でこの製品を使うか」という外的・内的な特性(=人物像)が重視されます。
したがって、マーケティングペルソナは、ユングの概念をそのまま引き継いだのではなく、「ユーザーに深く共感し、その役割を演じることで製品を改善する」というUX/デザイン思考の文脈で、その「役割を定義する」という機能だけを借用し、意味を大きく変えてしまったと言えます。
アラン・クーパーが「ペルソナ」という言葉を選んだ理由については、彼がユングの複雑な概念を完全に無視したわけではなく、ユングが用いた言葉の「役割」と「外面」という本質的な機能を、自身のソフトウェア設計の目的に適合させたためと考えられます。
クーパーが「ペルソナ」を選んだ理由の推測
アラン・クーパーは、自身の手法を「ペルソナ」と名付けた具体的な経緯について、以下のような理由から最も適切だと判断したと推測されます。
1. 「役割を演じる」という本質的な共通点
ユングの「ペルソナ」は、「社会的な役割を演じるための仮面(外面)」です。クーパーが提唱した設計手法の核は、開発者が架空のユーザーの「役割」になりきり、その視点を通してソフトウェアを評価することです。
- ユング: 社会の期待という観客の前で「役割」を演じる。
- クーパー: 開発者が顧客という「役割」を演じ、デザインを評価する。
「ある役割を演じるためのモデル」という意味で、他の「ターゲット顧客」「プロフィール」といった言葉よりも、「演じるための仮面(ペルソナ)」という言葉が、共感と視点切り替えの本質を最もよく表していると判断された可能性が高いです。
2. 「ステレオタイプではない」ことの強調
マーケティングの現場には、すでに「デモグラフィック(年齢や性別などの統計属性)」や「ターゲット」といった言葉が存在しました。これらの言葉は、往々にして抽象的な統計情報に留まり、人間的な感情や動機が欠落しがちでした。
クーパーのペルソナは、単なる属性ではなく、実在するかのような具体的で豊かな物語を持たせることが重要です。この「命を吹き込まれた、物語の登場人物」という意味合いを込めるのに、劇の登場人物(仮面)を意味する「ペルソナ」が、既存のマーケティング用語と差別化を図る上で効果的でした。
3. 用語の「簡潔さ」と「哲学的な深み」
ユングの概念は複雑ですが、「ペルソナ」という単語自体は簡潔で、「人間性」「心理」「役割」といった深みを感じさせます。
クーパーは、「理系が言語を軽視している」と批判されるかもしれませんが、むしろ彼はこの単語に内在する「人間的な側面」を重視し、技術開発者に「人間中心の設計」の哲学を伝えるために、あえて哲学的な用語を選んだとも解釈できます。
結果として、ユングが危惧したように、真の自己から離れた「外面(仮面)」だけが、実務的なツールとして抜き出され、広く定着した、というのが現状です。
用語が「希釈化」していった過程の推測
ユングの「ペルソナ(仮面)」が、クーパーによって「役割を演じるためのモデル」へと実用化された後、それがマーケティングの世界で「ターゲット顧客の属性リスト」のように単純化されていったのには、いくつかの要因が考えられます。
1. 伝言ゲームによる「意図の喪失」
クーパーの手法は、主にプロダクト開発やUX(ユーザー体験)デザインの分野から広まりました。これがマーケティングやセールスの部門に伝わる際、「顧客の深い動機や物語を理解して演じる」という最も重要な「演技」の側面が失われがちです。
- 最初の定義(クーパー): 顧客に深く共感し、その役割を演じることで設計を評価する。
- 伝播後の定義(マーケティング): 顧客の特性(デモグラフィック、サイコグラフィック)を明確にすることで、効率的な広告やコンテンツを作る。
結果として、ユングが危惧したように、ペルソナは「外的な属性(特性)」の羅列となり、その背後にある「心理的な仮面」や「演じる」という動詞的な側面が抜け落ちてしまったと推測されます。
2. ツールとしての「汎用性」の要求
マーケティングペルソナは、UXデザイナーだけでなく、コンテンツライター、広告運用者、セールス担当者など、非常に多様な職種で利用されます。
UXデザイナーは、ペルソナを基に「このユーザーはこのボタンをどう操作するか?」と深く演じます。
しかし、広告運用者はペルソナを基に「この属性の人に届く効率的なキーワードは何か?」というデータ駆動型の分析に利用します。
このように、ペルソナが共通言語として使われるようになると、それぞれの職種が最も必要とする「特性情報」だけが強調され、クーパーが意図した「共感のプロセス」自体は、必須ではなくなっていったのです。
3. 「理系/文系」の溝と実用主義
技術志向や実務志向が強い分野(特にデジタルマーケティングやエンジニアリング)では、「結果」を出すための効率が最優先されます。
言語や心理学が持つ複雑な背景や哲学的な深みは、時に「すぐに結果が出ない無駄」と見なされがちです。そのため、用語が持つ厳密さや哲学的な背景よりも、「このペルソナシートを使えば、誰でもすぐにターゲットを共有できる」という実用性だけが価値を持つことになり、簡潔な「特性」モデルへと収斂していきました。
用語の変容は、「厳密な思考」を「効率的なツール」へと落とし込む過程で、必然的に生じるトレードオフと言えるでしょう。
(初回投稿日 2016年11月15日)







