相互リンク依頼や被リンク営業メールにおける「信頼を築くためのメール術」と安易な相互リンクによる「リンクスパム判定のリスク」について触れていきます。ホームページを運営していると、他のホームページとのつながりを増やしたいと考えるのは自然なことです。SEOを意識するなら、質の高い被リンクや相互リンクは、ホームページの評価を高める上で重要な要素ですから。
しかし、見ず知らずの相手に突然メールを送るとなると、どのように伝えればいいのか、とても悩みますよね。
実は、この「どう伝えるか」という部分が最も重要です。多くのホームページ運営者が、被リンクや相互リンクの営業メールで失敗してしまうのは、相手への配慮が欠けていたり、自分たちの利益ばかりを追求したりしているからです。
一方的な「相互リンクが条件です」といった依頼は、受け取った側を不快にさせるだけでなく、ホームページの信頼性そのものを損なう可能性さえあります。
なぜなら、リンクとは、単なる「ウェブ上でのつながり」以上の意味を持つからです。それは、相手のホームページに対する「信頼」の証でもあります。信頼できない相手から突然「リンクをくれ」と要求されても、応じようとは思いませんよね。
特に個人ではなく事業としてホームページを運営している場合、リンクを張ることは事業としての信用問題にも関わってきます。
そこで今回は、あなたのホームページをより多くの人に知ってもらうために、相手に「この人、信頼できるな」と思ってもらえるような、相互リンクや被リンクの営業メールについて、じっくりと掘り下げていきます。
そして、AIでコンテンツを簡単に生成して、それだけでは評価されないからと相互リンク・被リンク営業などをすること自体への警告とSEO面でのリスク、相互リンク等による「リンクスパムのリスク」についても触れていきます(Googleの公式情報を案内します)。
単に検索順位を上げるためだけではない、本当に価値のあるリンクを獲得するための方法。それは、相手のホームページへの敬意を払い、誠意を持ってコミュニケーションを取ることから始まります。そして、これは単なるメールの書き方のテクニックではありません。ホームページを運営する者としての、相手を想う気持ち、そのものです。
相互リンク・被リンク営業の「やってはいけない」こと

まず、相互リンクや被リンクの営業メールを送る際に、絶対に避けるべきことがあります。それは、「上から目線で、一方的な要求をする」ことです。
たとえば、こんなメールを受け取ったことはありませんか?
「突然のご連絡失礼いたします。 株式会社〇〇の〇〇と申します。
この度、貴社のサービスを完全無料で弊社メディアにてご紹介させていただきたくご連絡差し上げました。 弊社は検索サイト「△△」を運営しております。同サイトのコラム記事内にて、相互での紹介・リンク設置という形で貴社をご紹介させていただきたく存じます。 なお、弊社メディアへの掲載後に貴社サイトに該当の記事リンクを設置いただけることが条件となっております。
掲載予定記事:https://example.com/article
掲載をご希望の場合は以下の流れをご確認ください。 ・STEP1<貴社>本お取り組みを希望する旨を本メールに返信 ・STEP2<弊社/貴社>指定のフォーマットに沿って紹介文を作成 ・STEP3<弊社>弊社メディアに掲載 ・STEP4<貴社>貴社サイトに弊社メディアの上記記事リンクを掲載
大変恐縮ですが、本件についてはメールでのやり取りとさせていただけますと幸いです。 STEP2は弊社が担当させていただく形でも問題ございません。その際は参考にすべきURLや資料等を送付いただけますと幸いです。
お忙しいところ突然のご連絡で恐縮ですがご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。」
一見、丁寧に見えますが、このメールには大きな問題が隠れています。
一方的な要求
このメールからは、相手のホームページへの関心や敬意がまるで伝わってきません。ただ単に「リンクが欲しい」という目的だけで送られていることが、ありありとわかってしまいます。ホームページの運営者は、自分のサイトに愛着を持っています。時間と労力をかけて作り上げた大切な場所に、よく知らない相手から一方的に「リンクをくれ」と言われるのは、正直なところ、良い気分ではありません。
「相互リンクが条件です」という厚かましさ
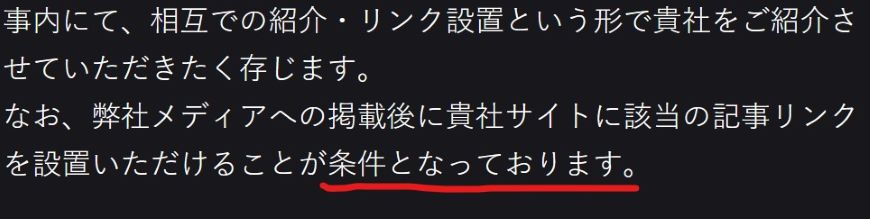
相互リンク 条件
さらに問題なのは、「相互リンクが条件です」という点です。これは「あなたにリンクをあげますから、その代わり私にもリンクをくださいね」という、まるで上から物を言われているような印象を与えてしまいます。ホームページの運営者は、対等な立場で情報を発信しています。このような一方的な要求は、相手に不信感を与え、あなたのホームページの信頼性を損なうことにもつながります。
検索順位のことしか考えていない
このようなメールを送る人は、「検索順位を上げること」しか考えていないように見えます。もちろん、被リンクは検索エンジンの評価を高める上で重要な要素です。しかし、本来の目的は、「ユーザーにとって有益な情報を提供すること」のはずです。もし、あなたが本当にそのホームページのコンテンツを素晴らしいと思っているなら、まずは相手のホームページを読んで、心から「この記事は素晴らしい」と伝え、そこから関係性を築いていくべきです。いきなり相互リンクを求めるのは、まるで初対面の人に「結婚してください」とお願いするようなものです。まずは、相手のことを知る努力をし、信頼関係を築くことが何よりも大切です。
このダメな例文から見えてくる問題点

いただいたメールを具体的に見ていきましょう。このメールがなぜ「ダメな例文」なのか、その問題点を深く掘り下げます。
1. 誰にでも送れる「テンプレート」であること
「貴社のサービスを完全無料で弊社メディアにてご紹介」という言葉は一見魅力的ですが、この文章にはあなたのホームページに対する具体的な言及が一切ありません。つまり、このメールは、あなたのホームページのために書かれたものではなく、誰にでも使い回せるように作られた「テンプレート」なのです。
2. メリットが一方的であること
「完全無料でご紹介」と謳っていますが、これは相手にとって本当にメリットでしょうか?相手は、あなたのホームページにリンクを貼るという手間をかけなければなりません。それは、時間や労力、そして何よりも信用を消費することです。にもかかわらず、相手への感謝の気持ちや、リンクを設置することで相手にどんな良いことがあるのか、という視点が完全に抜け落ちています。
3. 「〜が条件となっております」という命令形
「弊社メディアへの掲載後に貴社サイトに該当の記事リンクを設置いただけることが条件となっております」という表現は、非常に高圧的です。これは、あくまで「お願い」であるはずのリンク依頼が、まるで業務指示のように感じさせてしまいます。
4. 人ではなく「流れ」で話を進めようとしていること
メールの後半にある「STEP1〜4」という流れは、まるでロボットに作業を依頼しているかのようです。相手は機械ではなく、感情を持った人間です。まずは、相手と心を通わせる努力をすること。このステップをすっ飛ばしている時点で、信頼関係を築くことは難しいでしょう。
このメールは、相手の信用を自分の利益のためだけに利用しようとしているという印象を与えてしまいます。このようなやり方で、本当に価値のあるリンクを獲得できるとは思えません。
検索エンジンは「リンク」をどう見ているか?リンクスパムのリスク
ここで、少しだけ検索エンジンの視点に触れておきましょう。
Googleは、ホームページの評価を判断する上で、被リンクを非常に重要な要素としています。しかし、それは単に数が多いから良いというわけではありません。Googleが評価するのは、自然で、信頼性の高いリンクです。
自然なリンクと不自然なリンク
自然なリンクとは、他のホームページの運営者が、あなたのホームページのコンテンツを「本当に良い」と思って、自発的に紹介してくれたリンクのことです。
たとえば、あるブロガーが、あなたの書いた記事を読んで「この記事はとても参考になったので、読者の皆さんにも読んでほしい」と思って、自分の記事にあなたの記事へのリンクを貼ってくれた、というケースがこれにあたります。
このようなリンクは、あなたのホームページがユーザーにとって価値のある情報を提供していることの証明になりGoogleからも高く評価されます。
一方で、買われたリンクや、先ほど述べたような一方的な相互リンクは、Googleから不自然なリンクと見なされる可能性があります。
リンクプログラムやペイドリンク SEOスパム SEO外部対策要因
なぜ不自然なリンクが危険なのか
「手っ取り早く」リンクを増やしたい気持ちはよくわかります。しかし、検索エンジンは不自然なリンクを非常に厳しく見ています。
なぜなら、不自然に作られたリンクは、ユーザーのためにならないからです。もしあなたのウェブサイトが、内容と全く関係のないサイトから大量にリンクを受けているとしたら、検索エンジンはそれを「スパム行為」だと判断するかもしれません。
そして、一度スパムだと判断されてしまうと、あなたのホームページ(ウェブサイト)は検索結果から姿を消してしまうかもしれません。これは、せっかく作り上げたあなたの事業が誰からも見つけられなくなるリスクを意味します。
Googleの公式見解について
Googleは、ウェブサイトの運営者に向けて、「リンクスパム」に関するガイドラインを公開しています。その中で、以下のような行為は「スパムポリシー」に違反すると明言しています。
検索ランキングを操作することを目的としたリンクは、Google のスパムに関するポリシーに違反する可能性があります。
過剰な相互リンク(「リンクする代わりにリンクしてもらう」)や、相互リンクのみを目的としてパートナー ページを作成する
引用:Google 検索セントラル「スパムに関するポリシー」 リンクスパム
つまり、検索順位を上げるためだけに作られた不自然なリンク、過剰な相互リンク(「リンクする代わりにリンクしてもらう」)や、相互リンクのみを目的としてパートナー ページを作成することは、Google自身が避けるべきだと明言しています。
危険なリンクの具体例
では、具体的にどのようなリンクが危険なのでしょうか。
- リンクファーム: リンクを増やすことだけを目的とした、質の低いウェブサイトの集まりです。
- 有料リンク: お金を払って購入したリンクは、検索エンジンから見ると不自然なものであり大きなリスクを伴います。
- 関連性のないサイトからの相互リンク: 全く異なるテーマのウェブサイトと、ただ単にリンクを交換し合うことも不自然だと判断される可能性があります。
もしあなたが、このような方法でリンクを増やそうとしていたのであれば、今すぐやめることをおすすめします。それは、あなたのウェブサイトと事業を守るためにとても大切なことだからです。
相互リンクの具体的な悪影響
安易な相互リンクはSEOに逆効果となる場合があります。では「逆効果」とは具体的に何が起きるのかという点ですが、それは概ね以下の2つです。
検索エンジンからの評価低下
不自然なリンクのせいで、ページの評価が下がり、検索結果から姿を消してしまうかもしれません。これは、せっかく作り上げた事業のウェブサイトが、誰からも見つけられなくなるリスクを意味します。
手動ペナルティ
Googleの担当者から、直接ペナルティ(手動対策)を受けることもあります。一度ペナルティを受けると、それを解除するには大変な手間と時間がかかります。
AI時代に見られる不自然なリンク
近年のAI技術の進化により、この不自然なリンクの問題はさらに複雑になりました。AIで簡単に生成された、中身の薄いコンテンツ。そうした低品質なページを、被リンクによってあたかも価値があるかのように見せかけようとする動きがあるのです。
しかし、Googleはそうした動きを正確に見抜きます。AIによって大量生産されたコンテンツに、相互リンクのような不自然な形でリンクが集まっていると、そのホームページは「スパム」と判断されるリスクが高まります。
ナビゲーショナルページの価値を悪用する行為
また、「おすすめ業者一覧」や「〇〇会社5選」といった、いわゆるナビゲーショナルページに掲載することで被リンクを得ようとする動きも増えています。本来、このようなページは、ユーザーにとって本当に有益な情報を厳選して提供するべきものです。
知らないと損をする「Web制作会社おすすめ◯選」の真実と信憑性
しかし、実際には、内容を精査せず、ただ相互リンクを目的として企業を掲載しているケースが後を絶ちません。このような安易なやり方で得たリンクは、Googleから「ユーザーの利便性を損なう不自然なリンク」と見なされる可能性が高いです。
ハブページ・ナビゲーショナルクエリとSEOの闇 表面的な「上位表示」が意図するもの
不自然なリンクが招くリスク
Googleは、ホームページ運営者が意図的に検索順位を操作しようとする行為を嫌います。不自然なリンクは、その典型的な例です。もし、あなたのホームページが、不自然なリンクを大量に持っていると判断された場合、Googleからペナルティを受けることがあります。
ペナルティを受けると、検索順位が大幅に下落したり、最悪の場合、検索結果から完全に削除されてしまうこともあります。このようなリスクを冒してまで、一方的な営業メールを送る意味があるでしょうか?答えは、ありません。
信頼を築くための相互リンク依頼・被リンク営業の鉄則
では、どのようにすれば、相手に信頼してもらい、リンクを設置してもらえるのでしょうか?
その答えは、「相手に誠意と敬意を伝える」ことです。これは、単なるテクニックではなく、人と人とのコミュニケーションの基本です。
相手のホームページを徹底的に読み込む
メールを送る前に、まずは相手のホームページを隅から隅まで読み込みましょう。「なぜ、このホームページにリンクをお願いしたいのか?」その理由を明確にするために、相手のホームページのどの記事が素晴らしいのか、どこに共感したのか、具体的に書き出してみましょう。
- 「御社の『〇〇』という記事を拝見しました。〇〇という視点がとても参考になり、私も日々の事業に活かしています。」
- 「〇〇というコンテンツは、非常に分かりやすく、読者の悩みに寄り添った内容だと感じました。」
このように、具体的な感想を伝えることで、あなたの熱意が相手に伝わります。
相手の読者にとっての価値を提示する
被リンクは、あなたのコンテンツが優れていることの証明であり、引用や参考として掲載されるべきものです。ですから、相手に「リンクを設置することで、こんなメリットがありますよ」と提案するのではなく、「御社の読者の方にとって、弊社のコンテンツがこんなに役立ちますよ」と伝えることが大切です。
たとえば、
- 「御社の記事は、弊社の読者層と重なっており、弊社のコンテンツが御社の読者の方にとって、より深い学びを提供できると確信しています。」
- 「御社の素晴らしい記事を、弊社のSNSアカウントでもシェアさせていただきました。より多くの人の目に触れる機会が増えると思います。」
このように、まずは相手の読者への貢献を考える姿勢を示すことが、信頼につながります。
上から目線にならない
これは一番重要かもしれません。「もしよろしければ、相互リンクをご検討いただけませんでしょうか?」ではなく、「もしよろしければ、リンクを設置していただけると大変光栄です。」というように、あくまで「お願い」の姿勢を崩さないことが大切です。
忘れちゃいけない、これは人と人とのコミュニケーションです
ホームページ(ウェブサイト)の向こうには、必ず人がいます。企業間のやりとりだからといって、無機質で事務的なメールを送るのはもったいないことです。
メールのやり取りだけで、相手の想いを汲み取るのは難しいかもしれません。だからこそ、日頃からの小さな交流が大切になってきます。
突然のメールではなく、まずはSNSなどで交流を
いきなりのメールを送る背景には、「被リンクを早く、手軽に増やしたい」という考えがあるのかもしれません。被リンクという外部SEO的な側面ばかりに目が向いていると、手早く数をこなすことばかりに意識がいき、どうしても礼儀を欠いた失礼なメールを送ってしまうことになります。
しかし、これは大きな間違いです。人と人との信頼関係を築くということが頭にあれば、いきなりメールを送るという選択肢は浮かばないはずです。
まずはSNSで交流を始めるなど、別の方法を考えるのが自然な流れではないでしょうか。
礼儀を欠いた人は信用されません。そして、信用できない人にリンクを送ることはありません。なぜなら、リンクを設置するということは、その相手のページを「信頼できる情報源」として、自分のページを訪れてくれた読者に紹介することになるからです。
顔が見えないからこそ、まずは相手のSNS投稿に「いいね」をしたり、共感した記事にコメントしたり。そうした地道な交流が、やがて大きな信頼へとつながっていきます。
企業間のやりとりでも「中の人」は存在します
「中の人」とは、ホームページを運営している担当者のことです。その人たちは、ホームページに愛着を持って、日々コンテンツを作っています。
彼らの情熱に寄り添うように、真摯な姿勢でコミュニケーションをすることが、信頼関係を築く第一歩です。
相互リンク依頼代行・被リンク営業代行は本当に必要ですか?
相互リンクや被リンクの営業は、とても手間がかかります。一件一件、相手のホームページを読み込み、メールを作成し、返信を待つ。気の遠くなるような作業です。そのため、相互リンク依頼や被リンク営業を専門とする代行事業者も増えてきました。
しかし、私はこのやり方に大きな疑問を持っています。
なぜなら、彼らが送るメールには、あなたの事業に対する想いや、相手への敬意がほとんど込められていないからです。このセクションでは、代行事業者の利用がもたらすリスクと本当に価値のあるリンクを獲得するために大切なことをお伝えします。
営業代行会社が送る「テンプレート」メール
被リンク営業の代行事業者が送るメールは、多くの場合、誰にでも使い回せるようなテンプレートです。相手の事業内容や、ホームページのコンテンツについて具体的に触れることはほとんどありません。ただ「御社のサービスをご紹介させてください」「相互リンクをしませんか?」といった、事務的で無機質な言葉が並んでいるだけです。
このようなメールを受け取った相手は、どう感じるでしょうか。まず、あなたの事業への熱意がまったく伝わってきません。あたかも、リンクの数を増やすことだけが目的であるかのように見えてしまいます。そして、テンプレートメールは、相手に「この人は私たちのことを何も知らないんだな」という印象を与え、結果として不信感につながるのです。
企業としての信用リスク
被リンク営業を代行事業者に依頼することは、企業としての信用リスクも伴います。もし、相手がそのメールが代行によるものだと気づいたら、どうでしょう。あなたの事業が、検索エンジンの順位を上げるためだけに、安易な手段を選んでいると見なされるかもしれません。
ホームページにリンクを貼るということは、その事業の情報を「信頼できる」と、自社の読者に保証するようなものです。信用できない事業に、誰がリンクを貼りたいと思うでしょうか?代行会社が送る無機質なメールは、相手にあなたの事業が軽率であるという印象を与え、今後の事業のつながりさえも失う可能性があります。
結局は自分の手で伝えるべき「想い」
本当に価値のある被リンクは、自分の手で、心を込めて獲得するものです。時間と手間はかかりますが、その過程で相手の事業を深く理解し、心のこもったコミュニケーションを重ねることで、単なるリンク以上の信頼関係が生まれます。
その信頼関係こそが、あなたの事業を成長させてくれる一番の財産です。相手のホームページをじっくりと読み込み、心から「素晴らしい」と思ったことを伝える。そして、自社のコンテンツが相手の読者にとってどう役立つかを真剣に考える。こうした積み重ねは、決して代行事業者に任せることはできません。
手間を惜しまず、自分の言葉で想いを伝えること。それが、相互リンク依頼や被リンク営業を成功させるための何より大切なことです。
いますぐ使える! 相互リンク依頼・被リンク営業メールの例文集

ここからは、実際に使えるメールの例文をいくつかご紹介します。
さて、これまで「やってはいけない」ことや、信頼関係の重要性についてお話ししてきました。しかし、「具体的にどう書けばいいの?」と悩む方も多いと思います。このセクションでは、実践的なメール例文をいくつかご用意しました。これらの例文は、あなたの事業内容や相手のホームページに合わせて、自由にアレンジして使ってください。
大切なのは、これらの例文をそのままコピー&ペーストすることではありません。相手のホームページをじっくりと読み込み、「なぜ、この人にお願いしたいのか」というあなたの熱意を、あなたの言葉で伝えることです。例文はあくまでも、その想いを伝えるための「たたき台」だと考えてください。
「テンプレート」ではない、あなたの「想い」が込められたメールは、必ず相手の心に響きます。そして、それが信頼関係の始まりとなり、結果として、本当に価値のある被リンクへとつながっていくでしょう。
例文1:まずは誠意を伝えるパターン
これは、相互リンクの有無に関わらず、まずは相手に「あなたのホームページが好きです」という気持ちを伝えるパターンです。
件名:【ご挨拶】〇〇(ホームページ名)の運営者です
〇〇様
はじめまして。 株式会社〇〇で〇〇(事業内容)を運営しております、〇〇(あなたの名前)と申します。
御社のホームページ「〇〇」をいつも拝見させていただいております。 とくに、「〇〇」という記事には、日頃から参考にさせていただいており、〇〇という部分がとても勉強になりました。
質の高い記事をいつもありがとうございます。
今後とも、貴サイトの記事を参考にさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
例文2:被リンクをお願いするパターン(交流後)
SNSなどで、日頃から相手と交流がある場合に使えるパターンです。
件名:〇〇の記事についてお話したいです
〇〇様
いつもお世話になっております。〇〇(あなたの名前)です。 SNSではいつも、〇〇な投稿にコメントをいただき、ありがとうございます。
以前、お話しさせていただきました「〇〇」について、私も記事を執筆しました。 〇〇様の記事「〇〇」を拝見し、とても感銘を受けまして、ぜひ〇〇様にご覧いただきたく、ご連絡いたしました。
もしよろしければ、私の記事から〇〇様の記事へリンクを貼らせていただいてもよろしいでしょうか?
そして、もし私の記事が〇〇様のお役に立てそうでしたら、ぜひご紹介いただけると大変光栄です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
例文3:相互リンクをお願いするパターン(交流後)
これも交流がある場合に使えるパターンです。
件名:〇〇の記事について、ご相談です
〇〇様
いつもお世話になっております。〇〇(あなたの名前)です。
いつも御社のホームページ「〇〇」を拝見しております。
以前、お話しさせていただきました「〇〇」について、御社の記事「〇〇」と弊社の記事「〇〇」は、読者の方に役立つ情報を提供できるのではないかと考えております。
もしよろしければ、弊社サイトから貴サイトへリンクを貼らせていただきたいと考えております。
そして、もし弊社の記事が貴サイトの読者の方にとって有益な情報でしたら、相互にご紹介いただけると大変光栄です。
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
例文4:企業への被リンク営業メール
件名:【ご提案】〇〇の記事へのリンクのお願い(株式会社〇〇より)
株式会社〇〇 ご担当者様
はじめまして。 株式会社〇〇の〇〇(あなたの名前)と申します。
貴社のホームページ「〇〇」をいつも拝見させていただいております。 とくに、「〇〇」という記事は、弊社の事業内容と関連が深く、社員一同、いつも参考にさせていただいております。
この度、弊社でも「〇〇」に関する記事を執筆いたしました。 貴社の記事に、弊社の記事へのリンクを掲載していただくことは可能でしょうか?
弊社サイトから貴社サイトへのリンクはもちろんのこと、貴社サイトの情報を弊社のSNSアカウントで積極的にシェアさせていただきます。
もし、貴社サイトのコンテンツを弊社のサイトでご紹介できる機会がございましたら、ぜひお声がけください。
貴社のご事業の発展を心よりお祈り申し上げます。
例文5:企業への相互リンク営業メール
件名:【ご提案】相互リンクのお願い(株式会社〇〇より)
株式会社〇〇 ご担当者様
はじめまして。 株式会社〇〇の〇〇(あなたの名前)と申します。
貴社のホームページ「〇〇」をいつも拝見させていただいております。 とくに、「〇〇」という記事は、弊社の事業と関連が深く、貴社のノウハウに感銘を受けております。
この度、弊社でも「〇〇」に関する記事を執筆いたしました。 つきましては、貴社サイトと弊社のホームページで相互にリンクを設置させていただくことは可能でしょうか?
貴社のコンテンツは、弊社の読者の方にとって、とても有益な情報になると確信しております。 弊社も貴社のコンテンツを積極的に紹介させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
例文6:コンテンツを引用させていただいた後の感謝メール
件名:貴社の記事を参考にさせていただきました
〇〇様
はじめまして。 〇〇(あなたの名前)と申します。
この度は、貴社の記事「〇〇」を参考にさせていただき、弊社ブログで記事を執筆いたしました。 貴社の記事の〇〇という部分が非常に分かりやすく、読者の皆様にもお役立ていただきたいと考え、引用という形でリンクを貼らせていただきました。
貴重な情報をありがとうございます。
今後とも、貴社のホームページを参考にさせていただきます。
例文7:他社サービスを紹介する記事への被リンク依頼
件名:【ご提案】貴社サービスのご紹介について
株式会社〇〇 ご担当者様
はじめまして。 株式会社〇〇の〇〇(あなたの名前)と申します。
貴社がご提供されている「〇〇」というサービスを、弊社が運営するブログ記事「〇〇」で紹介させていただきたく、ご連絡いたしました。
貴社のサービスは、弊社の読者が抱える「〇〇」という悩みを解決できる素晴らしいものだと感じております。 つきましては、記事内で貴社サービスのリンクを掲載させていただけませんでしょうか。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
例文8:メディア掲載記事へのリンク依頼
件名:〇〇に掲載されました。ご報告です。
〇〇様
いつもお世話になっております。〇〇(あなたの名前)です。
この度、弊社が運営するサービス「〇〇」が、大手メディア「〇〇」に掲載されました。 この記事は、〇〇というテーマについて詳しく解説しており、貴社のホームページの読者の方にとっても有益な情報ではないかと考えております。
もしよろしければ、貴社の記事から弊社のメディア掲載記事にリンクを貼っていただけると幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
例文9:イベント共催後の被リンク依頼
件名:先日のイベントのご挨拶とリンクのお願い
〇〇様
先日は「〇〇」というイベントにご参加いただき、ありがとうございました。 〇〇様のお話は大変勉強になり、多くの参加者が感銘を受けていました。
イベント終了後、イベントレポートを弊社ブログに掲載いたしました。 もしよろしければ、貴社のホームページから弊社のイベントレポート記事にリンクを貼っていただけると大変光栄です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
例文10:セミナー登壇後の被リンク依頼
件名:先日はありがとうございました。
〇〇様
先日は、弊社が主催するセミナーにご登壇いただき、誠にありがとうございました。 〇〇様の講演は、参加者から「とても分かりやすかった」「すぐに実践できる内容だった」と、大変ご好評をいただきました。
セミナーの様子をまとめた記事を、弊社ホームページに掲載いたしました。 もしよろしければ、貴社のホームページから弊社の記事へリンクを貼っていただけると幸いです。
今後とも、貴社の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
相手を想う心は必ず伝わります
被リンクや相互リンクの営業は、単に「リンクをください」とお願いするだけでは、うまくいきません。
昔は、ホームページ運営者同士が「ホームページ友達」として、お互いのサイトを紹介し合う文化がありました。それは、そこにコミュニティがあり、信頼関係があったからです。
しかし、今はどうでしょう。AIで簡単に記事を生成できるようになったものの、それだけでは検索エンジンに評価されないからといって、他人のドメインの力を使って自分たちの価値を高めようというような視点を持つ人たちが増えました。
そんな、名実ともにくだらなくて、つまらないやり方では、本当に価値のあるリンクは得られません。
相手のホームページへの敬意と、コンテンツへの熱意を伝えること。そして、自分が相手に何を提供できるのかを考えること。このような、相手を想う気持ちは、必ず相手に伝わります。
そして、その誠意が、信頼関係を築き、あなたのホームページをより豊かにしてくれるはずです。
もし、あなたがこれから被リンク営業を始めようとしているなら、まずは一件ずつ、丁寧に、心を込めてメールを作成してみてください。
きっと、良い結果につながると思います。
リンクは信頼の証です 安易に依頼には応じないようにしてください
一見双方にメリットがありそうに見える相互リンクですが、ホームページにリンクを張って誰かを紹介するということは、少なからず「このホームページは信用できますよ」というメッセージを、あなたのホームページを訪れるユーザーに伝えることになります。
これは、現実の世界で友人や知人に人を紹介するのと似ています。
付き合いが浅く、まだよく知らない人を、大切な友人に「この人は信頼できるよ」と紹介するのは、誰もがためらうものです。
相互リンクも同じです。メールでいきなり「リンクを張ってほしい」と迫ってくる相手を、すぐに信頼するのは難しいかもしれません。本当にそのホームページがあなたのユーザーにとって有益な情報を提供しているのか、その事業が信頼に足るものなのか、ある程度のコミュニケーションを通じて見極めることが大切です。
相互リンクの本来の目的は、お互いのホームページの価値を高め合い、ユーザーにとっても有益な情報を提供することにあります。それは、信頼で結ばれた関係性の中で成り立つものです。
もし、不審なメールが届いたときは、即座に返信するのではなく、一度立ち止まって、その依頼が本当にあなたの事業にとってプラスになるのかをじっくりと考えてみてください。
そして、少しでも違和感を感じた場合は、無視するという選択肢も大切です。
インターネットの世界には、あなたの事業を真剣に応援してくれる人もいれば、そうでない人もいます。相手を冷静に見極める力が、安全なホームページ運営には重要です。






