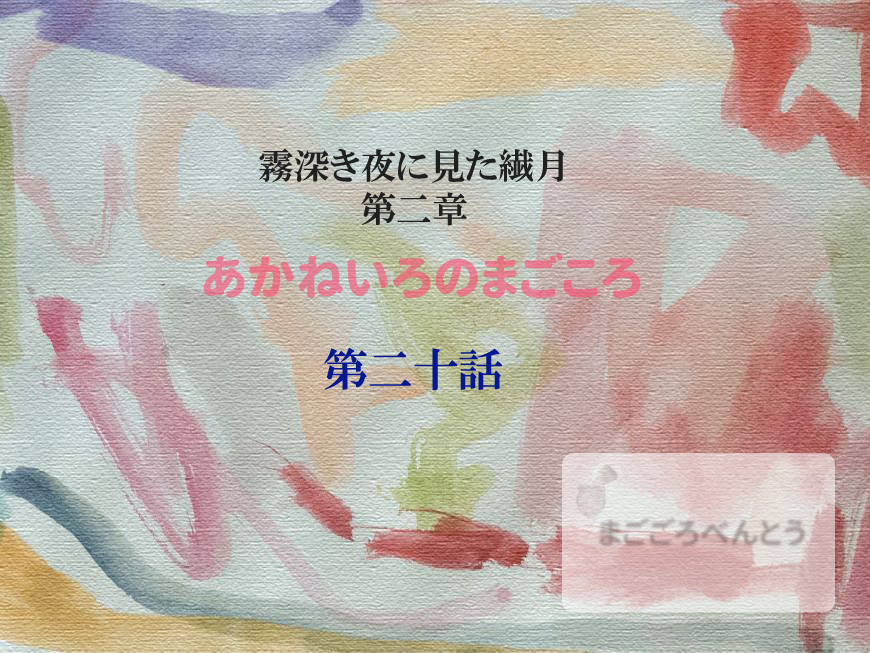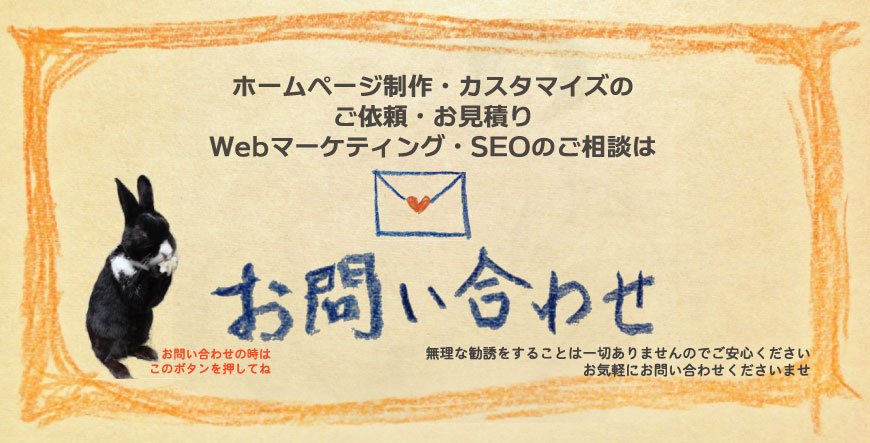一平が去った後も、祭りの熱気は衰えるどころか、さらにヒートアップしていた。だが、「まごころ弁当」のテント周辺で起きている現象は、明らかに異常だった。
「ねえ、ここだよね?」「まだあるかな?」
先ほどまでは、通りがかりの客が足を止める程度だったのが、急に若い女性やカップルを中心とした集団が、テントを目がけて一直線に向かってくるようになったのだ。あっという間にテントの前には長蛇の列ができ、最後尾が見えないほどになっていた。
「え、ちょっと……何これ?」
真紀は目を白黒させた。浩二も厨房の手を止め、呆然と外を見つめている。
「おい真紀、これ一体どうなってるんだ? さっきまでとは客層が全然違うぞ」
その時、列をかき分けるようにして、一人の男が笑顔で近づいてきた。大輝だ。彼の隣には、モデルのように洗練されたファッションに身を包んだ、若い女性が連れ添っている。一見するとカップルのようだが、二人の距離感はどこかビジネスライクでもあった。
「真紀さん、浩二さん! すごい行列ですね!」
大輝は悪びれもせず、いつもの調子で声をかけた。
「大輝さん! これ、一体何が……?」
真紀が問いかけると、大輝は隣の女性を掌で示した。
「紹介します。彼女はミナミ。実はフォロワー数十万人を抱えるインフルエンサーなんです。僕の仕事仲間でして」
ミナミと呼ばれた女性は、スマートフォンを片手に軽く会釈した。
「初めまして〜。お弁当、すごく楽しみにしてたんです」
大輝が種明かしをした。
「実は彼女、昨日の夜から『明日はこのお祭に行く』って投稿してて、今日の朝には『このお弁当屋さんが気になる!絶対食べる!』って、真紀さんの店のアカウントをタグ付けしてストーリーに上げてくれてたんですよ」
真紀は慌てて自分のスマホを取り出し、Instagramを確認した。通知欄が今まで見たことのない数で埋め尽くされている。ミナミの投稿を見たファンたちが、彼女と同じものを食べようと、あるいは彼女に会えるかもしれないと期待して、この場所に殺到していたのだ。これが、インフルエンサーマーケティングの威力……。真紀は背筋が寒くなるような、得体の知れないエネルギーを感じた。
しかし、現実は非情だった。
「すみません……! 只今をもちまして、本日分のお弁当は完売いたしました!」
浩二の声が響いた。準備していた数は、通常の予想をはるかに上回っていたが、この突発的な「バズ」の前にはあまりにも少なすぎた。
「えー、うそ!」「マジかよ、せっかく来たのに」
行列からは落胆のため息と、不満の声が漏れた。そして、当のミナミもまた、露骨に残念そうな表情を浮かべた。
「え〜、売り切れちゃったんですか? ショック……」
彼女はすぐにスマホを操作し、その場で写真を撮り始めた。「完売」の札と、自分のがっかりした顔。
数分後、彼女のSNSには新しい投稿がアップされていた。
『楽しみにしていたお弁当、目の前で売り切れちゃった😭 食べたかったなぁ……』
その投稿は瞬く間に拡散され、「かわいそう!」「そんなに人気なんだ」というコメントが次々と書き込まれていく。
真紀は、行列に並んでくれた人々の失望感を肌で感じ、胸が痛んだ。せっかく興味を持って来てくれたのに、手ぶらで帰らせてしまう。これはチャンスであると同時に、店への不満を生むリスクでもあった。
その時、一平の言葉が脳裏をよぎった。
『今日のこの熱を、どうやって冷めない資産として残すかだ』
ただ謝って終わらせてはいけない。この「買えなかった」という強烈な体験を、次回の期待に変えなければ。
真紀は、急いで残っていたチラシを掴むと、行列の方々へ駆け寄った。
「本当に申し訳ありません! 予想以上の反響で、ご用意できませんでした!」
真紀は一人一人に頭を下げながら、チラシを手渡していった。そして、必ずこの一言を添えた。
「次回の販売予定や、予約の情報は必ずSNSでお知らせします! ぜひチェックしてください!」
ただの完売詫びではない。「次は逃したくない」という心理に働きかける、次回の予告。チラシを受け取る人々の多くは、その場でスマホを取り出し、QRコードを読み込んでいく。
「またSNSでお知らせします」
その言葉は、祭りの喧騒の中で、真紀自身にも言い聞かせるような誓いの言葉となった。インフルエンサーという劇薬によってもたらされた瞬間的な爆発。しかし、その残り火を確かな炎に変えるのは、これからの自分たちの地道な努力なのだと、真紀は強く確信していた。