ホームページ集客の実践について、そして、少ないアクセスでも結果を出す方法についてお伝えしていきます。ここでいう「少ないアクセスでも結果を出す」ということは、ホームページからの問い合わせ獲得などが中心となります。
そうしたことから、今回の内容は、どちらかというと企業ホームページにおけるホームページ集客の実践についてであり、広告収入を狙ったアクセス数を追いかけるようなタイプのサイトには適していません。コーポレートサイトにおける集客が対象となります。
ホームページを既に所有しWebマーケティングを実施している方でも、これからホームページを作成する方でも、Webマーケティングの可能性に期待を持っている方も、その効果に疑念を持たれている方でも、ひとまずは、ホームページ集客の実践の全体像について概観していただければよいのではないかと思います。
WebマーケティングやWeb集客の情報を見ても「お勉強」になりがちです。
大切なのは実践と実際の効果であって知識を増やすことではありません。
先に効果の面のゴールやビジョンのようなものがあってこそ、知識、情報が活きてきます。
そこで今回は、ホームページ集客の実践について考えてみたいと思います。
リスティング広告の効果やそれらWeb広告とLP(ランディングページ)を組み合わせた集客方法は、緊急性の高いものに適していますが、一方で「緊急性が低く単価の高いもの」については、ホームページの内容が極めて重要になります。
(近年は「ここ」と決めた事業者のホームページを入念に見てから問い合わせをするという流れになりつつあります)
情報の「有用性」に囚われ、人の心を見失っていませんか?

現代のコンテンツ制作は、ともすればAI的な、文語ベースの思考に偏りすぎてしまうかもしれません。
検索エンジンで上位表示させること、多くのアクセスを集めることに重要なのは、情報の「有用性」や「網羅性」である、という考え方が浸透しているからです。
その結果、私たちは、人の感情を無視し、抽象的なものを嫌う、具体的な情報の羅列に終始しがちです。
もちろん、情報が役立つことは大切ですが、情報ばかりに着目し、その裏にある読者の気持ちを置き去りにしてしまうと、結局は誰の心も動かせない、乾いた文章になってしまいます。
読者の行動を「すべきこと」にする具体的なハウツーの問題点
私たちが提供するコンテンツが、ひたすら具体的なハウツーばかりで構成されている場合、読者の行動は「~しなさい」「~すべきである」という義務感、すなわち「have to」に縛られてしまいます。
たとえば、「集客のためには、この手順で必ず記事を書きなさい」「この通りにやれば、誰でも売上が上がる重要な方法です」といった具体的なノウハウは、一見親切に見えます。しかし、これらは読者の内発的な動機ではなく、外発的な圧力として作用するのです。
人の感情やモチベーションを無視した「have to」の行動は、決して長続きしません。
義務感で始めたことは、すぐに壁にぶつかり、読む側も実行する側も疲弊してしまいます。
結果として、コンテンツを読んだ相手の感情は動かず、行動も途中で止まってしまい、事業の成果には結びつかないでしょう。
感情を動かすコンテンツが、読者を「したいこと」へと誘う
私たちが目指すべきは、読者の行動を「したいこと」、すなわち「want to」に変えることです。
これこそが、共感や感情に訴えかけるコンテンツの役割です。
具体的なノウハウではなく、読者の抱える悩みや苦しみに寄り添い、「その状況下で起こるその気持ちは痛いほどよくわかりません。私も経験しました」という共感から入ることで、読者は「この人は自分のことを理解してくれている」と感じます。
この理解と共感が、読者の心を動かし、内発的な動機付けを生み出します。
抽象的な概念や、感情に訴えかける言葉は、情報の網羅性という観点ではAI的な思考に劣るかもしれません。
しかし、人の心に火を灯し、「やってみたい」「この人の考え方についていきたい」という重要な感情を生み出します。
少ないアクセスでも共感を意識すべき理由
「アクセス数が少ないから、まずはハウツーで集客を増やさなくては」と考えるかもしれません。
しかし、たとえアクセス数が少なくても、熱心に読んでくれる読者の心を深く動かすことの方が、事業にとってはるかに重要です。
共感を意識して作られたコンテンツは、質の高い読者、つまりあなたの事業のファンになり得る人々を惹きつけます。
アクセス数が多くても、感情が動かない一過性の訪問者を増やすよりも、少ないアクセスでも、深く共感し、自ら進んで行動を変えてくれる読者を増やすことが長期的な事業成長の土台になります。
あなたのホームページ(ウェブサイト)で発信する言葉が、誰かの感情に触れ、その人の内側から行動を変える「want to」を生み出す。
この「人への共感を意識したコンテンツ」こそが、アクセス数に左右されない、重要な成果を生み出す道だと考えます。
費用や労力をかけられないのであれば、やめたほうがいい

ホームページ集客は、ある程度の費用や労力が必要になります。
「広告枠があってその部分に自社の名前を掲載すれば良い」というような単純なものではありません。
土台となるホームページをどう作るか、何をどのように伝えるか、どうやってそのページを見てもらうか…
といったようにたくさんの要素があります。
テレビCMなどでは広告制作や放映に莫大な予算が投じられます。
しかしホームページとなると「無料ホームページもあるから」と、予算や労力について安見積もりをしがちです。もちろん無料ホームページを利用する形でも問題はありませんが、それ相応の労力をかける気がないと、何の結果も生まれません。
近年では所在地・営業時間情報などはGoogleマップ情報等で最低限の情報を掲載することができます。少し手間を掛けて何の結果も生まれないのであれば、ホームページの制作や運営はやらないほうがいいということになります。
ホームページ集客方法の論点

ホームページ集客の方法の基本的なポイントは、対象者に対してサービスやメッセージを用意することと、その対象者との接点を作ることです。
ホームページ集客の方法が語られる時、ほとんど対象者との接点、つまりアクセスについて語られます。
その理由は簡単で数値で確認できる、可視化しやすいという特徴があるからです。
ホームページを見た人にとって
「提供サービスの質、満足度、魅力はどれくらいか?」
「メッセージはどれくらい伝わっているか?」
ということは、数値化することが難しい面があります。
モデル化して大まかに数値化することはできますが、推測や主観、再現性のなさは残ります。
(アクセスは理系的、サイト内容は文系的であるということになります)
自己満足な「お勉強」で終わりがち

ある事業者は「ホームページ制作」というサービスを売るために、ある事業者はSEO(検索エンジン最適化)や分析ツールというサービスを売るために、という視点を念頭に置いて情報を配信しています。そうでない場合も、ブロガーが広告収入のために記事を掲載していることもよくあります。
それらの情報は、嘘や間違いが掲載されているわけではなく有益な情報もたくさんあります。
しかしたいていは「ある空間での正しさ」のみとなり、ホームページ集客の実践に対する有益性は限定的なものになりがちです。
SEOの情報としては正しいですが、200以上ある要素のいくつかについてのみ説明され、それがどの程度有効なのかというところは不明瞭である場合があります。
例として、これはある食材についての効能に似ています。ある食材に含まれるあるビタミンは確かに血流の改善に効果がありますが、だからといってその食材を取れば直ちに肩こりが改善するかといえば疑問点が残ります。少々論理が飛躍している面は否めません。
さらに投稿時はそれが最新で最も適切な施策だったとしても検索エルゴリズム変更によって本当に適切かどうかは今現在となってはわからないという場合もあります。
また、それが確かに正しい情報だったとしても、施策の労力や費用に対して、自社のマーケティングの上で費用対効果を期待できるものかどうかはさらに不明瞭です。
ホームページ集客方法のコンテンツの奥にある意図から内容とマーケティング寄与度の関係を考える
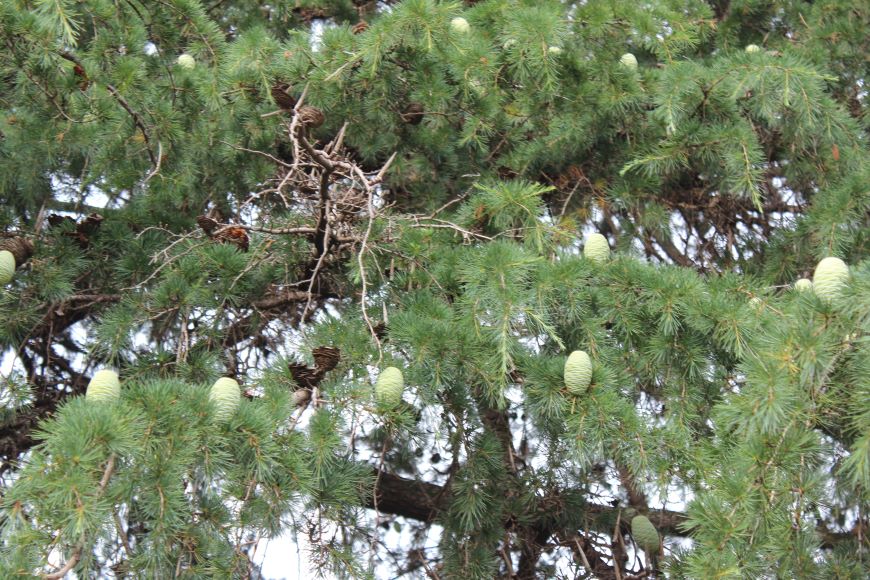
様々なコンテンツの奥にある意図から考えると、単にSEO(検索エンジン最適化)サービスならSEOサービス、アクセス解析やヒートマップなどの解析・分析ツールなら解析・分析ツールを販売したいがためのコンテンツが配信されやすくなります。
SEOサービスを例にして考えると、中心となる論点はアクセスとなります。
これは極端に考えるとホームページ集客の要素の片側、「接点づくり」側だけに特化した要素です。
しかし、企業やWeb担当者の方が本当に求めているものは「自社のサービスの販路となりうるか?」という点であり、その視点から考えると「アクセス」は目的の半分にしか寄与しません。
さらにそのアクセスの経路として他にWeb広告(リスティング広告やSNS広告)などもある中「SEO」だけに絞って考えるとさらに寄与度は半減します。
それにも増して特定のSEOサービスに特化した情報に絞られると「本当に企業のマーケティングに繋がるのか?」という疑念も生じます。
少ないアクセスでも結果を出す方法

さて、少ないアクセスでも結果を出す方法について触れていきます。これはホームページ集客であまり語られない数値化しにくい方の論点です。
これがなぜあまり語られないのか?
それは数値化しにくく可視化しにくいという点もありますが、もっと端的にホームページ関連の事業者や広告収入を目的としているサイト運営者があまり気にしない点であるからです。
それは単純にホームページという枠組みを超えたマーケティングのあり方です。
もっとシンプルに表現すれば、旧来からの商家、商人が目の前の商品をいかに売るかということを本気で楽しんで考えることに似ています。
さらにより良い商品をどうやって作るか、より良い提供の仕方はどのようなものかを楽しんで考えるというようなものになります。
アクセス数とCVとの相関関係の空間から脱する

アクセス数と実際のCV(コンバージョン、転換。ここでは閲覧者からの問い合わせ等の行動)との相関関係から「アクセス数を増やせばCV数も伸びるだろう」というのは、客観的に可視化された数値しか見えない人たちの漠然とした方法論です。
それも一つの方法論ではありますが、確率論の空間に縛られており、現状の最適化を強化するだけになります。それは時流の変化によって効果がジリ貧になることが予測されます。
アクセスの低下はCVの低下を意味し、アクセスの低下に恐れを抱くようになり、SEOやWeb広告に囚われるようになります。
結果が出なくても構わないという情熱と冷静さと面白さ

「目の前の商品をいかに売るかということを本気で楽しんで考えること」というのは、逆説的になりますが、「結果が出なくても構わないという情熱と冷静さと面白さ」が必要になります。
ホームページ集客のあり方として、「1ページを丹念に作る」ということになります。
しかしその「丹念に作る」という意味は、Webデザイナーが美しいデザインのページを作ることを意味するのではありません(それはそれで良い要素ですが本質は異なります)。
ここでいう「丹念に作る」ということの定義としては、ホームページを運営する企業が「結果が出なくても構わないという情熱と冷静さと面白さ」をもって「どのようにしてユーザーにメッセージを伝えるか?」ということを考えるということになります。
企業の内側にいる者の盲点

企業の内側にいると、その製品やサービスの利点や利用法について固定観念が生まれやすく盲点が発生しやすくなります。
実際の利用方法として顧客の声を聞いてみると「そのように使われていたのか」と驚くようなことがたくさんあります。
誰よりもその製品やサービスのことを知っているつもりでも、その魅力は内側にいると発見しにくいという特性があります。
弊社のWebコンサルティングはWebマーケティングを中心としたサービスですが、本質的にはマーケティング全般のコンサルティングとなります。
企業の外側から魅力を再発見し、それをホームページで表現する道筋を設計したりしています。
ホームページ集客を丸投げしてよいのだろうか?

ここで「ホームページ集客を丸投げしてよいのだろうか?」という疑問が起こります。
もちろん「よい」という人もいるでしょう。
まがい物を大量の広告で「一度限り売りつける」というのならばそれが一番合理的です。
また当座の資金に困っており、中長期的視点を検討する余裕がないという場合もそれでよいでしょう。
しかしながら、少ないアクセスでも結果を出すことができれば、ホームページの費用対効果は高いものになります。
さらにアクセス数が多くなれば、その効果はアクセスとの純粋な比例ではなく指数関数的に効果が高まります。
本格的なSEO単体のサービスを展開しない理由
弊社では、現在本格的なSEO単体のサービスを展開していません(SEO簡易分析のサービスは取り扱っていますが、これはホームページの改善提案のバージョン違いという位置づけです)。Webコンサルティングにおいては、基本的にトータルのマーケティングに着目し、Webマーケティングの企画設計を中心にサービスを提供しています。このためSEOだけに着目したコンサルティングは実施していません。
その理由のひとつは、SEOにだけ注力しているということは、単に「アクセス数を稼ぎたい」という姿勢になりやすく、根本的なところが欠けている場合が多いからというものになります。
もう一つの理由はより根源的です。
それは全体を考えたトータルWebマーケティングが弊社サービスのあり方であるからです。
「トータルWebマーケティング」
ホームページ集客に限らず抽象化したWebマーケティング、さらに抽象化した企業のマーケティング全体や事業の全体像自体を考えること。
それがホームページ集客にとって重要であり、遠回りに見えてもが結果的に少ないアクセスでも結果を出す方法を発見する最短ルートになります。
少ないアクセスでも結果を出すホームページ集客の実践方法

少ないアクセスでも結果を出すホームページ集客の実践方法は、単純と言えば単純です。
「見込み客と出会い、見込み客の心が動くこと」
それだけです。
ホームページを制作し、必要なページを丹念に作り、多少のアクセスがあればホームページ集客を実践することができます。
もちろん「何をどのように書くか」という文の作成に不慣れな場合もあります。
しかし周りに得意な人もいるはずです。
おそらく探せば一人か二人は得意な人がいると思います。
(それでも見当たらない場合は、ご相談ください)
例)見込み客の意図に応じた「言語化」

例えば、あるサービスに対して、同じ機能を求めている場合でも見込み客の意図はバラバラです。
「3年だけ持てばいいので安価なものを」
「多少の費用はかかっても10年以上継続利用したい」
ある意図に合わせたサービスに絞るのか、それとも両方をカバーするのかは事業のあり方の問題となります。
絞り込む場合でも両方を対象とする場合でも、それぞれ具体的に伝えるメッセージは異なってきます。
共通点もありますが、伝えるべきメッセージは真逆の場合もあります。
ホームページを制作する時に、良い表現をすればそれらを包括した、抽象化した表現になりがちです。
「Aというサービスを取り扱っています」
というような表現になります。
そして価格表が掲載されていたとします。
| サービス名 | 耐用年数 | 価格 |
|---|---|---|
| A-1 | 3年 | 100000円 |
| A-2 | 10年以上 | 250000円 |
しかし
「Aというサービスを取り扱っています」
「A-1は、耐用年数は3年程度ですが、安価に提供しています」
「A-2は、価格は高いですが、10年以上の耐久性があります」
と、ページ内容を具体化することで見込み客のニーズに対応します。
価格表を入念に読み込めば、{A-1=耐用年数3年、安価」「A-2=耐用年数10年以上、高価」という事はわかりますが、「丹念に作り込む」とは、そうした意図を言語化してしっかり表現するということになります。
これは一例です。
例)「なぜその価格なのか?」の説明

もう一つ例を掲載しましょう。
「なぜその価格なのか?」ということの説明が不足しているケースが良くあります。
例えば、ある植物の精油(エッセンシャルオイル)があったとします。
その精油の名前で検索すると、同一量で半額、1/3の価格のものがたくさん販売されています。
すると商品選択をしているユーザーは、「何によって価格が決まっているのかがわからない」という混乱が起こります。
「安すぎるものはまがいものかもしれないし、かといって高額なものは、単に高額に設定されているだけかもしれない」
「精油(エッセンシャルオイル)は、100%天然成分無添加のオイルであり、用途はアロマテラピー」
「アロマオイルは、精油に添加物が組み合わされたものであり、用途はルームフレグランスなど」
という分類により、「精油(エッセンシャルオイル)であるから価格が高い」ということを伝え、さらに、「原料にもランクがあり、最高級の原料を使用しているため高額になる」という説明があればユーザー(見込み客)は納得します。
もちろん、購入動機はユーザーごとに異なるため、すべての見込み客がそれを受け入れて購入するかは別問題です。
「精油といえば100%天然成分無添加のオイルだから高いのは当然だろう。さらに原料の原産地を見れば最高級で高額になることくらいはわかるはずだ」
というのは、販売側から見ればある意味「当たり前」です。業界人向けの販売であるならばそれでも良いのかもしれません。
しかし一般ユーザーの知識量は千差万別です。
これらを丹念に作り込んでいけば、自然とホームページの集客は実現していきます。
その上で適切なページ設計、サイト全体の構造設計やある程度のアクセス確保を行えばWebマーケティングは成功します(しかしながらこれら方法は、Web専業でないと少し難しいかもしれません)。
画像素材を工夫する

「ページを丹念に作る」という点で考えれば、画像素材を工夫するということも一つの方法となります。たくさんの費用をかけて美しい画像を生成したり、AI(人工知能)を活用して画像を自動生成するというのも一つの方法ですが、大切なのは「何を伝えるか?」です。
独自性のある画像を用いることはもちろん、手書き画像素材を利用することで、より一層メッセージが伝わることがあります。
「送り手の気持ちが伝わり、受け取り手の気持ちが動く」ということが大切です。
そう考えると手書きの画像の方が個性や臨場感が伝わりやすいのではないかと思います。
こうした工夫は、美しく整った画像の制作を外注したりAIを利用しなくても可能な工夫です。
新規ホームページ制作を実施する必要はない

少ないアクセスでも結果を出すホームページ集客の実践においては、新規ホームページ制作、大幅なリニューアルを実施する必要はありません。
重要であるのはページ内容であるため、既存ホームページの改良で十分です。
意図の言語化や用途の明示といった具体的な内容を掲載することは、キーワードが増えることにも繋がります。
そうすると検索エンジンを経由してアクセスがやってくる可能性が高まります。
内容の充実によって接点が生まれる可能性が高まる、つまり「縁が生まれる」ということになります。
見込み客、検索ユーザーの「あれをこうしたいなぁ」という「意図」、つまり因があり、検索エンジンや「ホームページ」という縁によって結ばれ、問い合わせ等の「結果」が生起するということになります。
もちろん新規ホームページ制作を実施しても構わない

もちろん新規ホームページ制作を実施しても構いません。
場合によってはその方が、意志を反映しやすくなるという場合もあります。
現在利用しているホームページが更新しにくいものであったり、追加修正に毎回費用がかかるものである場合は、自社で更新しやすいWordPressサイトなどに変更した方が、中長期的には理に適っている場合があるからです。
アクセス数に囚われる必要はありませんが、丹念に作り込んだページであるのであれば、どうせなら検索エンジンからのアクセスを獲得しやすいページにしておいた方が、やりがいを感じますし、さらにページの価値は高まります。この時点で、SEO(検索エンジン最適化)が意味を成してきます。
ホームページ集客の実践の手順

ホームページ集客の実践の手順として、端的にはアクセス数やSEOを考える前に内容の充実の方に意識を向けなければならないということになります。
そこまでできそうにないという場合は、最初からホームページ集客を考えないということも選択肢のひとつとして入ってきます。
企業の公式ホームページ、YouTube、Instagram、LINE、メルマガ、ブログ…といったところは、「どこで表現するか?」というだけの問題です。もちろんそれぞれに特性もあり、テクニックもあり、ユーザー層も異なります。
ただ、「どこで表現するか?」の前に「何を?」が来るのは当然です。
ゴールは徹底的に抽象化し、逆にホームページやそのコンテンツ(ページ内容)は徹底的に具体化するのが理想です。
もちろん「何を伝えればいいのか?」という点において、どの製品やサービスのことを伝えたいのかは明白です。しかし、それを具体化する場合に足が止まってしまう場合があります。
感情と行動の壁を破る「葛藤」の観察 読者の中に生まれる「葛藤」とは何でしょうか??
ここで、方向性を読者、ユーザー側に思いっきり向けて、さらに具体的に感情と行動の壁を破る「葛藤」の観察について触れてみます。
私たちのホームページ(ウェブサイト)を訪れる方が抱える「葛藤」とは、単に迷っている状態ではありません。心理学的な視点から見ると、それは「変化を強く望んでいるのに、意識的な努力や選択では、その一歩を踏み出すことができない精神的な緊張状態」です。
一般的には「個人が複数の相反する動機、要求、欲求の板挟みとなり、一つの決定や行動を選択できない精神的な緊張状態」と定義されます。
換言すれば、自己成長や現状の変化を強く望んでいるにもかかわらず、「意識的な操作(意図的な行動選択)」ではその変化を生じさせることができない状態が葛藤です。
心の中では「変わりたい」「集客を成功させたい」と願っている。
それなのに、どうしても手が止まってしまう。
この矛盾した状態こそが、私たちがまず深く理解すべき、読者の抱える最も重要な壁です。
葛藤を生む「抵抗」 情報不足は本当の理由ではありません
多くの場合、コンテンツは、この葛藤を解消するために「情報」が足りていないのだと考えがちです。
正しい手順やノウハウを教えれば、読者は行動できるだろう、と。
もちろん、本当に情報が不足している場合は、その提供(ハウツー)は有用性を持ちます。具体的な選択肢が増え、意識的に「何をすべきか」を選べるようになるからです。
しかし、ほとんどのケースで、行動を阻む本当の抵抗は情報不足ではないかもしれません。
1. 変化への不安がブレーキをかける「損失回避の心理」
読者の心の奥底には、「変化を選ぶことで失うもの」への恐れが潜んでいます。
それは、時間やお金といったコスト、失敗したときの失望、今の安定を崩すことへの漠然とした不安などです。
人は、利益を得る喜びよりも、損失を回避することを重要視します。この本能的な「損失回避」の心理が、「情報を見るのはやめておこう」「今はまだ動くときではない」という無意識のブレーキとなって、行動を止めてしまうのです。
2. 「義務感(have to)」が思考を狭める
「集客をしなければならない」「SNSを毎日更新すべきだ」という義務感、つまり外側からのプレッシャーで動いているとき、私たちの心は疲弊し、思考の抽象度が低下してしまいます。
視野が狭くなり、新しい情報を見ても「どうせ自分には無理だ」と判断してしまったり、本来重要なはずの「行動したい(want to)」という内発的な動機を見失ってしまいます。
読者の視界をひらく共感のストーリーとプロセスの重要性
単なるハウツーの羅列では、この無意識下の「損失回避」や「義務感」という真の抵抗を乗り越えることはできません。
私たちが本当にすべきことは、読者の「なぜ葛藤が生まれるのか」という心の機微に深く寄り添い、彼らの内側の不安を理解することです。
特定の顧客の気持ちに共感し、その葛藤を乗り越えるためのストーリーや段階的なプロセスを示すこと。これにより、「私だけではないんだ」「この方法なら自分にもできるかもしれない」という視界がひらけ、無意識下のブレーキが解除されます。
これが、読者を「have to」の空間から救い出します。自然と「want to」へと変化します。
こうした丹念さが、少ないアクセスでも熱量の高いファンを生み出すための重要なポイントとなります。
弊社では、ホームページ制作のハイグレードプラン(簡易Webコンサルティングが含まれています)やWebコンサルティングにおいて、こうした内容の充実、具体化、全体設計において共にご相談させていただいています。
(初回投稿日 2025年4月3日)






