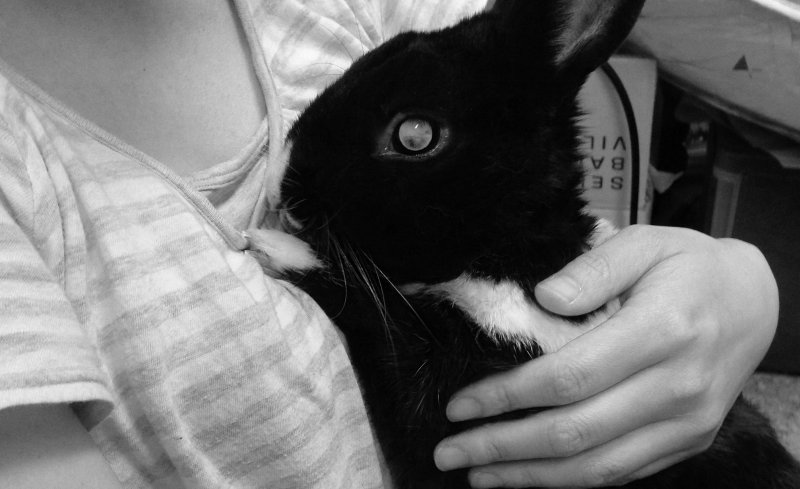「無能な営業」を雇っていませんか?ホームページ制作で成果を出す人が必ず持つ 「営業スタッフ」的プランニングを解説します。
ホームページを「最強の営業スタッフ」にするために
無能な営業スタッフとは、実は御社のホームページのことかもしれません。
「Webで『売上を作る仕組み』を作る」
それがWebマーケティングの本質です。
そう考えると「営業力のないホームページ」は、どう評価されるべきなのでしょうか?
高い制作費用をかけたにもかかわらず、問い合わせも注文もないホームページは、給料だけを払い続けている無能な従業員と同じです。訪問客が来ても、ただカタログを見せているだけで、商談を成立させる気配がない。もし御社のホームページ(Webサイト)がその状態なら、今すぐテコ入れが必要です。
既にそのようなホームページを制作してしまっていたとしても、ホームページはどの時点からでも改良していくことができます。
今すぐにでも、何をどう改良すればよいのかが明らかになってから始めるのでもどちらでも良いと思います。
では、あなたの事業の成果に貢献する「成果を出す営業スタッフ」となるホームページ(Webサイト)は、どのようにプランニングされるべきでしょうか?
この問いへの答えは、金融の営業経験を持つ私と、営業手当だけで三桁に上る現役スーパー営業マンとの「銭湯での密談」にあります。
(営業成績が全国トップクラス、不動産関係の上場企業の営業スタッフです)
今回は、このプロフェッショナルの視点から見えた「凄腕コンテンツ」を生み出すサイト設計の考え方をお伝えします。
アクセス数を追うだけでは手に入らない、深い信頼を勝ち取り、御社のホームページ(Webサイト)を「最強の営業スタッフ」にする具体的なプランニング手順を解説していきます。
無能なホームページが抱える「3つの特徴」をはっきりと定義します

「うちのホームページは本当に成果が出ないのか?」と疑問に感じたなら、それは優れた一歩です。
「やはり改良した方がいいのか?」という変化に気づくことから始まります。
優秀な営業スタッフであれば決して犯さない、致命的な「営業の失敗」を、ここではっきり「無能なホームページの診断基準」として定義します。
御社のサイトがどれか一つでも該当していないか、確認してみてください。
「ホームページ制作費」は既に支払済みかもしれませんが、日々機会損失が生まれているかもしれません。
(もったいないなぁ、と思うことがあります)
無能な特徴1:顧客の話を聞かない(一方的な情報発信)
御社のホームページは、一方的に話すだけの「自己満足営業」になっていませんか?
顧客の話を聞かない営業スタッフは、お客様の質問や不安を無視して、ただ自社の商品がいかに優れているかを熱弁し続けます。ホームページ(Webサイト)も全く同じです。
企業が「伝えたい情報」と、お客様が「知りたい情報」は、往々にして違います。
その溝を埋められず、自社の理念や実績を一方的に羅列するばかりのホームページ(Webサイト)は、お客様の抱える真の疑問や潜在ニーズを無視しています。これでは、お客様は「自分ごと」としてホームページ(Webサイト)を見てくれず、すぐに立ち去ってしまいます。
これは自社制作した場合や事前企画のない「型通りのホームページ」を販売するホームページ制作会社に依頼した場合などに多いケースです。
無能な特徴2:提案力がない(具体的な事例や証拠がない)
あなたの事業の「信頼できる証拠」を、本当に示せていますか?
優れた営業スタッフは、お客様の課題を聞いた後、必ず「他社ではこう解決した」という具体的な事例や、裏付けとなるデータを示します。これにより、お客様は「この人に任せれば間違いない」と確信できます。
しかし、無能なホームページ(Webサイト)は、「私たちは技術力があります」「信頼してください」といった抽象的な言葉を並べるだけです。肝心の実績紹介には数値的な結果がなく、お客様の声も顔写真すらない紋切り型かもしれません。
実績や専門性を示す証拠(E-E-A-T)が不足していると、お客様は最後の決断ができず、「また別の会社も見てみよう」と、すぐに離脱してしまいます。
こちらもホームページを自社制作した場合や、集客目線の企画のない「定式的なホームページ制作」を行うホームページ制作会社に依頼した場合などに多いケースです。
無能な特徴3:クロージングが曖昧(問い合わせまでの導線が不明確)
せっかく興味を持ってくれたお客様を、立ち去る前に「次はこれです」と導けていますか?
商談が盛り上がっても、最後に営業スタッフが「ご検討ください」とだけ言って席を立ったらどうなるでしょうか。お客様は次に何をすればいいか迷ってしまい、結局そのまま時間だけが過ぎてしまいます。
ホームページ(Webサイト)における最大の失敗の一つが、この「クロージングの放棄」です。サービスの詳細ページを読み終わったとき、記事を最後まで読んだとき、ページ下部にただ小さな問い合わせボタンがあるだけでは不十分です。
お客様が次に進むべき具体的なステップ(導線)が用意されていません。
例えば、「無料資料ダウンロード」「個別相談の予約」「導入事例集の請求」など、行動の選択肢を明確に提示しないと、せっかくの熱意も冷めてしまい、成約の機会を逃してしまいます。
アクセス数へのこだわりと「ポスティング」

ウェブサイト・ホームページを有効に「機能」させるためには、まずホームページへの「アクセス」が必要になります。
どんな広告物もそれが誰かの手元に届かなければ意味がありませんし、営業スタッフもひとまず営業先を確保しなければ、そもそも営業活動自体が始まりません。
しかしながら、単純なアクセス数の増加と、コンバージョンの増加は比例するわけではありません。
通常、ホームページのWebマーケティング活用を考えた時には、母数である「ユーザー数」を増やすことがひとつのポイントとなります。
メッセージを伝える時に必要となるのは、まず「メッセージそのもの」、そして「メッセージを届けること」です。
そこで考えられる方法は、SEOなどによる自然検索からのアクセス数の向上、ソーシャルネットワーク(SNS)でのシェアによるアクセス、そしてリスティング広告など、広告の利用などです。
チラシであればポスティングや折り込みの部数が、ホームページで言うところのアクセス数に該当します。DMならDM発送した数ですね。
ホームページ運用においてアクセス数(ページビューやセッション数)は目に見える指標であるため注目されやすい傾向にあります。
確かにアクセス数の増加は、認知拡大やWebマーケティング施策の効果を測る上で重要な数値のひとつですが、それだけを追いかけていても売上や成約にはつながりません。
本当にコンバージョン(問い合わせなどのユーザーの行動)に結びつけるには、「どのようなユーザーが、どんな意図で、どのページにアクセスしているか」といったアクセスの質を検討する必要があります。
プランニングなくコンテンツを増やしたり、SEOのリンク集めをしてアクセスを伸ばすこと

まずホームページが「誰か」に見られないと、そもそもの機能を持つことができないため、ひとまず考えられる方法で「アクセス数」を伸ばすことがひとつのポイントにはなります。
しかし、「単純にプランニングなくコンテンツを増やしたり、SEOのリンク集めをしてアクセスを伸ばすこと」は、営業スタッフが「闇雲に広告をばらまき、闇雲に電話アポを行い、汗水を垂らして走りながら、インターホンを鳴らして飛び込み訪問をしていること」に似ています。
当然ながら、Webマーケティングの本来の目的は「ホームページへのアクセス」ではなく問い合わせや資料請求などの「コンバージョン」です。
そしてそれが、「実際の営業活動における成約」など「企業にとって売り上げにつながるかどうか」という点です。
※コンバージョンとは、問い合わせ、資料請求、購入、予約、LINE登録など、ユーザーが企業側の目的に沿って行う具体的なアクションを指します。
コンバージョンにつながらないアクセスばかりになると最終的な売上向上には繋がりません。
数だけが目的になり、質が問われていない
確かにチラシでいうポスティング部数や営業スタッフでいう、営業の面会件数はその後の売上までの中間の数値目標として考えてもよいのですが、数だけが目的になり、質が問われていないというポイントに着目したいところです。
ホームページに訪れるユーザーが、Webマーケティングにつながるような企業のサービスを調べに来たわけではなく、「趣味的な情報を検索してたまたま訪れた」という場合が多ければ滞在時間も短く直帰率は高くなりがちです。
その前に、サービス利用につながる確率はかなり低いユーザーです。
企業名を知らず、サービスや商品にも興味がない状態でアクセスした場合、せっかく訪問しても目的のコンテンツがなければ即座に離脱されてしまいます。このようなユーザーは、Webマーケティング視点で見れば「質が低いアクセス」に該当します。
彼の会社では、物件情報のチラシの配布を自分で行うことがあるそうなのですが、新人営業スタッフは数千枚ポスティングをして、翌日以降連日問い合わせはゼロ。
一方彼の上司の凄腕の方は500枚のチラシ配布で、翌日2件の問い合わせを得るそうです。
ホームページの費用対効果についてお伝えしましたが、ホームページのマーケティング活用や費用対効果を考える上で、この構図は見逃すことができないのではないでしょうか?
「質の高いアクセス」とは、明確なニーズや課題を持ち、それに関連する情報を探していて自社サービスに親和性の高いユーザーの訪問を意味します。特にユーザー側でニーズが顕在化しており、自社サービスとの相性が高い、自社サービスこそがそのユーザーの課題を解決できるという場合はWebマーケティングに繋がりやすくなります。
例えば、検索エンジン経由で「地域名+業種名」や「サービス名+料金」などの具体的なキーワードで流入してきたユーザーは、その関心の高さからコンバージョンに結びつく可能性が高く、質の高いアクセスとして評価できます。こうした見込み顧客を安定的に集めることWebマーケティングは形になっていきます。
優秀な営業スタッフの「思考プロセス」をホームページ設計に落とし込みます

無能なホームページが抱える問題点が明確になったら次は解決策です。
単にWebデザインを変えるのではなく、成果を出し続ける優秀な営業スタッフが商談前に何を考え、どう行動しているか、その思考プロセスをそのままホームページ(Webサイト)の設計に適用します。
ここからは、いよいよ具体的なプランニングの話です。
「改善」「改良」という朧気なイメージを具体的にしていきます。
どのように改良していけばよいのかが徐々に明らかになっていくでしょう。
優秀な営業の思考1:ペルソナ(お客様像)の徹底的な理解
優れた営業は、会う前にあなたの「不安」と「要望」を全て予測しています。
優秀な営業スタッフは、お客様に会う前に徹底的に下調べを行います。お客様の事業の状況、業界の課題、そしてお客様がその商品・サービスに何を求めているのか、あらゆる「不安」や「疑問」を事前に把握しようとします。
ホームページ(Webサイト)のプランニングも同じです。サイトマップやコンテンツを作成し始める前に、まず「誰に」「何を」解決したいのかというペルソナ(お客様像)を詳細に定義してください。
そして、そのお客様が抱えるであろう不安や疑問を完全にリスト化します。このリストこそが、ホームページ(Webサイト)のページ構成(情報設計)を決める設計図となります。お客様の「知りたい」に全て応える構造こそが信頼獲得の第一歩です。
ポイントのひとつは「ニーズ」にある

一般的に、営業と販売の違いは、相手のニーズのレベルにあります。
販売は、根本的にニーズがあり、それが表面化している中で、該当商品やサービスを「選ぶ」段階にあります。
一方、営業は、ニーズが潜在化しており、提案によってニーズを顕在化してもらうことが必要な要素として考えられます。
端的には、販売は「放っておいてもそこにあれば売れる可能性があるモノ」、営業は「ニーズに気付いてもらわないと売れる可能性がないモノ」といったイメージです。
販売であれば、ひとまず数を増やすと言ったことも有効的かもしれませんが、営業ではその営業効率を高めるために対象者を選定する必要があります。
ホームページを営業スタッフとして考えた場合には、まず、提案によってニーズが顕在化する客層との接点をつくり、かつ、ホームページ上で「ニーズに気づいてもらう」ということが必要ではないでしょうか?
もちろん、販売であっても、こうしたニーズの顕在化への活動は販売数に影響を与えます。
なお、余談ですが、私たちの取り扱っている「ホームページ制作」などのサービスも営業が必要な部類に入ると考えられます。
ニーズの顕在化レベル

「集客アップを叶えるホームページ」と、値札を付けつつiTunesのように「販売カード」をコンビニに置いてもらっても、レジに進んで買おうという人はおそらくいないでしょう。
また、「ホームページどうですか?」といきなり言っても、それで「よし、依頼しよう」
ということにはほとんどならないと考えられます。
そこで、先ほどの話の中で、「チラシをポスティングして問い合わせを得る」ということを考えてみた時、この「ニーズの顕在化度合い」が営業の成功要素として重要なひとつのポイントとして考えられます。
そして、ニーズと合わせて購入の実現可能性が本当にあることが必要になります。
- ニーズの顕在化レベルがなるべく高いこと
- 実現可能性が高いこと
実現可能性も要素のひとつ

小学生に「家が欲しいですか?」と質問すると「欲しい!」と答えるかもしれませんが、おそらく即金で購入したりローンを組むことはできません。
大学生に同じ質問をした場合、「いつかは欲しい」と答えるかもしれません。
この場合は、ニーズ自体はあっても、現段階での実現可能性がないことを知っているからです。
先ほどの「凄腕の上司」の方は、ニーズがある程度顕在化していそうで、かつ購入の可能性のある世帯にだけ、「購入が視野に入る規模の物件の情報」のみをポスティングをしたそうです。
一方、新人営業スタッフは、該当エリアに様々なジャンルの売買物件情報が掲載されたチラシをくまなくポスティングしたそうです。
真面目なスタッフさんのようですので、もしかしたら「学生マンション」にも投函しているかもしれません。
ホームページ制作においても、そのプランニングや作り込み、SEOの初期設計段階において、対象者の絞込を行って、Webマーケティング効率を高めることが重要になるでしょう。
優秀な営業の思考2:商談(コンテンツ)の「流れ」の最適化
ページを訪れたお客様を、迷わず成約へ導く「最強のストーリー」はありますか?
お客様のニーズを理解したら、次はどう商談を進めるか、全体の流れを設計します。無能な営業スタッフは、お客様に興味のあるページを勝手にクリックさせて終わりますが、優秀な営業スタッフは、必ず「この順番で情報を伝えれば、お客様は納得し、契約してくれる」というストーリーを持っています。
ホームページ(Webサイト)においても、この「商談の流れ(ユーザー導線)」を計画的に設計することが極めて重要です。
トップページからサービス詳細、そして問い合わせに至るまで、お客様の感情と理解度を高める順序でコンテンツを配置します。
具体的には、
- トップページ:あなたの課題を理解していますよ、という挨拶と共感の提示(商談の導入)
- サービスページ:課題に対する具体的な解決策とメリットの提案(本題のプレゼンテーション)
- 価格・事例ページ:不安を解消する裏付けとコストの明確化(リスクの払拭)
というように、すべてのページで次に進むべき明確な行動(導線)を示す必要があります。ホームページ(Webサイト)全体を、お客様をゴールまでスムーズに運び切る、一つの「設計されたストーリー」として機能させましょう。
「凄腕コンテンツ」を生むための具体的な着眼点

優秀な営業スタッフが、どんなに美しいトークを展開しても、最後に「当社の事例をご覧ください」という説得力のある一言がなければ、契約は成立しません。
優れたプランニングと導線設計に決定的な「証拠」を組み込むことが、ホームページ(Webサイト)を凄腕の営業スタッフへと進化させます。
感情に訴える「事例トーク」の重要性
お客様が求めているのは、単なる実績ではなく、「自分と同じ成功体験」です。
無能なホームページ(Webサイト)は、導入実績ページに会社のロゴと名前を並べるだけで終わります。
しかし、優秀な営業スタッフは違います。
彼らは、過去の成功事例を語る際、単なる結果ではなく、「お客様が抱えていた不安」から始まり、「具体的な提案」によってその不安が「どう解消されたか」という感情のストーリーを語ります。
ホームページ(Webサイト)の「お客様の声」や「導入事例」ページは、まさしくこの「事例トーク」の場です。
単に成果(売上○%アップなど)を語るのではなく、御社のサービスを導入したお客様が「以前はこんなに困っていた」「導入後、〇〇という未来が手に入った」という、ビフォーアフターの感情的な変化を伝えてください。
これが、読み手に「自分もこうなれる」という強いイメージと信頼(E-E-A-T)を与え、「この事業に任せよう」という最後の決断を後押しします。
どこもかしこも同じようなことを言っている場合、競合と自社を区別することができません。
それは意志決定の際の決定要因が不足することになります。
ホームページのコンテンツSEO

同じようなことが、「ホームページのコンテンツ」にも言えるかもしれません。
ページ数を増やしたり、様々なキーワードでの「アクセス」を得ようと、様々なコンテンツを配信しているケースがよくあります。
確かにそれでアクセス数は向上するかもしれませんが、先ほどの「新人営業スタッフ」のような結果が待っているかもしれません。
ポスティングも、チラシ印刷代、スタッフの人件費などが必要なため、もちろんコストがかかります。
同じように、コンテンツの配信にも最低限、電気代と人件費が必要になります。
コンテンツ自体が持つ集客効果に期待したり、コンテンツSEOの効果を期待して、記事を配信していくことは方向性としては有効的です。
しかし、全体的なSEOやWeb集客のプランニングを飛ばしてしまうと、営業ロスが多い営業スタッフのように、走り回っている割に結果が出ない、というような事態になってしまうおそれがあります。
重要な部分からプラスしていく

コンテンツSEOによって、ホームページのアクセスを向上させる事自体は、必ずプラスにはなりますが、「プラス」であればそれでいいというわけではなく、まずは重要な部分からプラスにしていく必要があります。
ウェブデザインに費用をかけることも同じかもしれません。しかしながら、ホームページ制作においては、Webマーケティング効果向上に関する重要な部分からプラスしていく必要があります。
例えば、店舗にインテリアをひとつ追加すれば、それは確かに「お店の雰囲気向上」には貢献してくれるかもしれません。
しかしながら、そのインテリアを見る人の数が増えなければその「貢献」もあまり期待することができません。
コンテンツSEOとそれぞれの「重要度」

限られた費用をどう分配するかということがキーポイントとなりますが、まずは「重要度の高いもの」から費用をかけていく必要があります。
コンテンツSEOにかかるコンテンツプランニングや、メインコンテンツの制作にあたり、きちっとした「ベースとなるコンテンツ」を軸にすることが重要になります。
内部最適化によるSEOやコンテンツ増加なども「プラスの要素」ですが、軸を外した「プラス」を狙うと、当然結果も軸がずれてきます。
特にコーポレートサイトでは、単純な「アクセス数」ではなく、潜在客層からのアクセスといった「有効なアクセス」を増やしていく必要があるでしょう。
この構造は、先ほどの話の中の「ポスティング」と共通する部分があります。
釣りのたとえ

私はあまり表現が好きではないのですが、営業の世界には「釣りのたとえ」というものがあります。
ひとことで言うと「魚のいない場所で釣りをするな」ということのようです。
そして、魚のいる場所で釣りをする場合でも、その魚が好きなエサを選ばなければならないということのようです。
同時に、高い釣具を使っても、「魚のいない場所」で「魚が食いつかないエサ」で釣りをしても収穫はないということを意味しています。
趣味の釣りなら、結果が出なくても良いのかもしれませんが、漁師さんなら死活問題です。それと同じように、営業の分野にいる中で、走り回った挙句、結果が出ないというのは問題です。
それと全く同様に、結果が出ない、成果の出ないホームページは、それを利用する企業にとって本来もっと問題視されるべきではないでしょうか?
ホームページの企画やコンテンツプランニングに共通

「ニーズがある方」に出会うことができないのならばコストはかかる一方です。
あれこれお話しても「どこにもニーズがない」方に、営業をすることはタダの「押し売り」です。
そして「隠れたニーズ」があるにも関わらず、それに気付いていただくことができない場合は、まだまだ営業スタッフとしては修行の余地があります。
これらの要素は、すべて、ホームページの企画やコンテンツプランニングに共通しています。
営業効率を高めることを意識する
このことを意識して、Webマーケティングやホームページの企画に応用する必要があります。ホームページを営業スタッフとして考え、ホームページ制作の手前の企画段階で、営業効率を高めることを意識していくことで、効果的なホームページの全体像が見えてきます。
そして、営業の対象者の絞込と同じように、ただのホームページのアクセスアップではなく、「有効なアクセス」を向上させること、SEOやコンテンツSEOの本質はそんなところにあるのではないでしょうか。
(初回投稿日 2016年8月11日
ホームページを「営業スタッフ」として考えてプランニング・制作すると答えが見えてくる)