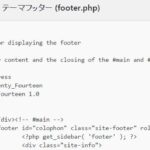近年セマンティックHTMLが再評価されています。セマンティックHTMLとは、Webページのコンテンツが持つ「意味」や「役割」を、HTMLのタグを使って正確に伝える記述方法です。見た目を装飾するためではなく「見出し」「段落」「ナビゲーション」などの情報を明確に示し、その情報のその部分が何であるかを明確に定義します。これにより、検索エンジンや音声読み上げソフトなどの機械がページ内容を正確に理解できるようになりウェブアクセシビリティや検索性、将来的な拡張性が高まります。
ただ、元々HTMLは文書であり論理構造を示すものがHTMLマークアップです。しかし歴史的にWeb黎明期にはその目的がしっかりと確認されていましたが、Webデザイナーが増え、Webデザインにおいてグラフィックが重視され、これらの役割は蔑ろににされていきました。
その一方、検索エンジンの進化やAI、大規模言語モデル(LLM)の台頭によって、セマンティックHTMLの重要性が再確認されています。
そこで今回は、セマンティックHTMLの重要性や本来の役割を、HTMLの歴史からそれが軽視された背景、そして再評価されるきっかけとなった現代のLLMO(大規模言語モデル最適化)に至るまでを概観し、実際のHTMLマークアップによるセマンティックHTMLの記述例について触れていこうと思います。
インターネット黎明期のWeb・HTMLの役割は「学術文書の共有」

インターネットが世界に広がり始め、Webページというものが誕生した頃、HTMLはまさに「文書」を作るための言葉でした。その起源は、もともと学術論文や研究データを世界中の研究者が共有するための仕組みにあります。
だからこそ、HTMLは単に文字を表示するだけでなく、その情報がどんな意味を持っているのか、論理的な構造を明確に伝える役割を担っていました(そうした点は現在でも変わりありません)。
たとえば、<h1>タグは「このページのいちばん重要な見出しですよ」と示し、<p>タグは「ここからここまでが一つのまとまった段落ですよ」という意味を持っていました。箇条書きにしたい情報があれば<ul>や<ol>を使い、項目ごとに意味を付与していたんです。これらのタグは、情報を整理し、それらが持つ意味をはっきりと示すための「骨格」だったんですね。
当時のWebは、今のようなカラフルで動きのあるものではなく、シンプルにテキストとリンクが中心でした。だからこそ、HTMLの役割は、どんな環境でWebページを開いても、あるいは目の不自由な方が音声読み上げソフトを使っても、誰もがその内容を正確に理解できるように、情報そのものの論理的な繋がりを定義することにありました。
デザインよりも情報の伝達とアクセシビリティが何よりも優先されるべきだった時代のお話です。
グラフィックデザインの台頭と「見た目」への傾倒

Webの黎明期が過ぎ、時代が進むにつれて、Webサイトは単なる文書の共有ツールから、もっと魅力的で表現豊かなメディアへと変わっていきました。この変化を大きく後押ししたのが、CSS(カスケーディングスタイルシート)の登場です。
CSSは、文字の色やサイズ、画像の配置、余白の調整、さらにはアニメーションまで、Webページの見た目を自由にコントロールする力を私たちに与えてくれました(ホームページのCSS・スタイルシート編集方法)。
グラフィックデザインの世界で培われたスキルを持つデザイナーたちがWebの世界に参入し始めると、Webページはどんどん「魅せる」ことに力を入れるようになります。美しい写真やイラスト、洗練されたレイアウト、インタラクティブな要素が次々と取り入れられ、ユーザーの目を引きつけることに主眼が置かれるようになりました。
ただ、個人的にはここで違和感を持ちました。
「HTML文書をしっかりとマークアップすることは、視覚障害を持つ方にも音声読み上げで情報を伝えることができる。いわばウェブアクセシビリティだ。でも世間はきれいなフォントを使いたいがために(当時は現代のような美しいWebフォントを使用できませんでした)、ボタンなどをすべて画像化していてaltも付けない。HTMLは文書だと言ってもグラフィック上がりの彼らには伝わらない」
この「見た目」を重視する風潮の中で、HTMLタグの使い方も少しずつ変わっていきました。本来、意味を伝えるためのタグが、視覚的な効果を出すためだけに流用されることが増えたんです。
例えば、単に文字を大きく表示したいからという理由で、内容的には見出しではない部分に<h1>タグを使ったり、文字を太くしたいだけで<strong>タグを使ったり。このように、情報が持つ「意味」よりも、画面上での「見た目」を優先するあまり、HTMLが本来持っていた論理的な構造が薄れてしまうケースが少なくありませんでした。
SEOの依頼でページを確認すると、余白をつけるために「引用タグ」を使っており、そのページの本文の大半が「引用部分」となり、正規の本文がほとんどないため(本当はあるのですが…)検索エンジンから除外されているということもありました。
ウェブアクセシビリティ
昔からセマンティックは、SEOの面では多少意味のあることでした。というより本質は、ウェブアクセシビリティです。「ユーザーのための配慮」は、「検索エンジン最適化と切り離せない」というか、評価される要素として考えるのはそう難しくありません。
その一方で、よくデザイン系のWebデザイナーや広告代理店に冷やかされました。
「そんなことして何になるんですか?」ってね。
「効率悪くないですか?」というような言葉の裏に
「そんなことを設定して費用を高くするつもりじゃないでしょうね?」
という威圧もありました。
しかし、画像でボタンを作ったり、画像の中にだけメッセージを込めるというのはいいですが、きちんとaltを指定しておかないと音声読み上げができません。
つまり、視覚障害を持つ方には、何が書いてあるかわからないページになります。
そうなるとウェブアクセシビリティを心がけるのは当たり前だろうという気にはなるのですが、
おしゃれ気取りの「グラフィック中心のWebデザイナー」や
コスト面や収益のことしか頭にない「広告代理店」には、
「意味なくないですか?」と冷やかされました。
まあ話が通じない人を説得する気はありません。
昔はCSSのグラデーションもブラウザのバージョンなどによって実装できたりできなかったりでした。できない場合はベタ塗りという指定をしたりしていました。そこでどの環境でもグラデーションにという場合、画像で背景を作ったりする必要がありました。
それはわかるんですが、きちんとaltなどを実装したりしてウェブアクセシビリティを高めた方がいいと考えています。必須ではなくベター領域ですが、「HTMLは文書である」というとよく冷やかされました。
はっきり言いましょう。
ホームページをチラシの延長だと思っているグラフィック系の人たちや制作発注の原価を下げたい広告代理店なんかが「効率悪くないっすか?」と、ウェブアクセシビリティを破壊していったんです。
Webデザイナーたちは、ユーザーにどう見せるか、どう感じさせるかに夢中になり、HTMLが文書としての骨格を持つことへの意識が、残念ながら薄れていった時期でもあったと言えるでしょう。
忘れられがちだった「細かな意味付け」タグの存在

Webのデザインが視覚的な表現に注力するようになると、HTMLの中には、見た目には直接影響しないけれども、情報としての意味を細やかに伝えるためのタグが数多くありました。しかし、これらは残念ながら、多くのWeb制作者の意識から遠ざかっていってしまいました。
たとえば、<abbr>タグは、略語(例えば「HTML」や「CSS」)が何を表すのかを補足するためのものでした。マウスカーソルを合わせると正式名称が表示されるといった機能はあったものの、それがなければページのデザインが崩れるわけではありません。また、専門用語や特別な概念を定義する際に使う<dfn>タグや、その定義内容をリスト形式で示す定義リスト(<dl>、<dt>、<dd>)も、本来は情報の構造を明確にするための大切な要素でした。Q&Aサイトや用語集など、情報とその説明をきっちり紐づけたい場面で、これらのタグはとても力を発揮するはずなんです。
他にも、<cite>タグで引用元を示したり、<q>タグで短い引用をマークアップしたり、あるいは**<time>タグで記事の公開日時やイベントの日時を機械が読み取りやすい形式で記述したり。連絡先情報を示す<address>タグ**もそうですね。これらはすべて、情報そのものの正確性や文脈、関連性を高めるためのタグです。
なぜ、これらの細やかなタグが「忘れ去られた」かというと、やはり「デザインに直接関係ないから」という理由が大きかったのではないでしょうか。CSSで見た目を整えることが主流になると、これらの意味付けのためのタグは、まるで舞台裏の道具のように扱われ、その存在意義が見過ごされがちになってしまったのです。
しかし、情報の「意味」を追求する今の時代に、これらの「古くて新しい」タグたちが、再び重要な役割を担う可能性を秘めているのかもしれません。
「意味」の再評価 セマンティックHTMLの重要性

かつてはデザインの陰に隠れがちだったHTMLの「意味」という側面が、今、再び強く求められるようになりました。これは、Webを取り巻く環境が大きく変化し、単に情報を「表示する」だけでなく、「理解する」ことがより重要になってきたからです。
現代のWebは、情報が爆発的に増え続けています。そんな中で、私たちの欲しい情報に効率よくたどり着くために、検索エンジンは日進月歩で進化を遂げてきました。彼らは、単にページに書かれたキーワードを見るだけでなく、HTMLの構造を深く分析し、そのコンテンツがどんな意味を持ち、どの部分が特に重要なのかを読み解こうとします。
例えば、<h1>タグでマークアップされた内容はそのページの主題であり、<main>タグで囲まれた部分は主要なコンテンツである、といったように、HTMLの構造から文脈や意味を推測するアルゴリズムが発達してます。
セマンティックなHTMLを使うことで、検索エンジンはあなたのWebページの内容をより正確に把握し、結果として関連性の高い検索結果として表示してくれる可能性が高まります。これは、あなたの事業を多くの人に知ってもらう上で、もはや避けて通れない要素と言えるでしょう。
「音声読み上げの需要」によりセマンティックHTMLの重要性が再認識された
さらに、スマートスピーカーやスマートフォンの音声アシスタントが普及したことも、セマンティックHTMLの重要性を再認識させる大きな要因となりました。これらのデバイスは、画面を持たなかったり、あるいはユーザーが画面を見られない状況で情報を伝えたりします。
視覚情報が限られる環境でWebページの内容を正確に理解し、ユーザーに届けるためには、HTMLが持つ意味が何よりも大切になります。
音声読み上げソフトがHTMLの構造を頼りに情報を読み上げるように、機械が情報を正確に把握するためのガイドラインとして、セマンティックHTMLは欠かせない考え方となっています。
このように、Webは単なる静的な情報表示の場から、機械が情報を解釈し、活用する場へと進化しているため、HTMLに込められた「意味」が以前にも増して価値を持つようになっているのです。
大規模言語モデル(LLM)とセマンティックHTMLの未来

私たちが今まさに体験している技術革新は、セマンティックHTMLの価値を一層高めています。特に、近年目覚ましい発展を遂げているAI、中でも大規模言語モデル(LLM)の登場は、Webコンテンツの利用方法に大きな変革をもたらしました。
AI(LLM)の登場とWebコンテンツの利用
LLM(大規模言語モデル)は、Web上の膨大なテキストデータを学習することで、人間が話すような自然な言葉を理解し、生成する能力を持っています。AI(LLM)がWebページを読み解く際、単なる単語の羅列としてではなく、その情報が「どのような文脈」で「どのような関係性を持っているのか」を把握しようとします。
ここで、セマンティックHTMLが持つ「意味」の明確さが非常に重要になってきます。
例えば、HTMLが論理的に構成され、見出し、段落、リスト、そしてそれぞれの意味を示すタグが適切に使われているWebページは、LLMにとって質の高い学習データとなります。
情報が構造化され、その意味が明確であるほど、AIはコンテンツの内容を正確に理解し、要約したり、質問に答えたり、あるいは新しいコンテンツを生成したりする際に、より信頼性の高いアウトプットを生み出せるようになります。
これは、Webのコンテンツが「情報源」としてAIに利用される未来において、その信頼性を高める上で非常に大きな意味を持つでしょう。
Web標準と持続可能な事業運営
Web標準の動きも、セマンティックHTMLの重要性を後押ししています。意味が明確なHTMLは、将来登場するであろう新しいデバイスや技術に対しても、柔軟に対応できる基盤となります。
例えば、数年後に私たちが想像もつかないようなデバイスでWebを閲覧するようになったとしても、意味がきちんと定義されたHTMLであれば、そのデバイスが情報を適切に解釈し表示してくれる可能性が高くなります。
これは、ホームページ(Webサイト)を長く運用していく上で、非常に大切な考え方です。一度きちんと意味を込めてマークアップしておけば、将来的な改修や新しい技術への対応がスムーズに進み、結果として事業を継続しやすくなります。
Web開発のコミュニティ全体でも、アクセシビリティやユーザビリティといった「誰もが使いやすいWeb」を追求する動きが活発になっており、その根幹にはやはりセマンティックHTMLの存在があります。
このように、セマンティックHTMLは、現在のAI技術の発展と、未来を見据えた持続可能なWeb開発の両方において、その価値を再認識されています。
実践!セマンティックHTMLによる「意味」の構築術

ここまで、セマンティックHTMLがなぜ今、再び注目されているのかをお話ししてきました。ここからは、実際に日々のWeb制作でどのように「意味」を構築していくのか、具体的なタグとその使い方を見ていきましょう。
決して難しいことではなく、少し意識を変えるだけで、あなたのWebページはより価値のあるものに変わります。
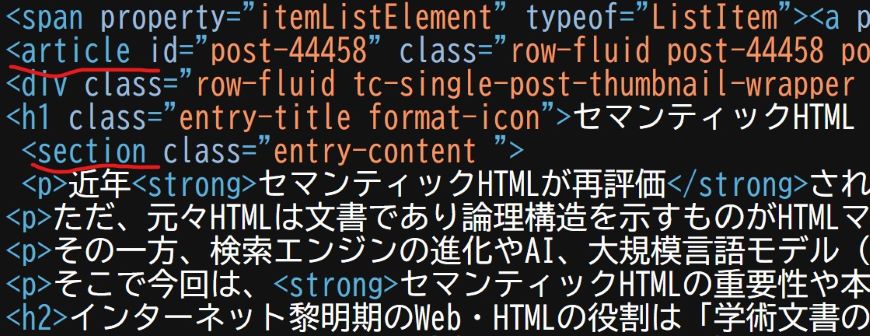
articleやsectionのマークアップ セマンティックHTML
主要なセマンティックタグとその役割
HTML5で導入された新しいセマンティックタグは、Webページの主要な部分に意味を与えるために設計されています。
<body>: これはもうご存知の通り、Webページのすべてのコンテンツを含む、まさに「本体」です。<body><header>: ページの導入部分や、セクションの冒頭を示すために使われます。サイト全体のロゴやナビゲーション、記事のタイトルなどがここに含まれることが多いですね。<header><nav>: ナビゲーションリンクのまとまりを示すタグです。主要なメニューや、目次のようなページ内リンクの集まりに使います。<nav><main>: そのページの主要な、かつユニークなコンテンツを囲むタグです。通常、1ページにつき1つだけ配置し、サイドバーやフッターなど、他の部分とは明確に区別します。<article>: 独立した完結した内容を持つコンテンツ、例えばブログ記事やニュースの投稿、フォーラムの投稿などに使います。このarticleタグの中身だけで意味が通じるべき、と考えるとわかりやすいでしょう。<article><section>: 文書内でテーマごとに分けられた、まとまりのあるセクションを示すタグです。汎用的なグループ化に便利ですが、見出し(<h1>〜<h6>)と一緒に使うことで、より意味が明確になります。<section><aside>: メインコンテンツとは直接的な関連が薄い、補足的な情報を配置する際に使います。サイドバーの関連リンクや広告、用語解説などがこれにあたります。<aside><footer>: ページの末尾部分やセクションのフッター部分を示すタグです。著作権表示、連絡先情報、プライバシーポリシーへのリンクなどがよく配置されます。<footer>
これらのタグを使うことで、「見た目をこうしたいからこのタグを使う」のではなく、「この情報はこういう意味を持つからこのタグを使う」という、本来のHTMLの考え方を取り戻すことができます。
「忘れられた」細かなタグの活用例
先に触れた、デザインに直接関係しないからと見過ごされがちだった細かなタグたちも、今の時代だからこそ、その真価を発揮します。
<abbr>
<abbr>は略語をマークアップし、その正式名称をtitle属性で提供します。ユーザーがカーソルを合わせると正式名称が表示され、読み上げソフトも正確に伝えます。<abbr>
<p><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>はWebの基盤です。</p>
<dfn>と定義リスト(<dl>, <dt>, <dd>)
<dfn>と定義リスト(<dl>, <dt>, <dd>)は、専門用語の定義や、Q&A形式のコンテンツで力を発揮します。<dt>で用語を、<dd>でその説明をマークアップすることで、情報が構造的に関連付けられます。<dfn> <dl> <dt> <dd>
<dl>
<dt><dfn>セマンティックHTML</dfn></dt>
<dd>Webページの要素が持つ意味を明確に伝えるHTMLの記述方法です。</dd>
<dt>AI</dt>
<dd>人工知能(Artificial Intelligence)の略です。</dd>
</dl>
<time>
<time>で日時情報(公開日、イベント開催日時など)をマークアップすることで、機械がその情報を正確に解釈できるようになります。例えば、カレンダーアプリへの連携などが容易になります。<time>
<p>この記事は<time datetime="2025-08-21">2025年8月21日</time>に公開されました。</p>
<cite>と<q>
<cite>と<q>は、引用元を明確にし、情報の信頼性を高めます。<q>は短いインラインの引用に、<cite>は作品のタイトルや引用元を示します。<cite>
<p>ティム・バーナーズ=リーは<q cite="https://www.w3.org/People/Berners-Lee/">Webの力は普遍性にあります</q>と述べました。</p>
<address>
<address>で、文書やセクションの連絡先情報をマークアップします。これは、フッターなどで提供される連絡先や執筆者情報などに使われます。<address>
<address>
筆者: ふぁん<br>
お問い合わせ: info@example.com
</address>
具体的なマークアップのBefore/After
例えば、同じ見た目を持つWebサイトでも、その裏側のHTMLの「意味」は大きく異なることがあります。
Before(意味が不明確なマークアップ)
<div class="header">
<div class="logo">ロゴ</div>
<div class="menu">
<span>ホーム</span>
<span>サービス</span>
<span>お問い合わせ</span>
</div>
</div>
<div class="content">
<h1>最新情報</h1>
<div class="post">
<h2>記事タイトル1</h2>
<p>記事の本文がここに入ります。</p>
</div>
</div>
<div class="footer">
<p>© 2025 My Company</p>
</div>
このコードは、divタグにクラス名をつけることで見た目の構造を作っていますが、それぞれのdivが具体的に何を意味するのかは、クラス名を見なければ分かりません。検索エンジンや音声読み上げソフトは、これらのdivがそれぞれヘッダーやナビゲーションであることを推測するしかありません。
After(セマンティックなマークアップ)
<header>
<div class="logo">ロゴ</div>
<nav>
<ul>
<li><a href="#">ホーム</a></li>
<li><a href="#">サービス</a></li>
<li><a href="#">お問い合わせ</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<h1>最新情報</h1>
<article>
<h2>記事タイトル1</h2>
<p>記事の本文がここに入ります。</p>
</article>
</main>
<footer>
<small>© <time datetime="2025">2025</time> My Company</small>
</footer>このセマンティックなコードでは、<header>、<nav>、<main>、<article>、<footer>といったタグが、それぞれのコンテンツが持つ役割を明確に示しています。たとえCSSが適用されていなくても、このHTMLだけでWebページの論理的な構造を理解することができます。機械にとっても人間にとっても、情報が「理解しやすい」形になっているんですね。
このように、少しの意識とタグの知識で、あなたのWebページは見た目だけでなく、その「意味」においてずっと豊かなものになるんです。
https://funfairfanfare.com/%e3%82%bb%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%afhtml-%e8%ab%96%e7%90%86%e6%a7%8b%e9%80%a0-%e6%84%8f%e5%91%b3/ の記事(セマンティックHTML – 論理構造・意味)への追記セクションです。
この記事を検索するユーザーは、HTMLを勉強中の方や、SEO担当者として「セマンティック(意味論的)」という難解な言葉の意味を知りたがっている層です。 単なる「タグの使い分けルール」の説明にとどまらず、トッププロの視点から「なぜ今の時代にそれが重要なのか」を、AIや音声検索といった最新トレンドと絡めて解説することで、読者の納得感を高める内容にしました。
AIや音声検索の時代だからこそ、機械に「意味」を伝える価値があります
セマンティックHTML(意味のあるマークアップ)の話をすると、単なるプログラマーのこだわりのように聞こえるかもしれません。しかし、これは現代のWebマーケティングにおいて非常に実利的な意味を持ちます。
私たちが普段見ているホームページのデザインは、人間には理解できても、Googleの検索ロボットやAIにはただの「文字と画像の羅列」に見えています。そこで、「ここが記事のタイトルです」「ここからがナビゲーションです」とタグを使って教えてあげること(意味付け)が重要になります。
ここでは、きれいなコードを書くためではなく、事業の成果につなげるためのセマンティックHTMLの活用意義についてお話しします。
検索エンジンやAIに誤解されずに情報を渡せます
Googleなどの検索エンジンは、日々進化していますが、それでも人間のように完璧に文章を理解できるわけではありません。
例えば、重要なサービスの名称をただの文字(divタグ)で囲むのと、見出しタグ(h1やh2)で囲むのとでは、検索エンジンへの伝わり方が違います。セマンティックなタグを使うということは、検索エンジンに対して「このページで一番言いたいことはこれです」と正解をカンニングさせてあげるようなものです。
また、最近のAI(ChatGPTなど)が情報を収集する際も、HTMLの構造をヒントにしています。正しいタグ付けをしておくと、AIがあなたのホームページの内容を正確に学習し、ユーザーへの回答として引用してくれる可能性が高まります。
音声検索や読み上げ機能への対応はSEO評価にもつながります
「ヘイ、Siri」や「OK、Google」で検索をする人が増えました。音声アシスタントは、検索結果から答えを拾い上げて読み上げますが、このときもHTMLの構造が整理されているページの情報が優先されやすくなります。
また、目の不自由な方が使う「スクリーンリーダー(画面読み上げソフト)」も、HTMLタグを頼りに「次はメニューです」「ここから本文です」と案内します。
Googleは「すべてのユーザーにとって使いやすいホームページ」を高く評価します。セマンティックHTMLを使ってアクセシビリティ(使いやすさ)を高めることは、社会的な意義があるだけでなく、SEOの観点からも非常に賢い戦略といえます。
メンテナンスのコストを下げ、将来の改修を楽にします
ホームページ(ウェブサイト)は一度作って終わりではありません。数年後にリニューアルしたり、担当者が変わったりすることがあります。
そのとき、すべての要素が意味のない <div> タグばかりで作られていると、どこに何が書いてあるのか解読するだけで膨大な時間がかかります。一方で、<header> や <footer>、<article> といったタグが正しく使われていれば、初めてそのコードを見る人でもすぐに構造を理解できます。
長期的にホームページを運用していく中で、修正にかかる時間や費用を抑えることができるのも、見逃せないメリットです。
完璧を目指さず、主要な部分から取り入れてみてください
すべてのタグを厳密に使い分けるのは、プロでも骨が折れる作業です。無理をして完璧を目指す必要はありません。
まずは、ページの骨組みとなる部分、例えば「ヘッダー(header)」「フッター(footer)」「メインコンテンツ(main)」「ナビゲーション(nav)」の4つを意識するだけでも十分な効果があります。
見た目はCSS(スタイルシート)で整えることができますが、裏側の構造を整えられるのはHTMLだけです。少しの気遣いで、検索エンジンからの評価が変わる可能性がありますので、ぜひ主要なタグから見直してみてください。
セマンティックHTMLでWebの「意味」を追求する

これまで見てきたように、セマンティックHTMLは単なる技術的な話題にとどまりません。
それは、ホームページ(Webサイト)を「人」にも「機械」にも、そして「未来」にも優しく、価値あるものにするためのとても大切な考え方です。
「見た目」と「意味」の調和
Webデザインは、ユーザーの心をつかみ、使いやすさを提供する上で、これからも欠かせない要素であり続けるでしょう。しかし、その華やかな「見た目」の裏側で、HTMLが持つ本来の「意味」を尊重することで、あなたのWebサイトはより深みを増します。
デザインを追求しつつも、裏側の論理構造をきちんと整える。この「見た目」と「意味」の調和こそが、これからのWebサイト制作には求められます。
それはまるで、美しい建物を建てる際に、外観のデザインだけでなく、その基礎や骨組みがしっかりしているかどうかも等しく重要であることと同じです。
基礎がしっかりしていれば、そこにどんな装飾を施しても美しさが損なわれることはありませんし、長く安全に使い続けられます。
Web制作者に求められる視点
私たちWeb制作者は、単にコードを記述するだけでなく、その情報が持つ「意味」を深く理解し、それを最も適切に表現する役割を担っています。これは、まさに「情報設計」という、より広い視点を持つことにつながります。
かつてセマンティックHTMLを意識してページを作ると
「そういうことじゃないよ。ダサいよ」
とグラフィックデザイン系の人たちに笑われたものです。
セマンティックHTMLを意識することは、短期的な作業効率だけでなく、Webサイトが検索エンジンに適切に評価され、多様なデバイスやAIに理解され、そして長期にわたって価値を提供し続けるための重要な要素の一つとなりつつあります。
Webの進化は止まりません。AIの登場によって、Webコンテンツのあり方や利用され方は、これからさらに大きく変わっていくでしょう。そんな時代において、意味が明確で構造化されたHTMLは、あなたのWebサイトがそうした変化に柔軟に対応し、これからも多くの人に必要とされ続けるための確かな基盤となるはずです。
ぜひ、Webサイトを作る際は、その「見た目」だけでなく、そこに込められた「意味」にも心を配ってみてください。
それが、より良いWeb、そしてより良い未来を創る一歩になるはずです。