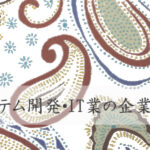少し長いタイトルですが、今回は「オウンドメディア運営には本腰を ブームに流されずに計画的に」と題しまして、近年浸透してきた「オウンドメディア(Owned Media)」について触れていこうと思います。オウンドメディアとは、自社が主体となって所有・管理するメディアのことを指します。具体的には、自社Webサイト内のブログ投稿、コラム記事、特設ページなどのページコンテンツ、そして動画コンテンツ、メールマガジンなども含まれます(広義にはパンフレットやホワイトペーパーも含まれます)。特にWebにおけるコンテンツマーケティングでは、検索エンジン経由での集客を目的としたSEOコンテンツ、SNSからの誘導を意識した記事、問い合わせやリード獲得につながる記事の配信などが中心となります。
弊社、ホームページ制作 京都のWeb制作会社ファンフェアファンファーレでは、WordPressを利用したホームページ制作(ウェブサイト制作)、そしてWordPressなどのCMSを利用したオウンドメディア構築のお手伝いをさせていただいております。
さて、本題ですが、巷ではオウンドメディアブームというワードが飛び交っていることがあります。
「そもそもオウンドメディアって何だろう?」
「オウンドメディアの運営って手間がかかりそう。外注するほうがいいのかな…」
「オウンドメディア運営にも注意点などがあるのだろうか?」
そんな様々な疑問についてお伝えしていきます。
コンテンツマーケティングがWebマーケティングの方法として着目されてから、オウンドメディア運営に乗り出す企業も増えています。もちろん私たちもこうしたオウンドメディアによるコンテンツマーケティング導入を推奨していますが、ホームページ内のオウンドメディア運営自体にはプラス要素もあるものの、注意点もたくさんあります。従来のマスメディアや広告媒体と異なり、オウンドメディアは自社のブランドコンセプトやマーケティング戦略を即時的に直接反映させることができます。そして定期的な購読やコンテンツのストック性によって中長期的に顧客との接点を築いていける特徴があります。潜在顧客層からの認知獲得から見込み客の育成、既存顧客との関係の強化まで一貫して行うことができます。
それではまず、「オウンドメディア」自体について、その内容や企業による活用の例についてから見ていきましょう。
オウンドメディアは昔から活用されている

まず、オウンドメディアは昔から活用されています。特に揚げ足を取るわけでも何でも無く、オウンドメディア自体は、10年以上前から企業のWebマーケティングのひとつとして積極的に活用されています。企業ブランディングとWebマーケティングの基盤として重要な位置づけとなっています。
広義のオウンドメディアである「ウェブサイト」を指しているわけでもなく、コンテンツの配信という意味では、10年以上前からレンタルブログなどでオウンドメディア運営自体は行われています。
もっと広い意味で捉えた場合には、定期的なニュースレターの送付などもオウンドメディアです。
「自社メディア」という意味では、かなり昔からマーケティング・PRにおいて活用されている方法ではないでしょうか。
広義のオウンドメディアと狭義のオウンドメディア

オウンドメディアとは、広い意味では「自社メディア」というような意味があるため、自社発信の情報コンテンツがあるのならば、オウンドメディア運営にあたりますし、こうした情報の発信に着目すればかなり昔から活用されてる方法であると考えることができます。
狭義のオウンドメディアである、ホームページ内にコンテンツ投稿システムを設置して行うオウンドメディア運営は比較的最近の流れですが、外部のブログサービスを利用して連携させていた、というものと構造としては近いものがあるため、狭義のオウンドメディアの歴史も意外と長いと考えることができます。
サイトの内に組み込むオウンドメディアの出現
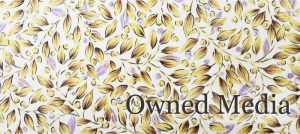
ただ、Webマーケティングの分野において、オウンドメディアが注目され、かつオウンドメディアを自サイト内に組み込むという意味では、その流れは比較的最近のことです。
レンタルブログ⇒mixi⇒Facebook・Twitter(現 X)⇒WordPress
のような流れになっているだけで、ソーシャルの活用などで途切れること無く昔からこの仕組は続いています。
企業ホームページ内部にオウンドメディア機能を組み込むことが、高度な技術を要し、予算的に難しかったため、WordPressやMovable Typeなどが登場する前は、外部ブログなどの利用という形でオウンドメディア運営がなされていました。
ブログからSNSに移行

その後SNSなどの登場により、アメブロやライブドアブログなどからSNSに移行したりという形で運営方式が変化しているだけで、企業による情報発信、コンテンツ発信自体は古くから姿形を変えながらも積極的に行われています。
新しい情報発信の形、オウンドメディアの形が登場する度に、ユーザーの居所も変化するため、どのオウンドメディアを利用すればよいのかというふらつきがあるのも事実でしょう。
という私も2004年ごろにはライブドアブログなどを利用し、上記の流れで個人的なコンテンツ生成の場を彷徨った一人です。余談ですが、その少し前からホームページ制作(ウェブサイト制作)には手を出していました。
…
なんでもそうですが、ブームというものはリスクが高い性質があります。爆発的に成長した市場は、期待値が上がりすぎて、その後急下落を起こすことが多いのは確かです。オウンドメディア運営もその例外ではありません。
WordPressなどのブログCMSを利用し、企業ホームページ内のブログとSNSを併用

時代が進んでレンタルブログサービスからSNSに移行するという流れもありましたが、その後企業ホームページのベースシステムとしてWordPressなどのブログCMSを利用する流れになりました。そしてオウンドメディアとしては、SNS単体の利用から企業ホームページ内のブログとSNSを併用する流れになりました。
ユーザーの行動を喚起するコンテンツの制作・Webライティング
ホームページ上で行うオウンドメディアに限らず、コンテンツの制作・Webライティングにおいては、単なる情報提供に終わらせずにユーザーの行動を喚起するCTA(Call To Action)の設計に基づくことが重要です。資料請求・問い合わせ・LINE追加・商品購入など、どのアクションを促したいのかを明確にし、本文との文脈を自然に繋ぐCTA配置が求められます。特に、導線設計とページレイアウトを同時に設計する「コンテンツとUX」の発想が、CV率の向上に大きく寄与します。
さて、次にオウンドメディア運営開始にあたってぶつかる壁や注意点などについて見ていきましょう。
計画的にオウンドメディア運営を

オウンドメディアは基本的にブログ形式で、新しいコンテンツを発信していくというものですが、ブログ慣れしていないうちは、一つの記事を書くのに相当の時間を費やします。300文字程度でもなかなか書けないものです。
しかしながら10記事くらい書くと、なんとなく感覚がつかめてきます。そしてその後は一気にブログ記事を書いてしまうのですが、記事の配信数はある程度安定している方が、メディアとしては形がキレイです。
オウンドメディア運営の最初の課題、ぶつかる壁は、「コンテンツが書けない」ことです。企業サイト内にオウンドメディアを導入してみたものの、肝心要の記事を配信していくこと自体につまずいてしまうというケースです。
Web担当スタッフの方がブログ運営経験者であれば、記事配信も楽に進むかもしれませんが、全くの執筆未経験の場合は、「何をどこまで書いて良いのかわからない」というような、未開の地への恐怖心も相まって、最初のコンテンツがなかなか配信できないという壁があることがよくあります。オウンドメディア運営において、計画性はWebマーケティング効果を大きく左右する要素となります。思いつきでコンテンツを企画し制作・公開していても、ユーザーのニーズと検索意図に合致しないコンテンツが増え、結果としてアクセスが伸びません。その結果、Webマーケティング効果が現れない状態になりがちです。ターゲット設定も極めて重要です。自社の製品やサービスの特性を再確認した上でユーザーがどのような悩みや欲求に基づいて検索し、どのような情報に価値を感じるのかを想定しておくことで、キーワードの選定や記事構成の方向性がぶれなくなります。
計画的なオウンドメディア配信ができない

そして、次の課題は、運営者の情報ストックが尽きた時にホームページの更新、コンテンツの配信が止まってしまうなど、計画的なオウンドメディア配信ができないという問題点です。これを防ぐためには、オウンドメディアによるコンテンツマーケティングの施策設計の段階から中長期視点でのロードマップを描き、継続的な運用を前提とした計画が重要になります。
ある程度計画的にオウンドメディアの運営を行わないと、メディア自体の印象が変になります。
例えば、1年のうち、1月1日から書き始めるとして、1月、2月は毎日更新されていたものの、9月、10月頃には月に1記事、そして12月はゼロ、そして翌年からは更新なしという状態のオウンドメディアが、その後3年くらい放置されていた場合、あまり印象は良くないものです。
個人的なブログならばそれでも構いませんが、企業やお店のメディアにおいて、そういった状況はユーザーによっては
「閉店したのでは?」
「この会社は今でも運営されているのだろうか?」
「ここに掲載されたサービスは今でも稼働しているのだろうか?」
という疑念すら起こりうる可能性があります。
これに対応するためにはオウンドメディアのKGI(最終的な成果指標)とKPI(中間の進捗指標)をある程度設定しておいた方が無難です。企業間取引(BtoB)企業の場合であれば「月間10件の資料請求」、個人向けのBtoCであれば「毎月1000UUの新規流入」といったように、目的に応じて数値目標を定義してそれに対応するコンテンツカテゴリや更新頻度を設定していきます。
「コンテンツマーケティング」や「オウンドメディアブーム」という言葉を気にせずに、気楽に更新できる内容の短文サブコンテンツでも良いのではないでしょうか。それでもPRとしては、十分に価値のあるものだと考えています。
よくわからない言葉が飛び交う昨今
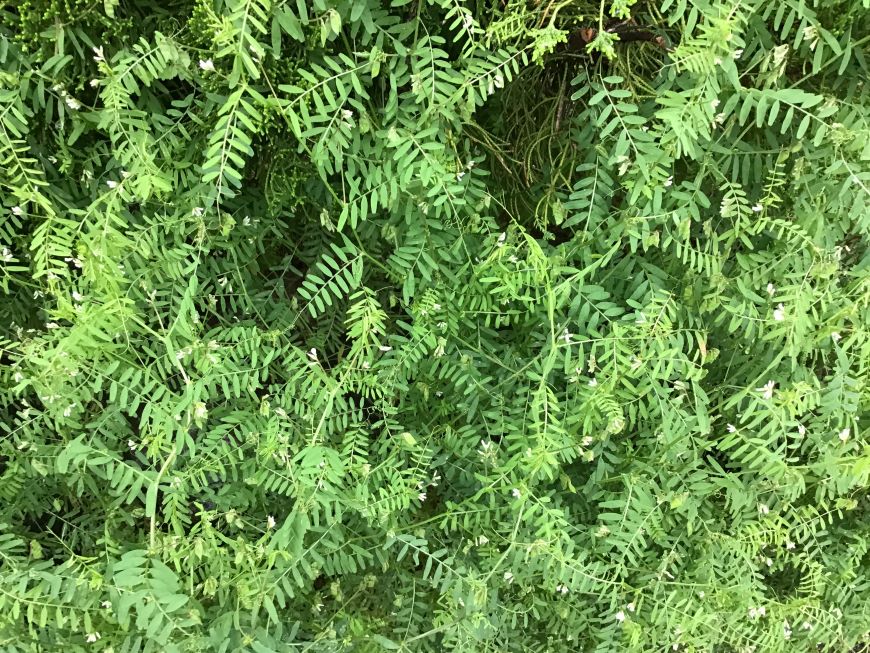
「Webマーケティング」くらいまでは、なんとなく意味がわかりますが、「UIデザイン」「UX」「DX」「SEO対策」いう言葉になると、日本語訳としては意味があまりわからないものになります。
直訳すると、「UIデザイン」は「利用者と機器の意志伝達のための意匠」、「SEO対策」は「検索エンジン最適化対策」というふうになります。なんだかわかるようなわからないような言葉です。
「検索エンジン対策」の方が意味としては理解できるはずですが、「検索エンジン最適化」を対策するということはなんだか理解できません。しかも、検索エンジンは敵でも、害でもありません。そういうわけで、何でも専門用語をくっつければ良いわけではないと考えます。
外来語や略語をなんとなくくっつけただけの言葉なのですが、「また新しい用語が出てきた」となれば、オウンドメディアを運営しようとされる企業のウェブ担当者の方からすれば、それだけで、辟易してしまうのではないでしょうか。
ひとまず近年は、こういったウェブの略語とマーケティングとかデザインという言葉をなんとなくくっつけただけの言葉が飛び交っていますが、そのような言葉を追うより、商いやサービスの根幹を意識するほうがよっぽど賢明だと考えます。
という余談でした。
オウンドメディアでのコンテンツ配信の時に変な用語を使ってしまうと、企業の資質が問われるというようなリスクもあります、というような注意点でした。
オウンドメディア運営には「本腰」が必要です

さて、話を戻しますが、見出し通り、オウンドメディア運営には「本腰」が必要です。
理由はただ一つ、先の例のようにオウンドメディア運営が途中で終わってしまっては、ウェブPRとしては逆効果になりかねないからです。
10年、とまでは行かなくても、向こう3年、それが無理なら1年間でも、年間での配信数をある程度想定しておくと先のようなリスクは回避することができます。
オウンドメディア運営の最初の壁は「文章がうまくかけない」とか「どうしても日記コンテンツ的になりがちで、きちんとしたコンテンツを作り上げることができない」とか、「最初の1ページが書けない」と言うものですが、その次に訪れる、「オウンドメディアに慣れてきた時に、一気にコンテンツを出し切ったあと、ネタ切れ状態が続いて更新が止まる」というようなことや、「Web担当スタッフが抜けてしまって、更新が止まってしまう」という状態へのリスクについても予め対応策を考えておいたほうが良いかもしれません、
オウンドメディアにおいてコンテンツの品質は最も重要な要素ですが、その質は単なる文章の上手さや専門知識の有無に留まりません。ユーザーの検索意図と合致しており、適切な文脈の中で「読む意味がある」と感じてもらえるかどうかが、オウンドメディアコンテンツとしての価値を左右します。コンテンツの集客力を高めるためにはコンテンツ企画の段階から検索需要、読者心理、ページ内導線、UI/UX、SEO施策を総合的に設計する必要があります。
外部ライターの方に依頼するケース

最近ではオウンドメディアコンテンツの執筆を外部ライターの方に依頼するケースもあるようですが、メディアサイトほどの規模を想定していないのであれば、それは避けたほうが良いかもしれません。
自社のことを一番知っているのは自社の方々ですし、企業の色とのミスマッチが生まれるリスクがありますからね。
もしWebライティングにかかるライターの方を利用される場合は期間を定めての連載のような形のほうが良いような気がします。
外部依頼できない自社独自のコンテンツを多用なフォーマットで用意する
独自性を高めるためには外部依頼できない自社独自のコンテンツを多用なフォーマットで用意することが重要です。コンテンツの種類も多様であるべきで、ノウハウ記事やコラムだけでなく、ホワイトペーパー、事例紹介、Q&A、用語解説、動画インタビュー、比較表、チェックリストなど、多様なフォーマットで企画を展開することでユーザーの接触機会を増やし、メディア全体の厚みを持たせることができます。これにより、ユーザーのステージ(認知・検討・比較・意思決定)に応じた情報提供が可能となり全体のWebマーケティング力強化につながります。
良質の固定ページ

読み物のような一般記事を定期配信するよりも、コンテンツによるWebマーケティング・SEM(検索エンジンマーケティング)などを狙うなら、良質の固定的なページ(ストック情報)を制作したほうが、更新の停滞によるマイナスイメージのリスクはありません。
またこうした良質の固定的なページのコンテンツは、事業に関連する情報であるため、コンテンツSEOにも直接的に効果があります。事前にカスタマージャーニー(認知・興味・比較・購入・継続)に基づくコンテンツの企画設計を行えば、ホームページへの流入からコンバージョンに至るまでの導線も明確になります。
ウェブPRとしての気楽な記事

「オウンドメディア運営には本腰が必要です」と書いてしまいましたが、放置状態を避けられるのであれば、ウェブPRとしての気楽な記事の更新の計画だけでも十分だと考えます(SEO上の対策は別問題として残ります)。
ただ、SEM(検索エンジンマーケティング)やコンテンツSEOによるSEO効果を狙うならば、メディアサイトでない限り、高クオリティのストック情報の方がおおむね効果があります。
しかしながら、気楽で簡単な記事を気軽に投稿すると「このホームページはよく更新しているな」という印象に繋がります。
オウンドメディア運営のリスク

先に少し触れましたが、ブームの流れに乗って、オウンドメディアを構築した場合でも、向こう3年間などで記事の配信数が偏ったり、最終更新日から相当の期間が経過していたりすることは、コーポレートサイトなどに組み込まれたオウンドメディアの最大のリスクだと考えています。
「オウンドメディアを運営しないこと」よりも、こちらのほうが危険です。
例えば、「あけましておめでとうございます」
という一文が最新記事として掲載されていて、投稿日が2012年1月1日だった場合を想定していただければわかりやすいのですが、サイトを見るユーザーによっては、「もしかしたらテストサイトかもしれない」という疑念すら起こります。
するとそのサイトに掲載されている情報のすべてが古い情報で、信頼性がないと判断される可能性もあります。それはユーザーにとっても検索エンジンにとってもです。
信頼のできない情報が掲載されているサイトは信用されません。
オウンドメディア運営にとって、寸分の狂いもない計画というものは必要ありませんが、せめてこのリスクだけは避けた方が良いでしょう。
また、少し余談でお伝えした、用語の使用方法を含めてコンテンツの品質が低いものばかりになった場合は、企業の資質が問われ、ブランドイメージにマイナスになるリスクもあることも注意しておきたいところです。運営体制の整備も重要であり、記事の企画・執筆・校正・公開・分析の流れを明確化しておくと運営が楽になります。可能であればそれぞれに担当者を置いておけばコンテンツの品質低下を招きます。特に、専門性の高い業種であれば、社内の技術者や現場担当者から一次情報を引き出し、編集部門がそれを文章化する体制を構築することもできます。
弊社では、WordPress(ワードプレス)をベースとしたオウンドメディア構築などのWeb制作サービスを提供しております。
(初回投稿日 2016年4月19日)