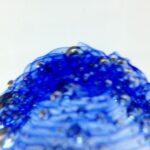ソーシャルメディア(SNS)はあくまでWeb上のプロモーションでの二次ツールとして利用するとよいと考えることができます。Webマーケティングのひとつとして、SNS・ソーシャルメディアを運用するという方法もありますが、なるべく自社のホームページや配信コンテンツと連動させて相乗効果を狙う方向で「Webマーケティングの二次ツール」として運用されることをおすすめします。
ソーシャルメディアの強み、ソーシャルメディアマーケティングの強みは、シェアによる客観性と、ユーザーとの距離の近さにあります。
広告性の高いリスティング広告などの利用に比べてソーシャルメディアマーケティングはユーザーとの距離の近さの分、臨場感を与えやすい傾向にあります。
しかしながら、Webマーケティングにおいてソーシャルメディアを利用する場合は、あくまでコンテンツマーケティングの二次ツールとして利用することを検討したほうが良いでしょう。
Webマーケティングはオウンドメディアを活用しコンテンツマーケティングに取り組むことに加えソーシャルメディア・SNSを二次利用することでさらにWebマーケティング効果を高めることができます。
ソーシャルメディアでの直接的なWebマーケティング活動
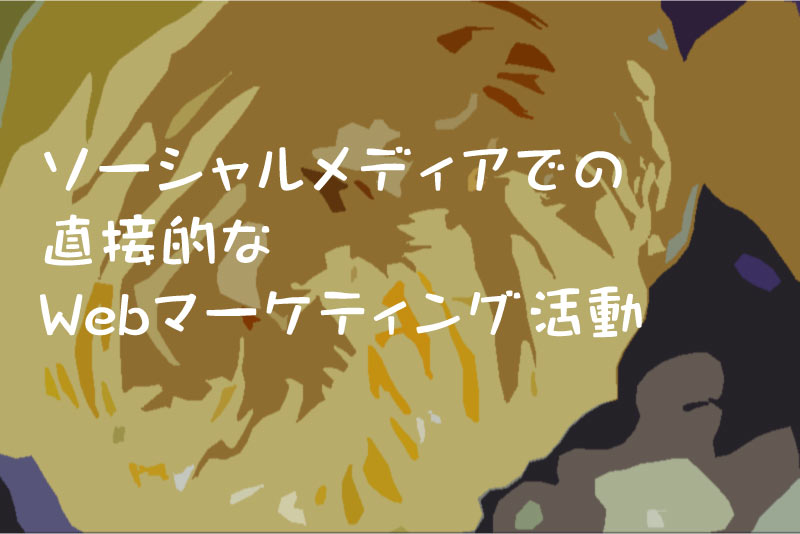
ホームページのコンテンツページヘのシェアボタンの設置や公式アカウントでの投稿などで、公式ホームページへのアクセスを向上させることができるほか、ソーシャル単体での直接的なマーケティング活動も可能です。SEO、SNS、メールマーケティング、広告運用、CRMなどのチャネルを横断的に設計することでシナジーを生み出します。
ソーシャルメディア・SNSの代表例は、Facebook、X(Twitter)、Google+、Instagramなどです。近年ではLINEなども対象になっています。ソーシャルメディアでコンテンツを拡散することがコンテンツマーケティングの効果拡大には有効的です。
そして、そうしたソーシャルメディアでは、第三者によるシェアによるWebプロモーション力向上、検索エンジンなどに依存しない安定的なサイトトラフィックの一つの要素として活用することは可能です。ただ、ソーシャルメディアでの直接的なWebマーケティング活動には賞味期限のような単発性があり、継続して安定したマーケティング効果を期待することはできません。
FacebookでのWebマーケティング
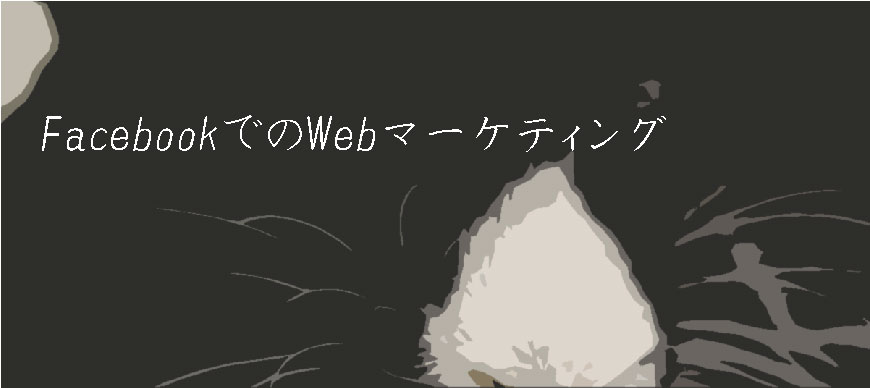
一時期FacebookでのWebマーケティングが注目されましたが、大企業と異なり、中小企業や地域のお店では書籍などで紹介されているようなFacebookを利用したプロモーションでは費用対効果が見込めません。
基本的にFacebookは個人対個人のコミュニケーションツールのため、一方的なプロモーションは嫌がられる傾向にあります。
一方的なプロモーションを続けると、「広告のようで鬱陶しい」という印象がつき、PRとしては逆効果になりかねません。
どちらかというと個人事務所などで、コメントのやり取りなどによる「ユーザー間コミュニケーション」を軸としたWeb集客が功を奏する傾向にあります(むしろ集客は結果であって、集客目的のプロモーションを行っても意味がないと考えることができます)。
ソーシャル広告
検索結果に連動した形で広告を表示するリスティング広告とは異なった形のWeb広告として、Facebook広告やX広告(Twitter広告)などのソーシャル広告を利用するという方法もあります。
リスティング広告は、特定の検索キーワードに連動した形で広告が表示されるのでマーケティングとしてのマッチ性は高いですが、その分広告要素が強く、既にニーズが顕在化したユーザーに対してのアプローチに適しており、新しいプロモーションには不向きです。
逆にソーシャル広告は、直接的なマーケティングよりも少し手前にある、ニーズが顕在化していない様なユーザー層にも的確にアプローチすることができるため、PR的な新規プロモーションには向いている傾向があります。
業種によってはソーシャルメディア活用が不向き
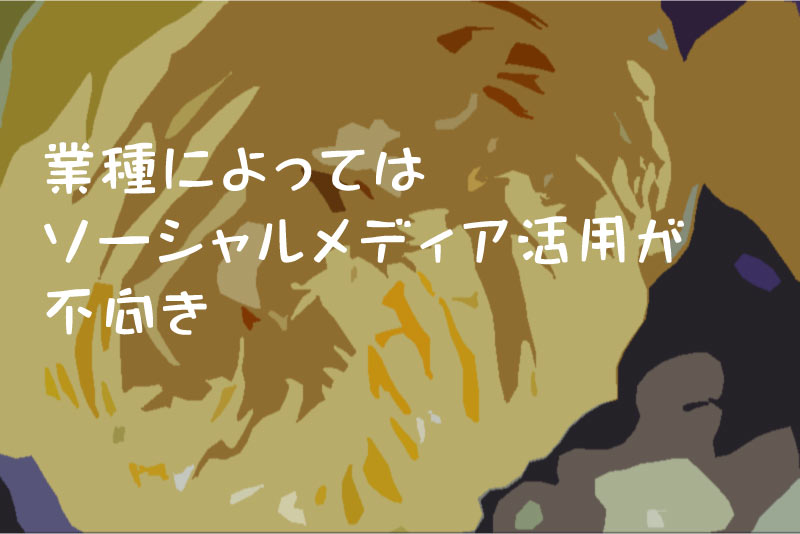
一般消費を対象とした業種は、Facebook、X(Twitter)、Google+、Instagramなどソーシャルメディアの活用と相性が良いですが、企業間取引のみの企業など、業種によってはソーシャルの活用が不向きな場合があります。
Webマーケティング活動としてのソーシャルメディア活用はプラス要因にはなりますが、その活用の効果は、業種によって異なり、また、実質ユーザー数の変化により、時代によって変化することが考えられます。
SNSのタイムラインの投稿は、時系列的に流れていくため、あくまで、公式ホームページを軸として「二次ツールとして」ソーシャルメディアを活用することが望ましいといえるでしょう。
個人的な活動との混同は避けよう
極端な例としては、例えば運送会社において、代表者の「趣味の料理」ばかり運送会社のSNS公式アカウントで配信してもマイナスイメージになりかねません。代表者の個人アカウントで活動する分には問題がありませんが、あくまで企業の公式アカウントでは、業務に関連した配信だけを心がけるほうが無難でしょう。セッション数、オーガニック検索流入、直帰率、滞在時間、CTAクリック率、資料請求数といった定量指標に加え、ヒートマップやユーザーインタビューなどで得られる定性データを組み合わせます。これらを月次レポートとして可視化しチーム全体で現状認識を合わせることが重要です。
SNSとホームページ(ウェブサイト)を使い分けることの重要性
現代において、事業の情報を発信するツールとしてSNSが非常に強力で便利なのは間違いありません。手軽に最新情報を届けられ、お客様との距離を縮めることができる、素晴らしい手段です。
しかし、その手軽さゆえに、ホームページ(ウェブサイト)の運用を疎かにし、事業の情報発信のすべてをSNSに頼りきってしまうのは、実は大変危険なことかもしれません。
私たちが常に意識しておかなければならないのは、「ほとんどのお客様は、あなたのSNSにログインしていない」という事実です。
事業主自身が日頃からSNSを熱心に使っていると、情報を見に来るお客様全員が同じようにSNSのアプリを開いて、あなたの事業のアカウントを熱心にフォローしていると考えがちです。ですが、実際には、初めてあなたの事業を知った方や、特定の情報だけを求めて検索エンジンからたどり着いた方が、たまたまSNSアカウントを見たとしても、アカウントをフォローしているとは限りません。
ログインの壁が情報を阻む可能性
SNSには、そのプラットフォームの特性上、大きな「壁」が存在します。
例えば、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、利用していない人やログアウトしている人に対して、積極的に最新の投稿を見せようとはしません。多くの場合、「ログインまたはアカウント作成」を促す画面が表示され、それ以上スクロールしても、直近で配信した「休業日のお知らせ」のような大事な最新情報が見れないようになっているかもしれません。
お客様がWeb検索や公式ホームページからSNSアカウントに移動したとしても、ログインの「壁」に阻まれて、知りたい情報にたどり着けない、という状況が起こり得るのです。これは、お客様にとってストレスであり、事業側にとっては情報伝達の機会損失になってしまいます。
SNSは「玄関」、ホームページは「家」
SNSは、あくまでも「集客の玄関口」や「最新情報を素早く発信する拡声器」として捉えることが重要です。その役割は、多くの人に情報を届け、興味を持ってもらい、「もっと詳しく知りたい」と思わせることにあります。
そして、お客様が「もっと詳しく」知りたいと思ったときに、いつでも誰でも、アカウントの有無やログイン状態に関係なく、事業の基本的な情報、商品やサービスの詳細、そして過去の情報が整理された状態で確認できる「家」のような場所が必要です。それが、あなたの事業の公式ホームページ(ウェブサイト)です。
事業の情報発信において、SNSとホームページ(ウェブサイト)は、それぞれが持つ役割を理解し、お互いを補完し合う関係で運用していくことが重要になります。手軽さに頼りすぎず、誰でも情報にアクセスできる環境を整えることが、長く安定した事業運営の土台を築くことにつながるでしょう。
「SNSで告知済み」は危険信号「休業日案内」が届いてない!お客様の信頼を削る小さな放置
(初回投稿日 2015年10月4日)
ホームページ制作&Webマーケティング 京都

ホームページの制作・企画・運営・更新やホームページのSEO対策、ローカル検索対策などのWeb制作サービス、Webマーケティングなら、京都のWeb制作会社(ホームページ制作会社)
株式会社ファンフェアファンファーレへ!
ホームページ制作 京都 ファンフェアファンファーレは、Webマーケティング効果を最大限に引き出すSEOに特化したホームページ制作やカスタマイズ、SEOを手がけております京都市のWeb制作会社(ホームページ制作会社)です。
「ホームページ制作」京都府京都市内エリア(上京区、中京区、下京区、東山区、右京区、左京区、北区、南区、西京区、山科区、伏見区)では、ホームページ制作・作成・SEO対策等のWeb制作サービスにつきましては、ご訪問での打ち合わせ・ヒアリング・ご提案をさせていただいております。SEO・Web集客・WebマーケティングにかかるWebコンサルティングもご対応可能です。