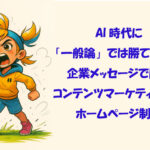今回は、「ホームページのコンテンツ改良の必要性と期間限定コンテンツ」と題しまして、サイトの改良、コンテンツの改良の必要性についてお伝えしていきます。ホームページ公開時点からある程度の期間が経過している場合は、コンテンツ(ホームページ掲載内容。主に文章)の改良を検討してみましょう。文のリライトを中心としたページの改良です。
コンテンツの質を測る上で、もちろん記載内容の正確性や情報の網羅性などは重要な要素ですが、期間が経過すれば当然に社会の仕組みも変化していくようにコンテンツ内容の概念も若干変化していきます。
そうした時流に合わせていくということもコンテンツの質を考える上では大切な要素です。
ただし、その一方で、期間がすぎればほとんど価値をなさない「期間限定コンテンツ」というものもあります。
またホームページの場合は、必要な情報が不足していることもよくあります。そうしたコンテンツを見直し改良していくことで、ホームページ自体を作り変えたりするよりももっと簡単に効率的にWebマーケティング効果を高めていくことができます。
コンテンツの質とリライト

以前、「良質なコンテンツのタネは現場にたくさん落ちています」というタイトルで、コンテンツ制作についてお伝えしましたが、どんな良質のコンテンツも、それを作った段階では、100%の完成度であるかどうかはわかりません。
コンテンツ制作の段階で、もちろん100%の完成度を目指すのですが、そのコンテンツを3ヶ月後、半年後、一年後に読み返すと、不十分な点が見えてくることがあります。
それは、コンテンツ制作者・Webライター自身のレベルが上ったことも関係しているでしょう。もちろんコーポレートサイト(企業サイト)内の投稿であれば、企業のレベルはもちろんそのあり方が変化したという場合もあります。
「完璧だと思っても、その先にまだ質を高める要素があることが見える」という点は、観察者のレベルアップに起因していると推測されます。
こうした時に既存ページのリライトを検討してみましょう。
コンテンツの質と評価の変化

合わせて、進歩が著しい業種であれば、コンテンツの質と評価はどんどん変化します。
かなり前のコンテンツは、もしかしたら「過去の情報」として、アーカイブ資産としての価値だけが残る場合もあります。
これはコンテンツマーケティングなどにおける記事コンテンツがメインですが、もちろん企業の公式ホームページなどのページでも同じようなことが考えられます。
検索エンジンにおける評価の変化とSEO
検索エンジン上のコンテンツ評価の変化としては、検索エンジンにおけるアルゴリズム変更、特にAIの導入によって評価のあり方が年々変化しています。コンテンツ自体の文脈や情報の新しさ、ユーザー体験の比重が高まっています。コンテンツの質の判断において情報の網羅性や構成の整合性だけでなく、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視する傾向にあり「ユーザーが満足するコンテンツ」が評価されるようになってきています。また、ユーザー側の情報収集のあり方も変化してきています。スマートフォンの普及によって、情報を「流し見」する傾向が強くなり、一方で、特定の悩みや比較検討の段階においては、より詳しく信頼性のある情報を求める傾向が強まっています。
ホームページ制作では、その「ホームページのでき」を測る時、Webデザインや操作性などがよく重視されますが、ホームページで最も大切なのは情報の中身であるコンテンツです。どのようなページであっても、読み手にとっては記載内容が不十分である可能性は常につきまとっています。
記載内容が不十分

もちろん、企業などの情報を全て公開する必要はないと考えますが、会社案内ひとつとっても記載内容が不十分であるケースがあります。
特にコンテンツマーケティングにおいて、コンテンツは公開して終わりではなく定期的にリライトを行い質を高めていくことが重要になってきます。リライトは、単なる文言の修正にとどまらず、情報構造の見直しやデータの更新、読みやすさの向上、ユーザー導線の最適化といった様々な視点で内容を考えていくことができます。
リライトを実施するかどうかの判断は、アクセス数や離脱率といった行動データの変化です。Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを活用してアクセスが減っている主要ページや記事を確認することで対象を見つけていくことができます。CTR(クリック率)が低い記事や滞在時間が短くなっているページを特定することでどのコンテンツが評価が低いのかが見えてきます。
ホームページのコンテンツも記載内容が不十分であることがほとんどです。
サービス内容のページであっても、価格表などの「事実としての情報」以外にも、伝えておくべき点は、探せばたくさんあります。ここで問題になるのが、「何をどのように改善すべきか」の判断です。
そんな時にヒントとなるのが実際の顧客からの声です。
実際の顧客からの声を参考にコンテンツをリライト・追記

実際の顧客からの声を参考にコンテンツをリライト・追記するというのが、コンテンツの質を高めるのに最良の方法のひとつです。顧客の声は、実際のニーズや不安、不満、価値観を知るための信頼性の高い情報源です。コンテンツを改善する際に、顧客との接点から得たフィードバックをそのまま反映することでコンテンツの質を高められる他、検索ユーザーの行動に合ったページになる可能性も秘めています。
電話でのお問い合わせを受けて、電話越しに顧客から「問い合わせられた点」などがそのわかりやすい例となるのではないでしょうか?
その質問点・疑問点自体が、不足している情報の代表例として考えられるポイントです。ただし、もちろん競合他社との関係上、公開を控えている部分もあると考えられますから、質問が多い項目がそのままイコールで「不十分な項目」というわけではありません。
電話やメールにおけるお問い合わせ内容や営業現場でのやり取り、SNS上の口コミ、カスタマーサポートの対応履歴、アンケート結果などは非常に参考になります。何に不安を感じ、どこに不足情報があるのかが直接的に見えてきます。
ただ、こうした質問の多い項目をまとめて「よくあるご質問ページ」を作成したり、個別の項目に対する解説をコンテンツ化するのもホームページの改良、コンテンツの改良という面では最も理想的な形ではないでしょうか。
コンテンツを読みなおす

また、ホームページのコンテンツの改良には、実際に消費者目線に立ってコンテンツを「読みなおす」ということも良い方法です。
どうしても、文章作成などを手掛けるコンテンツ制作者や、その業種に精通している方の場合は、コンテンツ内容に精通しているがゆえの盲点が発生することがあります。
そんな時は、自社スタッフや業界人以外に確認してもらうということも一つの方法です。深いところまで知り尽くしているがゆえに見えにくい点というのもありますからね。
その時は、コンテンツの出来具合というよりも「質問」を求めると良いかもしれません。
コンテンツを見て無理矢理にでも記載項目について質問をしてもらうという方法です。
全てを記載する必要はありませんが、コンテンツの精度を高めるという点を意識すれば、いくらでもコンテンツは良質なものになっていきます。
その結果、実際のWebマーケティングにおいても結果が変わってくるでしょう
SEOの要素も完全には「最適化」されていない

SEOとは、サイト全体やページを検索エンジンに最適化することを意味します。その結果、Googleなどの検索結果において、上位に表示され、サイトへのアクセスが向上します。
その大前提となるのが、サイト(ホームページ)のクオリティや、ページのコンテンツの質です。
そして、次の段階として、適切なページの作りとしてSEOの出番がやってきます。
検索結果順位を決める検索エンジンのアルゴリズムも日々改良されていますが、ページを作った時点から、よくよくページを見直すとSEO施策が施されはしているものの、厳密な意味で検索エンジンに「最適化」されていない場合も多々あります。
それはせっかく作りこんだホームページ(ウェブサイト)や良質のコンテンツが、100%の力を出し切れていないということです。
コンテンツの改良と合わせてSEOも改良
目くじらを立てて検索順位を意識する必要はありませんが、コンテンツの改良と合わせて、そんなSEOの視点も改良すると、ホームページ活用により良い結果が生まれるでしょう。
基本的な内部SEOの概念はほとんど変化しませんが、重要視されるポイントや若干の取扱の変更などがよくあります。
コンテンツページ数の多い大規模サイトであれば、そうした変化に大きく影響を受けますが、一般的な企業ホームページのサイトボリュームであれば、それほどSEOの変化を追う必要はないでしょう。
コンテンツの有効期間

情報には有効期間があると言われることがあります。そう考えると、当然コンテンツにもある程度有効期間があると考えるとができます。
コンテンツ種類によっては、完全に情報が無価値になるということはないのですが、SEM(サーチエンジンマーケティング)としての価値などは、コンテンツを放っておくと、サイト(ホームページ)全体もろとも価値が減少することがよくあります。
それは単一のコンテンツであれば、期間が経過してトレンドから外れるということもありますが、それよりもサイト全体としては、競合が切磋琢磨しているうちに相対的に価値が下がるという現象も意味しています。
そんなことを考えていると、高校生の時「バイト募集」のことを思い出しました。
終わったなら終わったと知らせて欲しい
高校生の時に、あるお店でバイト募集の張り紙がしてありました。
今ではインターネットを利用してバイト探しをする、求人フリーペーパーでバイトを探す、ということが一般的ですが、当時は、求人サイトはおろか、求人フリーペーパーすらほとんどない時代でした。
京都は大学が多い関係からか、高校生がアルバイトをできるところはそれほどありませんでした。
「やっと見つけた!」
そう思って欣喜雀躍した私は、張り紙に書いてあった電話番号をメモして、早速家の固定電話から面接希望の電話をしました。
すると、「ああ、ごめん。はがすの忘れてた」という答えが返ってきました。
些細な事といえば些細な事ですが、当時高校生だった私は、勇気を振り絞って電話したにも関わらず、返ってきたそんな答えに「ぽかん」としました。
いまだにコンテンツの記載内容が有効かは運営者しか知らない

これと同じようなことがウェブ・ホームページでもよくあるのではないでしょうか。
- 「コンテンツの記載内容が有効ではなくなった時点で、コンテンツは削除する」
- 「コンテンツの記載内容が有効ではなくなった時点で、記載内容に打ち消し線をつける」
- 「コンテンツの記載内容が有効ではなくなった時点で、掲載終了という文字を加える」
といった、ホームページ(ウェブサイト)でのローカルルールは、サイト運営者か常連くらいしかわからないものです。
先のバイト募集の例で言えば、コンテンツ作成日が3ヶ月前だった場合、ページが削除も「募集終了」の文字もない場合は、おそらくまだ募集しているという推測がたちますが、個人的には、「本当にまだ記載内容は有効なのだろうか?」という疑問がわきます(先の高校生の時の経験が影響しているのでしょう)。
逆に情報の有効期限の提示やページの最終更新日が表示され、かつ、その日付が直近であれば、その「バイト募集」の情報が未だに有効であるということの確信が持てます。
特に求人情報のような固定的なページではない「期間限定コンテンツ」の場合、そういった配慮が必要になるでしょう。
必ずしも要るわけではないのですが、そういった少しのコンテンツの改良が、ページをより良いものにするだけでなく、その先にいるユーザーの関心をググッとそそるでしょう。
「SNSで告知済み」は危険信号「休業日案内」が届いてない!お客様の信頼を削る小さな放置
コンテンツ改良、まずは現状の把握から

「コンテンツの情報が古いままではダメだということはわかった。ではどのように進めていけばいいのだろう?」
そうお考えの方も多いと思います。
コンテンツの改良と聞くと、新しい文章を書くことだと考えるかもしれません。しかし、本当に大切なのは、いま公開しているコンテンツがどれだけ役に立っているのか、現状をきちんと知ることです。
1. 現在のコンテンツを評価する
コンテンツの評価には、ホームページ(ウェブサイト)の分析ツールが役に立ちます。たとえば、Google Analyticsのようなツールを使えば、次のような数字が見えてきます。
- アクセス数
- ページに滞在した時間
- どこから来たのか(検索エンジン、SNSなど)
- コンバージョン率(購入や問い合わせなどの行動に至った割合)
これらの数字から、「アクセスは多いけれど、すぐに離脱されているな」「特定のページからの問い合わせが多いな」といった、ユーザーの行動を読み取ることができます。
2. 改善点を見つける
次に、これらの数字をもとに、改善すべき点を探します。数字だけではわからないことも多いので、ユーザーの声を聞くことも重要です。
- ユーザーアンケート
- ヒートマップツール
- 直接の問い合わせやフィードバック
ヒートマップツールを使えば、ユーザーがページのどこをクリックしたか、どこまで読んでいるかが視覚的にわかります。ユーザーアンケートで「この記事で解決できなかったことは何ですか?」と直接聞くのも、とても有効な方法です。
3. 改良したコンテンツを公開する
改善点が見つかったら、いよいよコンテンツの改良です。ユーザーのニーズに合わせた情報を加えたり、よりわかりやすい言葉に書き換えたり、図や表を入れて見やすくしたりするのも良いでしょう。
改良版を公開したら、それで終わりではありません。再び分析ツールを使って、アクセス数や滞在時間、コンバージョン率の変化を測定します。「滞在時間が長くなった」「問い合わせが増えた」といった変化があれば、改良が成功したと言えます。
このサイクルを繰り返すことで、あなたのページは少しずつ、そして確実に、よりユーザーにとって価値のあるものに育っていきます。
古い情報はユーザーを遠ざけてしまうかもしれません
コンテンツを改良する上で、とくに注意したいのが情報の鮮度です。古い情報をそのままにしておくと、ユーザーに誤解を与えたり不信感を持たれたりするかもしれません。
たとえば、すでに提供を終えたサービスや、古い料金体系がそのまま掲載されていると、せっかくページを見つけてくれたユーザーをがっかりさせてしまいます。その結果、あなたの事業に対する信頼を損なうことにもつながりかねません。
このような事態を防ぐためにも、コンテンツを更新する際は、必ず社内の関係部署と連携することが重要です。
責任者によるチェック体制を整えましょう
コンテンツを常に最新の状態に保つには、定期的なチェック体制が大切です。たとえば、次のような仕組みを設けることをおすすめします。
- 社内情報とのすり合わせ サービスの変更や新商品の発売など、最新の情報が共有される場を設ける
- 責任者のチェック: コンテンツ公開前に、内容が正確かどうかを責任者が確認する
このような体制を整えることで、ユーザーはいつも安心してあなたのページを訪れることができるでしょう。信頼は、事業を続けていく上でなによりも大切な土台となります。
最新のSEOトレンドと事例
コンテンツを改良する際、検索エンジンの動向を理解することは重要です。最近の検索エンジンは、単なるキーワードの数だけでなく、ユーザーにとって本当に役立つ、質の高い情報を高く評価する傾向にあります。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方
以前から重要とされてきたE-A-T(専門性、権威性、信頼性)に、新たに「経験」が加わり、E-E-A-Tという考え方が注目されています。これは、実際にその分野で経験を積んだ人が書いたコンテンツを、より高く評価するというものです。
たとえば、
- 料理のレシピなら、実際にその料理を作った経験談
- 製品レビューなら、実際にその製品を使った感想
といった、書き手自身の一次情報がとても重要になっています。
音声検索や動画コンテンツへの対応
スマートスピーカーの普及もあり、音声で情報を検索するユーザーが増えています。音声検索では、より口語的で簡潔な言葉が使われるためコンテンツも自然な会話に近い言葉で書くことが大切です。
また、文章だけでなく、動画で情報を伝えることも効果的です。YouTubeなどで動画コンテンツを作成し、ウェブサイトに埋め込むことでユーザーの滞在時間を増やしたり、より多くの情報を伝えたりすることができます。
コンテンツ改良で成果を出した事例
実際にコンテンツ改良で成果を出した事例はいくつもあります。
ある住宅情報サイトは、昔の記事をリライトし、古い記事に、ユーザーが本当に知りたい「実際に住んでみた人の声」や「物件選びで後悔しないためのチェックポイント」といった情報を追加した結果、ユーザーの滞在時間が伸びて問い合わせ数も増えたという事例もあります。
このように、ユーザーの視点に立ってコンテンツを更新することが、結果として検索エンジンからの評価を高めることにつながります。
コンテンツ改良はユーザーの声を聞くのが一番早く、確実です
コンテンツを一方的に発信するだけでなく、ユーザーの声に耳を傾けることでページはさらに魅力的になります。ユーザーと双方向のコミュニケーションをとることで、あなたの事業に対する信頼感も高まるでしょう。コンテンツ改良はユーザーの声を聞くのが一番早く、そして確実です。
1. フィードバックを簡単に集める仕組み
ユーザーに気軽に声を届けてもらうためには、次のようなツールが役に立ちます。
- チャットボット
- 簡単なアンケートフォーム
とくにチャットボットは、「このページで知りたい情報は見つかりましたか?」といった簡単な質問から、ユーザーの疑問を効率よく集めることができます。こうした小さな工夫が、ユーザーが「自分の意見を聞いてもらえた」と感じるきっかけになります。
もちろん直接顧客と接する機会がある場合は、直接ご意見を頂戴するというのも良いと考えます。
2. フィードバックから生まれたコンテンツ事例
ユーザーから寄せられたフィードバックは、コンテンツを改善する大きなヒントになります。
たとえば、 「商品の使い方について、もっと詳しく知りたい」 という声が多ければ「よくある質問(Q&A)」のコーナーを作ったり、使い方を解説する動画を追加したりすることができます。
実際に、あるサービスサイトでは、ユーザーの「料金プランの違いがわかりにくい」という声をもとに、比較表を作成しました。その結果、ユーザーの疑問が解消され契約数が伸びたという事例もあります。
3. Q&Aコーナーやコメント欄を設けるメリット
ページにQ&Aコーナーやコメント欄を設けることは、ユーザーとのつながりを深める良い方法です。
- ユーザーの疑問に直接答えられる
- 他のユーザーの参考になる
- 活発なコミュニティが生まれるきっかけになる
ユーザー同士が情報を交換し合う場にもなり、あなたのページが「ただ読むだけの場所」から「人が集まる場所」へと変わっていくかもしれません。
これらの方法でユーザーとコミュニケーションをとり、集まった声を活かすことで、あなたのホームページはもっとたくさんの人の役に立つ場所へと成長していきます。
(初回投稿日 2016年5月23日)
コンテンツの新鮮さがSEO・検索順位に影響を及ぼすというQDFアルゴリズムや、ホームページのコンテンツ自体の「正確性」の重要性について。